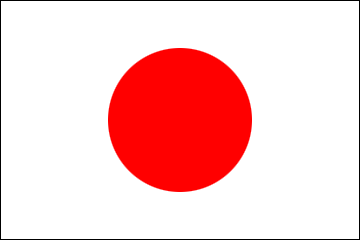生物兵器禁止条約(BWC)
令和5年4月25日
生物・化学兵器の歴史は古く,学問や産業の進歩とともに,人体に有害な生物剤・化学物質に関する研究も発展し,戦争におけるこれらの使用が研究・開発されてきた。 第一次世界大戦では,化学兵器が初めて本格的に使用され,その被害は死傷者130万人以上,そのうち死者は10万人に達したとされる。各国は第一次大戦の終了後も化学兵器を生産・保有等し続けたが,同時に生物・化学兵器の悲惨さは国際社会によって強く認識され,1925年,生物兵器及び化学兵器を規制する初めての国際条約として「窒息性ガス,毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書」(以下「毒ガス等使用禁止に関するジュネーブ議定書」という。)が作成された。ただし,毒ガス等使用禁止に関するジュネーブ議定書は,これら生物・化学兵器の戦争における使用は禁止したが,平時における生産・保有等については何ら規定していなかった。その後,1966年の第21回国連総会において化学兵器及び細菌兵器の使用を非難する決議が採択され,さらに,1969年,ウ・タント国連事務総長が「化学・細菌(生物)兵器とその使用の影響」と題する報告書を提出すると,これらの兵器の規制の重要性について軍縮委員会会議や国際連合の場で活発に議論されるようになり,それぞれの兵器を平時における生産・保有等を含めて規制する条約の作成が目指されるようになった。当初は,生物・化学兵器を一括して禁止する条約の作成が目指されたが,最終的には,比較的作成が容易と見られた生物兵器を禁止する条約をまず作成し,その後化学兵器を禁止する条約を作成することとなった。こうして,1975年に生物兵器禁止条約(BWC,正式名称は「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」(CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION)),1997年に化学兵器禁止条約(CWC,正式名称は「化学兵器の開発,生産,貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」)が発効した。
1 概要
1-1 生物兵器とは
日本が,1982年6月にBWCを批准し,日本国内におけるBWCの実施確保を目的として施行した「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律」が定める定義は以下のとおり。
1-2 生物兵器禁止条約(BWC)の成り立ち
国連事務総長の報告書等を受け,軍縮委員会会議における議論を経て,1971年に軍縮委員会会議において生物兵器禁止条約(「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(BWC : Biological Weapons Convention)」)が作成された。この条約は同年の第26回国連総会決議の採択を経て,1972年4月に署名のために開放され,1975年3月に発効した。なお,条約上では生物兵器の使用を禁止する文言が欠けているが,1980年に実施された第1回運用検討会議において,戦争における使用を禁止する「毒ガス等使用禁止に関するジュネーブ議定書」の遵守が再確認されている。
BWCは生物兵器を包括的に規制する唯一の国際法上の枠組みであり,2023年3月現在の締約国数は184に上る。
1-3 日本によるBWCの批准
日本は,1982年6月にBWCを批准し,日本国内におけるBWCの実施を確保するため,「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律」(BWC実施法)を制定し,生物・毒素兵器の製造,所持,譲渡,譲受けを罰則をもって全面的に禁止した。また,2001年12月には,爆弾テロ防止条約締結に際してBWC実施法を改正し,生物・毒素兵器の使用罪及び生物剤・毒素の発散罪を設け,この罪については国外犯も処罰の対象とした。
日本が,1982年6月にBWCを批准し,日本国内におけるBWCの実施確保を目的として施行した「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律」が定める定義は以下のとおり。
- 「生物兵器」とは、武力の行使の手段として使用される物で、生物剤又は生物剤を保有しかつ媒介する生物を充てんしたものをいう。
- 「毒素兵器」とは、武力の行使の手段として使用される物で、毒素を充てんしたものをいう。
- 「生物剤」とは、微生物であって、人、動物若しくは植物の生体内で増殖する場合にこれらを発病させ、死亡させ、若しくは枯死させるもの又は毒素を産生するものをいう。
- 「毒素」とは、生物によって産生される物質であって、人、動物又は植物の生体内に入った場合にこれらを発病させ、死亡させ、又は枯死させるものをいい、人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるものを含むものとする。
1-2 生物兵器禁止条約(BWC)の成り立ち
国連事務総長の報告書等を受け,軍縮委員会会議における議論を経て,1971年に軍縮委員会会議において生物兵器禁止条約(「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(BWC : Biological Weapons Convention)」)が作成された。この条約は同年の第26回国連総会決議の採択を経て,1972年4月に署名のために開放され,1975年3月に発効した。なお,条約上では生物兵器の使用を禁止する文言が欠けているが,1980年に実施された第1回運用検討会議において,戦争における使用を禁止する「毒ガス等使用禁止に関するジュネーブ議定書」の遵守が再確認されている。
BWCは生物兵器を包括的に規制する唯一の国際法上の枠組みであり,2023年3月現在の締約国数は184に上る。
1-3 日本によるBWCの批准
日本は,1982年6月にBWCを批准し,日本国内におけるBWCの実施を確保するため,「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律」(BWC実施法)を制定し,生物・毒素兵器の製造,所持,譲渡,譲受けを罰則をもって全面的に禁止した。また,2001年12月には,爆弾テロ防止条約締結に際してBWC実施法を改正し,生物・毒素兵器の使用罪及び生物剤・毒素の発散罪を設け,この罪については国外犯も処罰の対象とした。
2 BWCの課題と強化に向けた取組
2-1 BWCの課題
BWCは生物兵器の開発,生産,貯蔵,保有について戦時・平時を問わず包括的に禁止しているが,その一方で,化学兵器禁止条約(CWC : Chemical Weapons Convention)と異なり,締約国の条約の遵守を検証する手段に関する規定がない。1994年に開催された締約国特別会議において,検証議定書を検討するための政府専門家アドホック・グループ(AHG)が設置されたが,バイオテクノロジーや製薬業界等の関連業界への査察受け入れの負担等の影響が懸念される上,使用される生物剤は殺菌による証拠隠滅も容易である等の理由から,検証そのものが極めて難しいという問題があって,交渉は難航した。結局,2001年4月には同グループ議長案が提示されたが,2001年11月の第5回運用検討会議(運用検討会議は5年に一度開催)以降,検証議定書交渉は中断されている。
生物兵器の使用,開発の例としては,1999年に国連イラク特別委員会(UNSCOM)がイラクにおける大量の不法な生物学的活動を発見している。また,1995年のオウム真理教によるボツリヌス毒素・炭疽菌の開発,2001年の米国における炭疽菌事件,2018年のドイツにおけるリシンを用いたテロ未遂事件等を受けて,国家のみならず非国家主体による危険な生物剤を用いたテロ行為発生の可能性が現実的なものとして国際社会において受け止められるようになっている。近年,インターネットの普及やデジタルデバイスの進化に伴い,一般市民が自宅で遺伝子改変等の最先端のバイオテクノロジーの研究を行うことも可能になってきており,生物兵器開発に対するハードルの急激な低下が懸念されている。現在は,こうしたリスク・脅威に対抗する対策も含めた条約の強化が課題となっている。
また,近年,ウイルスの人工合成やゲノム編集といった先進生命科学技術を活用した生物兵器の凶悪化が懸念されるようになった。このため,その汎用性への対処も視野に入れた研究・開発の促進が求められている。
2020年からの新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は,万一生物兵器が使用された場合にも今回と同様の事態を想定させ,生物学的な脅威に対する国際社会の脆弱性への認識が高まった。新型コロナウイルス感染対応から得られた教訓,知見を踏まえつつ,BWCの枠組みの強化について議論を深めることが課題となっている。
2-2 BWC強化に向けた取組
検証議定書交渉の中断後,次の運用検討会議開催までの間に専門家会合と締約国会合を毎年開催し,BWCの強化に関する共通の理解と実効的な措置を促進するための議論を継続することが第5回運用検討会議(2001年)で決定された。第6回運用検討会議(2006年)では事務局機能を提供する履行支援ユニット(ISU)の設置,第7回運用検討会議(2011年)では毎年自国内にある研究施設,生物防護計画,疫病発生状況等について情報提供を行う信頼醸成措置の申告内容の改善,締約国間の国際協力・支援を促進するためのデータベースの立ち上げ,発展途上国の年次会合への参加を支援するための任意拠出金によるスポンサーシップ・プログラムの立ち上げ等の新たな措置について合意された。また,第8回運用検討会議(2016年)では,検証議定書交渉の再開を争点に米国とロシア,非同盟諸国等との対立が続き,第9回運用検討会議までの会期間活動に関する具体的提案の多くについて合意がなされないまま終了した。
2-3 最近の動き
2017年の締約国会合では,第9回運用検討会議(当初2021年に予定されていたが,以下に述べる通り,新型コロナウイルス感染症の影響で2022年8月に延期開催された)までの会期間活動として,毎年専門家会合及び締約国会合を行うことを決定した。また,2018年~2019年の専門家会合及び締約国会合では,バイオテロ対策,急速に進展するバイオ技術の悪用や誤用を防止するための施策,発生初期段階において生物兵器の使用に起因するのか自然発生なのか区別が困難で影響が広範囲に及ぶ恐れのある事案に対する支援,対応及び準備等について,BWCのフォーラムを活用した具体的な施策について議論が進められた。
2020年に入ると,新型コロナウイルス感染拡大により各会合はおおよそ1年間後ろ倒しとなった。専門家会合は2021年8月~9月に開催され,国際協力,科学技術の進展レビュー,国内実施,支援・対応・準備,及び条約の制度的強化について議論が進められた。
BWCは生物兵器の開発,生産,貯蔵,保有について戦時・平時を問わず包括的に禁止しているが,その一方で,化学兵器禁止条約(CWC : Chemical Weapons Convention)と異なり,締約国の条約の遵守を検証する手段に関する規定がない。1994年に開催された締約国特別会議において,検証議定書を検討するための政府専門家アドホック・グループ(AHG)が設置されたが,バイオテクノロジーや製薬業界等の関連業界への査察受け入れの負担等の影響が懸念される上,使用される生物剤は殺菌による証拠隠滅も容易である等の理由から,検証そのものが極めて難しいという問題があって,交渉は難航した。結局,2001年4月には同グループ議長案が提示されたが,2001年11月の第5回運用検討会議(運用検討会議は5年に一度開催)以降,検証議定書交渉は中断されている。
生物兵器の使用,開発の例としては,1999年に国連イラク特別委員会(UNSCOM)がイラクにおける大量の不法な生物学的活動を発見している。また,1995年のオウム真理教によるボツリヌス毒素・炭疽菌の開発,2001年の米国における炭疽菌事件,2018年のドイツにおけるリシンを用いたテロ未遂事件等を受けて,国家のみならず非国家主体による危険な生物剤を用いたテロ行為発生の可能性が現実的なものとして国際社会において受け止められるようになっている。近年,インターネットの普及やデジタルデバイスの進化に伴い,一般市民が自宅で遺伝子改変等の最先端のバイオテクノロジーの研究を行うことも可能になってきており,生物兵器開発に対するハードルの急激な低下が懸念されている。現在は,こうしたリスク・脅威に対抗する対策も含めた条約の強化が課題となっている。
また,近年,ウイルスの人工合成やゲノム編集といった先進生命科学技術を活用した生物兵器の凶悪化が懸念されるようになった。このため,その汎用性への対処も視野に入れた研究・開発の促進が求められている。
2020年からの新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は,万一生物兵器が使用された場合にも今回と同様の事態を想定させ,生物学的な脅威に対する国際社会の脆弱性への認識が高まった。新型コロナウイルス感染対応から得られた教訓,知見を踏まえつつ,BWCの枠組みの強化について議論を深めることが課題となっている。
2-2 BWC強化に向けた取組
検証議定書交渉の中断後,次の運用検討会議開催までの間に専門家会合と締約国会合を毎年開催し,BWCの強化に関する共通の理解と実効的な措置を促進するための議論を継続することが第5回運用検討会議(2001年)で決定された。第6回運用検討会議(2006年)では事務局機能を提供する履行支援ユニット(ISU)の設置,第7回運用検討会議(2011年)では毎年自国内にある研究施設,生物防護計画,疫病発生状況等について情報提供を行う信頼醸成措置の申告内容の改善,締約国間の国際協力・支援を促進するためのデータベースの立ち上げ,発展途上国の年次会合への参加を支援するための任意拠出金によるスポンサーシップ・プログラムの立ち上げ等の新たな措置について合意された。また,第8回運用検討会議(2016年)では,検証議定書交渉の再開を争点に米国とロシア,非同盟諸国等との対立が続き,第9回運用検討会議までの会期間活動に関する具体的提案の多くについて合意がなされないまま終了した。
2-3 最近の動き
2017年の締約国会合では,第9回運用検討会議(当初2021年に予定されていたが,以下に述べる通り,新型コロナウイルス感染症の影響で2022年8月に延期開催された)までの会期間活動として,毎年専門家会合及び締約国会合を行うことを決定した。また,2018年~2019年の専門家会合及び締約国会合では,バイオテロ対策,急速に進展するバイオ技術の悪用や誤用を防止するための施策,発生初期段階において生物兵器の使用に起因するのか自然発生なのか区別が困難で影響が広範囲に及ぶ恐れのある事案に対する支援,対応及び準備等について,BWCのフォーラムを活用した具体的な施策について議論が進められた。
2020年に入ると,新型コロナウイルス感染拡大により各会合はおおよそ1年間後ろ倒しとなった。専門家会合は2021年8月~9月に開催され,国際協力,科学技術の進展レビュー,国内実施,支援・対応・準備,及び条約の制度的強化について議論が進められた。
2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻以降,ロシアは,米国及びウクライナによるBWC上の義務違反を主張し,2022年9月には,ロシアの要請によりBWC第5条に基づいて公式協議会合(Formal Consultative Meeting)が開催された。また,2022年10月及び11月には,同じくロシアの要請により,BWC第6条に基づいて安保理会合が開催され,ロシアはその主張に基づく調査委員会を設置するとする決議案を安保理に提出したものの,否決された。
第9回運用検討会議は上記のような状況の下で,ベンチーニ・イタリア軍縮代表部大使を議長として,2022年11月28日~12月16日に開催された。従来の運用検討会議と同様,主として条約の実施のレビューに関する議論と決定・勧告に関する議論とが行われたが,前者については上記の第5条に基づく公式協議会合及び第6条に基づく安保理会合に係る書きぶりについて合意が達成されず,報告書からは条約の実施のレビューに関する記述はすべて削除された。他方,決定と勧告については,条約の効率性の強化及び履行の改善のために作業部会を設置すること,また,特に,作業部会は第10条の下での国際協力及び支援の完全な履行を支援するメカニズム及び科学技術の進展の検討・評価のためのメカニズムを設置するために勧告を行うことが決定された。採択された報告書の主な内容は以下の通り。
●2023年から2026年までの間,締約国はジュネーブにおいて年次会合を開催する。
●あらゆる側面での条約の有効性を強化し,また,その履行を改善することを決意し,すべての締約国に開かれた作業部会を設置する。
●作業部会の目的は,条約の強化及び制度化のための,法的拘束力のあり得る措置を含む,具体的かつ効果的な措置を特定し,また,締約国による検討及び更なる行動のために勧告を提出すること。
●作業部会は、以下の措置に取り組む。
(1) 第10条の下の国際協力及び支援
(2) 条約に関連する科学的及び技術的進展
(3) 信頼醸成及び透明性
(4) 遵守及び検証
(5) 条約の国内実施
(6) 第7条の下の支援等
(7) 組織、制度及び財政
●作業部会は,2023年から2026年までの期間,毎年,15日間実質的な会議を持ち,可能な限り早期に,望ましくは2025年末までにその作業を完了する。
●作業部会は,その作業終了時に,報告書をコンセンサスにより採択し,当該報告書は,2027年までに開催される第10回再検討会又はそれ以前の特別会議において,さらなる行動を決定するために検討が行われる。
●作業部会は,第10条の下の国際協力及び支援を完全に履行することを支援するためのメカニズム,及び条約に関連する科学的及び技術的進展を検討・評価し,適切な助言を締約国に提供するためのメカニズムを設置するために,適切な勧告を行う。
●条約履行支援ユニット(ISU)については,そのマンデートを2027年まで更新するとともに,会期期間中に必要な支援を提供するために,2023年から2027年の間,ISU内に新たに1名の常勤ポジションを設ける。
第9回運用検討会議は上記のような状況の下で,ベンチーニ・イタリア軍縮代表部大使を議長として,2022年11月28日~12月16日に開催された。従来の運用検討会議と同様,主として条約の実施のレビューに関する議論と決定・勧告に関する議論とが行われたが,前者については上記の第5条に基づく公式協議会合及び第6条に基づく安保理会合に係る書きぶりについて合意が達成されず,報告書からは条約の実施のレビューに関する記述はすべて削除された。他方,決定と勧告については,条約の効率性の強化及び履行の改善のために作業部会を設置すること,また,特に,作業部会は第10条の下での国際協力及び支援の完全な履行を支援するメカニズム及び科学技術の進展の検討・評価のためのメカニズムを設置するために勧告を行うことが決定された。採択された報告書の主な内容は以下の通り。
●2023年から2026年までの間,締約国はジュネーブにおいて年次会合を開催する。
●あらゆる側面での条約の有効性を強化し,また,その履行を改善することを決意し,すべての締約国に開かれた作業部会を設置する。
●作業部会の目的は,条約の強化及び制度化のための,法的拘束力のあり得る措置を含む,具体的かつ効果的な措置を特定し,また,締約国による検討及び更なる行動のために勧告を提出すること。
●作業部会は、以下の措置に取り組む。
(1) 第10条の下の国際協力及び支援
(2) 条約に関連する科学的及び技術的進展
(3) 信頼醸成及び透明性
(4) 遵守及び検証
(5) 条約の国内実施
(6) 第7条の下の支援等
(7) 組織、制度及び財政
●作業部会は,2023年から2026年までの期間,毎年,15日間実質的な会議を持ち,可能な限り早期に,望ましくは2025年末までにその作業を完了する。
●作業部会は,その作業終了時に,報告書をコンセンサスにより採択し,当該報告書は,2027年までに開催される第10回再検討会又はそれ以前の特別会議において,さらなる行動を決定するために検討が行われる。
●作業部会は,第10条の下の国際協力及び支援を完全に履行することを支援するためのメカニズム,及び条約に関連する科学的及び技術的進展を検討・評価し,適切な助言を締約国に提供するためのメカニズムを設置するために,適切な勧告を行う。
●条約履行支援ユニット(ISU)については,そのマンデートを2027年まで更新するとともに,会期期間中に必要な支援を提供するために,2023年から2027年の間,ISU内に新たに1名の常勤ポジションを設ける。
3 日本の取組
日本は,BWC運用検討会議等に多くのの作業文書を提出し,議論の活性化に貢献している(第9回運用検討会議では計10本の作業文書を提出)。中でも,検証制度を有さないBWCにおいて条約実施の信頼性を向上させるために重要な役割を果たしている信頼醸成措置について,一定のメカニズムに従って情報共有することのメリットを訴えるなど毎年具体的な提案を行っている。また,運用検討会議を含む関連会議において,我が国の専門家が,日本国内のバイオセキュリティ関係者間のネットワーク,最先端生命科学とデュアルユースの問題,バイオリスクの評価及び管理に関する我が国の取組等について発表することにより,BWC強化に貢献してきている。2021年8月~9月に開催された専門家会合では,専門家会合2(議題:科学技術の進展レビュー)の議長を中井一浩軍縮代表部公使(当時)が務め,科学技術の進展レビューや生物科学者の行動規範,生物学的リスクの評価と管理等について議論を促進した。また,2021年11月に開催された締約国会合では,本議長職を引き継いだ梅津茂軍縮代表部公使参事官が,専門家会合2の議論の成果を報告した。また,2022年の第9回運用検討会議では,小笠原一郎軍縮会議日本政府代表部大使が副議長を務めた。
また,日本は,国連軍縮部への拠出を通じて,2018年からBWC・ISUとともに「生物化学兵器使用に対する国連及び関係機関の連携強化」プロジェクト及び「東南アジア及び太平洋地域の担当者及び専門家に対するワークショップ」プロジェクトを支援している。これらのプロジェクトの下、生物兵器使用事案におけるアジア地域の対応能力強化に向けたワークショップや,生物兵器使用時における国内,地域,国際的連携に関するセミナー等が実施された。また,2022年12月,第9回運用検討会議に際しては,日本・ラオス・フィリピンの共催の下,「東南アジアにおける生物兵器禁止条約の実施強化の取組」と題するサイドイベントを開催し,上記プロジェクトを通じた成果について発信するとともに,この成果をまとめて作業文書(BWC/CONF.IX/WP.18)として同運用検討会議に提出している。
2023年は我が国がG7の議長国を務める年であり,バイオセキュリティを含む軍縮・不拡散分野においてはグローバル・パートナーシップ作業部会の議長国も務める。議長国として,第9回運用検討会議の機運を具体的なアクションへとつなげていくべく議論をリードすることが期待されている。
【最近の日本のステートメント】
・2022年11月28日 生物兵器禁止条約(BWC)第9回運用検討会議における小笠原大使ステートメント
・2022年4月4日 生物兵器禁止条約(BWC)第9回運用検討会議準備委員会における小笠原大使ステートメント
・2021年11月22日 生物兵器禁止条約(BWC)2020年締約国会合における小笠原ステートメント
【第9回運用検討会議に日本が提出した作業文書】
[国際協力に関連する作業文書]
・“Strengthening National, Sub-Regional and International Capacities to Prepare for and Respond to the Deliberate Use of Biological Weapons”: Final Project Report (有事に対する国内、地域的および国際的準備・対応能力の構築に係るプロジェクトレポート)(BWC/CONF.IX/WP.1)
・“Strengthening National, Sub-Regional and International Capacities to Prepare for and Respond to the Deliberate Use of Biological Weapons”: Project update (アップデート:有事に対する国内、地域的および国際的準備・対応能力の構築に係るプロジェクトレポート) (BWC/CONF.IX/WP.41)
・“Strengthening National, Sub-Regional and International Capacities to Prepare for and Respond to the Deliberate Use of Biological Weapons”: Project update (再アップデート:有事に対する国内、地域的および国際的準備・対応能力の構築に係るプロジェクトレポート) (BWC/CONF.IX/WP.43)
・“Strengthening the Capacity of Biological Weapons Convention National Contact Points in Southeast Asia”: Final Project Report (東南アジアのBWCナショナル・コンタクト・ポイントの強化に係るプロジェクトレポート)(BWC/CONF.IX/WP.18)
・Online Training Course for Biological Weapons Convention National Contact Points in Southeast Asia: A Model Approach for Other Regions (東南アジアのBWCナショナル・コンタクト・ポイントのオンライン強化トレーニングに係る作業文書)(BWC/CONF.IX/WP.42)
・International Activities of Global Partnership Member Countries related to Article X of the Biological and Toxin Weapons Convention (2017-2022) (BWC第10条に関連したグローバル・パートナーシップ加盟国の活動リスト) (BWC/CONF.IX/WP.51)
[条約強化に関連する作業文書]
・Investigation framework to strengthen the Biological Weapons Convention (BWC強化のための調査制度に係る作業文書) (BWC/CONF.IX/WP.39)
・Proposals to Enhance Confidence-Building Measures Participation by Step-by Step Approach (信頼醸成措置の提出促進に係る作業文書)(BWC/CONF.IX/WP.62)
・Strengthening Cooperation among States Parties and Relevant International Organizations in Response to Deliberate Spread of Infectious Diseases (有事の際のBWC締約国および関連国際機関の協力態勢強化に関する作業文書)(BWC/CONF.IX/WP.64)
[国内履行に関連する作業文書]
・Approach to Strengthening Measures for Emerging Infectious Diseases based on Lessons Learned from the Ebola Outbreak (エボラ出血熱の蔓延から学ぶ感染症対策の強化に係る作業文書)(BWC/CONF.IX/WP.40)
[科学技術メカニズムに関連する作業文書]
・Concept note and chart produced by the Chairperson of the 2020 Meeting of Experts on Review of Developments in the Field of Science and Technology Related to the Convention (2020年BWC専門家会合非公式協議 MX2議長による科学技術メカニズムに関する各国の立場まとめ) (BWC/CONF.IX/WP.44)
また,日本は,国連軍縮部への拠出を通じて,2018年からBWC・ISUとともに「生物化学兵器使用に対する国連及び関係機関の連携強化」プロジェクト及び「東南アジア及び太平洋地域の担当者及び専門家に対するワークショップ」プロジェクトを支援している。これらのプロジェクトの下、生物兵器使用事案におけるアジア地域の対応能力強化に向けたワークショップや,生物兵器使用時における国内,地域,国際的連携に関するセミナー等が実施された。また,2022年12月,第9回運用検討会議に際しては,日本・ラオス・フィリピンの共催の下,「東南アジアにおける生物兵器禁止条約の実施強化の取組」と題するサイドイベントを開催し,上記プロジェクトを通じた成果について発信するとともに,この成果をまとめて作業文書(BWC/CONF.IX/WP.18)として同運用検討会議に提出している。
2023年は我が国がG7の議長国を務める年であり,バイオセキュリティを含む軍縮・不拡散分野においてはグローバル・パートナーシップ作業部会の議長国も務める。議長国として,第9回運用検討会議の機運を具体的なアクションへとつなげていくべく議論をリードすることが期待されている。
【最近の日本のステートメント】
・2022年11月28日 生物兵器禁止条約(BWC)第9回運用検討会議における小笠原大使ステートメント
・2022年4月4日 生物兵器禁止条約(BWC)第9回運用検討会議準備委員会における小笠原大使ステートメント
・2021年11月22日 生物兵器禁止条約(BWC)2020年締約国会合における小笠原ステートメント
【第9回運用検討会議に日本が提出した作業文書】
[国際協力に関連する作業文書]
・“Strengthening National, Sub-Regional and International Capacities to Prepare for and Respond to the Deliberate Use of Biological Weapons”: Final Project Report (有事に対する国内、地域的および国際的準備・対応能力の構築に係るプロジェクトレポート)(BWC/CONF.IX/WP.1)
・“Strengthening National, Sub-Regional and International Capacities to Prepare for and Respond to the Deliberate Use of Biological Weapons”: Project update (アップデート:有事に対する国内、地域的および国際的準備・対応能力の構築に係るプロジェクトレポート) (BWC/CONF.IX/WP.41)
・“Strengthening National, Sub-Regional and International Capacities to Prepare for and Respond to the Deliberate Use of Biological Weapons”: Project update (再アップデート:有事に対する国内、地域的および国際的準備・対応能力の構築に係るプロジェクトレポート) (BWC/CONF.IX/WP.43)
・“Strengthening the Capacity of Biological Weapons Convention National Contact Points in Southeast Asia”: Final Project Report (東南アジアのBWCナショナル・コンタクト・ポイントの強化に係るプロジェクトレポート)(BWC/CONF.IX/WP.18)
・Online Training Course for Biological Weapons Convention National Contact Points in Southeast Asia: A Model Approach for Other Regions (東南アジアのBWCナショナル・コンタクト・ポイントのオンライン強化トレーニングに係る作業文書)(BWC/CONF.IX/WP.42)
・International Activities of Global Partnership Member Countries related to Article X of the Biological and Toxin Weapons Convention (2017-2022) (BWC第10条に関連したグローバル・パートナーシップ加盟国の活動リスト) (BWC/CONF.IX/WP.51)
[条約強化に関連する作業文書]
・Investigation framework to strengthen the Biological Weapons Convention (BWC強化のための調査制度に係る作業文書) (BWC/CONF.IX/WP.39)
・Proposals to Enhance Confidence-Building Measures Participation by Step-by Step Approach (信頼醸成措置の提出促進に係る作業文書)(BWC/CONF.IX/WP.62)
・Strengthening Cooperation among States Parties and Relevant International Organizations in Response to Deliberate Spread of Infectious Diseases (有事の際のBWC締約国および関連国際機関の協力態勢強化に関する作業文書)(BWC/CONF.IX/WP.64)
[国内履行に関連する作業文書]
・Approach to Strengthening Measures for Emerging Infectious Diseases based on Lessons Learned from the Ebola Outbreak (エボラ出血熱の蔓延から学ぶ感染症対策の強化に係る作業文書)(BWC/CONF.IX/WP.40)
[科学技術メカニズムに関連する作業文書]
・Concept note and chart produced by the Chairperson of the 2020 Meeting of Experts on Review of Developments in the Field of Science and Technology Related to the Convention (2020年BWC専門家会合非公式協議 MX2議長による科学技術メカニズムに関する各国の立場まとめ) (BWC/CONF.IX/WP.44)