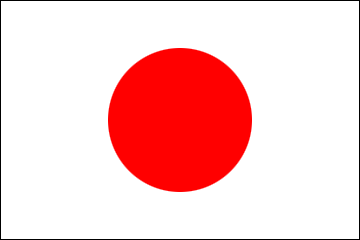代表部案内・大使挨拶
令和8年1月13日
市川大使挨拶
令和8年(2026年)年頭のご挨拶
国際的な核軍縮・不拡散体制の礎石である核兵器不拡散条約(NPT)は、本年、2022年以来の運用検討会議がニューヨークで開催されます。日本が毎年国連総会第一委員会に提出している核兵器廃絶決議も、大幅な改定の年に当たります。厳しい国際安全保障環境と核軍縮を巡る国際社会の分断が続く中、唯一の戦争被爆国として、核兵器使用の惨禍の実相や非人道性への国際社会の理解を一層促進し、また、将来の世代に継承していくことに引き続き積極的に取り組み、「核兵器のない世界」を目指す日本外交に貢献していきたいと思います。さらに、核軍縮の取組を前進させるため、引き続き、核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)の早期交渉開始や核戦力の透明性の向上等、具体的措置の実施を国際社会に呼びかけていきます。2026年は、自律型致死兵器システム(LAWS)に関する政府専門家会議(GGE)や、生物兵器禁止条約(BWC)の実施及び強化に向けた作業部会にとっても、取りまとめが予定される重要な年となります。日本の立場が十分反映されるよう、引き続き積極的に議論に参加して参ります。宇宙空間における軍備競争の防止に関するルール作りや、昨年日本が議長を務めた対人地雷禁止条約(APMBC)、本年9月にラオスにおいて5年に一度の検討会議が開催されるクラスター弾に関する条約(CCM)を含む通常兵器に関する条約や枠組みにおいても、日本として積極的に貢献して参ります。
軍縮会議日本政府代表部大使 市川 とみ子
特命全権大使・軍縮会議日本政府常駐代表
| 市川 とみ子 (いちかわ とみこ) 特命全権大使 軍縮会議日本政府常駐代表 %20%EF%BC%A8%EF%BC%B0%E7%94%A8.jpg)
 |
||
| 1985年 | 外務省入省 | |
| 1994-1995年 | UNPROFOR(旧ユーゴスラビア国連PKO) 政務官 | |
| 2001-2002年 | 在英国日本国大使館 一等書記官 | |
| 2002-2003年 | 在英国日本国大使館 参事官 | |
| 2003-2004年 | 欧州局西欧課長 | |
| 2005-2006年 | 経済局経済統合体課長 | |
| 2006-2009年 | 総合外交政策局軍縮不拡散・科学部不拡散・科学原子力課長 | |
| 2009-2011年 | 経済局政策課長 | |
| 2011-2014年 | 在ウィーン国際機関日本政府代表部 公使 | |
| 2014-2020年 | 国際原子力機関事務局事務局長特別補佐官 | |
| 2020-2023年 | (公財)日本国際問題研究所 所長 | |
| 2023年- | 軍縮会議日本政府代表部 特命全権大使 | |
連絡先
代表部住所 (郵便小包は代表部住所宛先へ、手紙及び書簡は私書箱宛先へ)
Délégation du Japon à la Conférence du Désarmement
Chemin des Fins 3, 1218 Le Grand-Saconnex, Genève, Suisse
私書箱: Délégation du Japon à la Conférence du Désarmement, Case postale 44, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse
電話: +41 (0) 22 717 3444
FAX:+41 (0) 22 788 3818
メール: delegation1@gv.mofa.go.jp
開館時間:9:00-17:30
代表部休館日
| 令和8年 1月 1日(木) 元旦(任国の休日) |
| 1月 2日(金) 年始休暇 |
| 1月12日(月) 成人の日 |
| 2月11日(水) 建国記念日 |
| 3月20日(金) ラマダン明けの祭り(国連の休日) |
| 4月 3日(金) 聖金曜日(任国の休日) |
| 4月 6日(月) 復活祭の月曜日(任国の休日) |
| 5月14日(木) 昇天祭(任国の休日) |
| 5月26日(火) 犠牲際(国連の休日) |
| 7月20日(月) 海の日 |
| 7月31日(金) スイス建国記念日振替休日(国連の休日) |
| 8月11日(火) 山の日 |
| 9月10日(木) ジュネーブ断食祭(任国の休日) |
| 9月21日(月) 敬老の日 |
| 11月 3日(火) 文化の日 |
| 11月23日(月) 勤労感謝の日振替休日 |
| 12月25日(金) クリスマス(任国の休日) |
| 12月29日(火) 年末休暇 |
| 12月30日(水) 年末休暇 |
| 12月31日(木) ジュネーブ共和国復興記念日(任国の休日) |