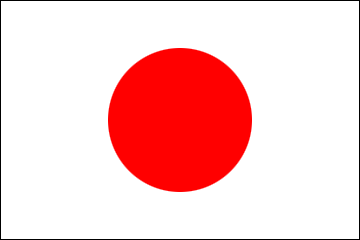軍縮・不拡散教育
令和7年9月3日
【概要】
軍縮・不拡散教育は、国連決議によれば、核兵器を含む様々な兵器による破壊的な作用がもたらす帰結、並びにそれら兵器の拡散の危険性及び対処の必要性について個人・社会の意識を向上させ、そのような知識及び実践を基礎として、国際安全保障や軍縮・不拡散問題への国、社会、個人の各レベルにおける具体的な取組の在り方について、自ら考え行動する能力(クリティカル・シンキング)を高めることを目的としている。このような教育は、世界的な軍縮・不拡散の着実な進展に向けた政府や市民社会の取組を支える基礎となる。
(参考)軍縮・不拡散教育の概要(外務省HP)
【活動の状況】
日本政府は、唯一の戦争被爆国として、核兵器使用の惨禍の実相や非人道性を国際社会及び将来の世代に継承していくことが人類に対する日本の責務であるとの認識の下、軍縮・不拡散教育を重視している。具体的には、被爆の実相を国境と世代を越えて伝え、軍縮・不拡散教育の重要性を強調するための様々な取組として、「非核特使」や「ユース非核特使」の派遣、「ユース非核リーダー基金」の立ち上げ、被爆証言の多言語化、国連軍縮フェローシップ・プログラムの枠組みでの各国若手外交官の被爆地研修等を通じた被爆の実相の伝達、核兵器不拡散条約(NPT)運用検討プロセスにおける軍縮・不拡散教育に関する作業文書の提出や共同ステートメントの実施、国連欧州本部における常設原爆展の開催支援などを行ってきている。
軍縮代表部は、NPT運用検討プロセスにおける各種活動に加え、ユース非核特使としてジュネーブを訪問する高校生平和大使その他日本のユースの受け入れ(意見交換や軍縮会議傍聴のアレンジ等)、国連軍縮フェローシップへの協力(訪日プログラムの調整、レセプション開催、フェローシップ経験者とのネットワーク構築等)、国連欧州本部における常設原爆展への支援等を通じて、軍縮・不拡散教育に積極的に取り組んで来ている。
【活動・ステートメント】
2025年
2025年9月3日 高校生平和大使(ユース非核特使)を招いたレセプションの開催
2025年9月2日 高校生平和大使(ユース非核特使)一行による軍縮会議傍聴
2025年9月1日 市川大使と高校生平和大使一行との意見交換
2024年
2024年12月10日 日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)のノーベル平和賞受賞について(外務大臣談話)
2024年8月21日 高校生平和大使(ユース非核特使)を招いたレセプションの開催
2024年8月20日 高校生平和大使(ユース非核特使)一行による軍縮会議傍聴
2024年8月19日 市川大使と高校生平和大使一行との意見交換
2024年7月25日 市川大使と広島市、長崎市及びユース代表との意見交換
2024年7月23日 NPT第2回準備委員会中の「ペーパーランタン」上映会サイドイベント
2024年7月22日 NPT第2回準備委員会中のユース交流レセプション の開催
2024年6月6日 2024年国連軍縮フェローシップ関係者を招いたレセプションの開催
2023年
2023年8月21日 高校生平和大使のジュネーブ訪問(国連軍縮フェローシップ参加者との意見交換の実施)
2023年8月21日 小笠原大使と高校生平和大使一行との意見交換 2023年6月1日 軍縮会議(CD)本会議における「教育と研究」に関する小笠原大使によるステートメント
2022年
2022年8月5日の核兵器不拡散条約(NPT)主要委員会Iにおける軍縮不拡散教育に関する小笠原大使ステートメント
2021年
2021年8月12日の軍縮会議(CD)公式本会議における「若者と軍縮」に関する小笠原大使ステートメント(英文)
軍縮・不拡散教育は、国連決議によれば、核兵器を含む様々な兵器による破壊的な作用がもたらす帰結、並びにそれら兵器の拡散の危険性及び対処の必要性について個人・社会の意識を向上させ、そのような知識及び実践を基礎として、国際安全保障や軍縮・不拡散問題への国、社会、個人の各レベルにおける具体的な取組の在り方について、自ら考え行動する能力(クリティカル・シンキング)を高めることを目的としている。このような教育は、世界的な軍縮・不拡散の着実な進展に向けた政府や市民社会の取組を支える基礎となる。
(参考)軍縮・不拡散教育の概要(外務省HP)
【活動の状況】
日本政府は、唯一の戦争被爆国として、核兵器使用の惨禍の実相や非人道性を国際社会及び将来の世代に継承していくことが人類に対する日本の責務であるとの認識の下、軍縮・不拡散教育を重視している。具体的には、被爆の実相を国境と世代を越えて伝え、軍縮・不拡散教育の重要性を強調するための様々な取組として、「非核特使」や「ユース非核特使」の派遣、「ユース非核リーダー基金」の立ち上げ、被爆証言の多言語化、国連軍縮フェローシップ・プログラムの枠組みでの各国若手外交官の被爆地研修等を通じた被爆の実相の伝達、核兵器不拡散条約(NPT)運用検討プロセスにおける軍縮・不拡散教育に関する作業文書の提出や共同ステートメントの実施、国連欧州本部における常設原爆展の開催支援などを行ってきている。
軍縮代表部は、NPT運用検討プロセスにおける各種活動に加え、ユース非核特使としてジュネーブを訪問する高校生平和大使その他日本のユースの受け入れ(意見交換や軍縮会議傍聴のアレンジ等)、国連軍縮フェローシップへの協力(訪日プログラムの調整、レセプション開催、フェローシップ経験者とのネットワーク構築等)、国連欧州本部における常設原爆展への支援等を通じて、軍縮・不拡散教育に積極的に取り組んで来ている。
【活動・ステートメント】
2025年
2025年9月3日 高校生平和大使(ユース非核特使)を招いたレセプションの開催
2025年9月2日 高校生平和大使(ユース非核特使)一行による軍縮会議傍聴
2025年9月1日 市川大使と高校生平和大使一行との意見交換
2024年
2024年12月10日 日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)のノーベル平和賞受賞について(外務大臣談話)
2024年8月21日 高校生平和大使(ユース非核特使)を招いたレセプションの開催
2024年8月20日 高校生平和大使(ユース非核特使)一行による軍縮会議傍聴
2024年8月19日 市川大使と高校生平和大使一行との意見交換
2024年7月25日 市川大使と広島市、長崎市及びユース代表との意見交換
2024年7月23日 NPT第2回準備委員会中の「ペーパーランタン」上映会サイドイベント
2024年7月22日 NPT第2回準備委員会中のユース交流レセプション の開催
2024年6月6日 2024年国連軍縮フェローシップ関係者を招いたレセプションの開催
2024年6月 6日 軍縮会議(CD)本会議における「教育・研究を通じた軍縮に係る能力構築」に関する市川大使によるステートメント
2023年
2023年8月21日 高校生平和大使のジュネーブ訪問(国連軍縮フェローシップ参加者との意見交換の実施)
2023年8月21日 小笠原大使と高校生平和大使一行との意見交換 2023年6月1日 軍縮会議(CD)本会議における「教育と研究」に関する小笠原大使によるステートメント
2022年
2022年8月5日の核兵器不拡散条約(NPT)主要委員会Iにおける軍縮不拡散教育に関する小笠原大使ステートメント
2021年
2021年8月12日の軍縮会議(CD)公式本会議における「若者と軍縮」に関する小笠原大使ステートメント(英文)