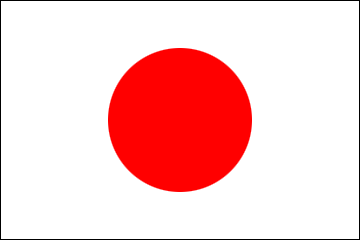軍縮機関(国連総会第一委員会、軍縮会議)
令和6年3月1日
国連における軍縮・不拡散
国連憲章第11条第1項は、国連総会の任務及び権限として、「軍備縮小及び軍備規制を律する原則」を明記した上で、これを含む国際の平和及び安全の維持についての協力に関する一般原則を審議することを掲げている。これを受け、同総会の下に軍縮・国際安全保障に関する議題を議論する第一委員会及び補助機関として特定の軍縮問題に焦点を当てて議論する国連軍縮委員会が置かれている。また、国際の平和と安全に第一義的な責任を負う機関である国連安全保障理事会においても、軍縮・不拡散問題が取り上げられてきている。さらに、国連事務総長の諮問機関であって、軍縮問題一般につき事務総長に直接助言を行う国連軍縮諮問委員会や、国連内にあって自律的な立場で軍縮分野の研究を行う国連軍縮研究所(UNIDIR)がある(なお、2017年以来、国連事務次長兼軍縮担当上級代表を中満泉氏が務めている)。
国連総会第一委員会
従来、国連総会の第一委員会においては、軍縮問題が、政治、安全保障、技術の問題等と一緒に議論されていたが、1978年の第1回国連軍縮特別総会は、「総会の第一委員会は、軍縮問題及び関連する国際安全保障問題のみを取り扱う」旨の決定を行い、以降第一委員会では主として軍縮・国際安全保障問題が議論されてきている。この委員会は、毎年秋の国連総会一般討論後、約5週間の会期で開催される。
第一委員会では毎年数多くの軍縮関連の決議が採択され、国際的な気運を高め、方向性を示す役割を果たしている。また、その動向は軍縮・不拡散の流れを見極める上で極めて重要である。2023年には60本の決議及び1本の決定が採択されている。日本も毎年、この分野における重要事項の決議案を提出している。特に、日本は、1994年以降毎年、核軍縮に関して日本が掲げる現実的かつ実践的アプローチに基づいた核兵器廃絶のための決議案を国連総会に対して提出してきており、いずれの決議案もこれまで圧倒的支持を得て採択されてきている。直近の2023年の決議は、148か国の賛成を得て国連総会で採択された。
また、日本は、小型武器問題が国際社会で本格的に提起された1995年からほぼ毎年、小型武器に関する決議案を南アフリカ及びコロンビアと共同で提出しており、2023年はコンセンサスで採択された。
第一委員会では毎年数多くの軍縮関連の決議が採択され、国際的な気運を高め、方向性を示す役割を果たしている。また、その動向は軍縮・不拡散の流れを見極める上で極めて重要である。2023年には60本の決議及び1本の決定が採択されている。日本も毎年、この分野における重要事項の決議案を提出している。特に、日本は、1994年以降毎年、核軍縮に関して日本が掲げる現実的かつ実践的アプローチに基づいた核兵器廃絶のための決議案を国連総会に対して提出してきており、いずれの決議案もこれまで圧倒的支持を得て採択されてきている。直近の2023年の決議は、148か国の賛成を得て国連総会で採択された。
また、日本は、小型武器問題が国際社会で本格的に提起された1995年からほぼ毎年、小型武器に関する決議案を南アフリカ及びコロンビアと共同で提出しており、2023年はコンセンサスで採択された。
軍縮会議(CD)
1 概要
軍縮会議(CD : Conference on Disarmament)は、唯一の多数国間軍縮交渉機関であり、ジュネーブに所在する。国連を中心とした第二次世界大戦後の軍縮努力がなかなか進展しない中、米国、英国、フランス、ソ連の4か国の合意により設置された「10か国軍縮委員会(1960‐61年)」を起源とし、「18か国軍縮委員会(1962‐68年)」、「軍縮委員会会議(1969‐78年)」を経て第1回国連軍縮特別総会(1978年)の決定により「軍縮委員会」が設置され、1984年に「軍縮会議」と名称を変更し現在に至っている。日本は、1969年に加盟した。
現在の加盟国は65か国であり、(1)西欧及びその他諸国グループ(日本を含む25か国)、(2)東欧グループ(6か国)、(3)非同盟運動(NAM)諸国を中心とするG21グループ(33か国)及び(4)中国により構成される。これは東西ブロックが対峙していた冷戦期の対立構造を受け継いでいる。なお、1年の会期は24週間とされ、4週間ごとに議長国(一年で6か国)がアルファベット順に入れ替わる。
CDはこれまで、前身の機関も含めて、核兵器不拡散条約(NPT、1968年)、生物兵器禁止条約(BWC、1972年)、化学兵器禁止条約(CWC、1993年)、包括的核実験禁止条約(CTBT、1996年)等、重要な軍縮関連条約を作成したものの、CTBT以降、実質的交渉を行うことができていない。
(注)CTBTは1994 年からCDの核実験禁止特別委員会において交渉された。交渉は2年半にわたって行われたが、最終局面でインドの反対によってコンセンサスで条約案を採択することはできなかった。しかし、CTBT 成立に対する国際社会の圧倒的支持と期待を背景とし、オーストラリアが中心となって、CDで作成された同条約案を国連総会に提出し、1996 年9月、国連総会は圧倒的多数にて同条約を採択した。
2 活動の状況
(1)概観
CDの意思決定はコンセンサスで行われることとなっているため、CDで合意された条約は実効的なものとなることが期待される一方で、CDにおける合意の達成はより困難なものとなる。CDでは、核軍縮、核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)、宇宙空間における軍備競争の防止(PAROS)、消極的安全保証(NSAs)を始めとする事項が取り扱われてきているが、地域グループや国により各事項の優先度が異なることやコンセンサス原則があることから、僅かな例外を除いて、実質的交渉を行うために必要な年間の「作業計画(Programme of Work)」を採択できない状況が続いている。
2009年に採択された作業計画は、FMCTについては交渉を、PARO及びNSAsについては実質的議論を、核軍縮については意見及び情報交換を行うことを決定した。しかし、採択直後から、パキスタンが作業計画を実施するための日程や議長を定める「作業計画の実施決定」案の採択に反対したことから、一旦合意済みの作業計画は実施されなかった。
(2)近年の動向
このように作業計画を採択できず条約交渉を開始できない状況が続く中であっても、上記の4主要事項を含め少なくとも実質的議論は行うべきとの意見を踏まえ、補助機関を設置してCDの議題に関する議論を進める等の取組がなされてきている。
2018年には、作業計画の採択には至らなかったものの、採択された決定に基づき、CDの議題に沿って5つの補助機関が設置された。補助機関では専門家による発表を含め、各国により共通理解を探るための議論が行われ、その内容は補助機関ごとの報告書にまとめられた(CD/2138、CD/2139、CD/2140及びCD/2141)が、消極的安全保証について議論した補助機関4は、報告書に合意できなかった。
2019~21年は、作業計画の採択に至らず、補助機関も設置されることなく、CDの議題に沿って各議長の下で分野別討論が行われた。
2022年は、作業計画の採択には至らなかったものの、採択された「作業に関する決定(Decision on the Work)」に基づき、CDの議題に沿って5つの補助機関((1)核軍拡競争の防止と核軍縮、(2)核戦争の防止、(3)宇宙空間における軍備競争の防止、(4)消極的安全保証、(5)放射性兵器等新型大量破壊兵器、包括的軍縮計画、軍備の透明性)が設置され、それぞれに調整役が指名され、各国により議論が行われた。しかし議論の結果、各補助機関の報告書の採択に至ったのは補助機関(3)及び補助機関(5)のみであった。
2023年は、作業計画の採択に至らず、補助機関も設置されることなく、CDの議題に沿って各議長の下で分野別討論が行われた。取り上げられたテーマは、核軍備競争停止及び核軍縮、核ドクトリン・戦力に関する透明性、宇宙空間における軍備競争の防止、教育と研究等であり、フランス及びドイツは、両国が連続して議長を務めた間にCDの再活性化を重視した。
【参考】軍縮会議における日本のステートメント
軍縮会議(CD : Conference on Disarmament)は、唯一の多数国間軍縮交渉機関であり、ジュネーブに所在する。国連を中心とした第二次世界大戦後の軍縮努力がなかなか進展しない中、米国、英国、フランス、ソ連の4か国の合意により設置された「10か国軍縮委員会(1960‐61年)」を起源とし、「18か国軍縮委員会(1962‐68年)」、「軍縮委員会会議(1969‐78年)」を経て第1回国連軍縮特別総会(1978年)の決定により「軍縮委員会」が設置され、1984年に「軍縮会議」と名称を変更し現在に至っている。日本は、1969年に加盟した。
現在の加盟国は65か国であり、(1)西欧及びその他諸国グループ(日本を含む25か国)、(2)東欧グループ(6か国)、(3)非同盟運動(NAM)諸国を中心とするG21グループ(33か国)及び(4)中国により構成される。これは東西ブロックが対峙していた冷戦期の対立構造を受け継いでいる。なお、1年の会期は24週間とされ、4週間ごとに議長国(一年で6か国)がアルファベット順に入れ替わる。
CDはこれまで、前身の機関も含めて、核兵器不拡散条約(NPT、1968年)、生物兵器禁止条約(BWC、1972年)、化学兵器禁止条約(CWC、1993年)、包括的核実験禁止条約(CTBT、1996年)等、重要な軍縮関連条約を作成したものの、CTBT以降、実質的交渉を行うことができていない。
(注)CTBTは1994 年からCDの核実験禁止特別委員会において交渉された。交渉は2年半にわたって行われたが、最終局面でインドの反対によってコンセンサスで条約案を採択することはできなかった。しかし、CTBT 成立に対する国際社会の圧倒的支持と期待を背景とし、オーストラリアが中心となって、CDで作成された同条約案を国連総会に提出し、1996 年9月、国連総会は圧倒的多数にて同条約を採択した。
2 活動の状況
(1)概観
CDの意思決定はコンセンサスで行われることとなっているため、CDで合意された条約は実効的なものとなることが期待される一方で、CDにおける合意の達成はより困難なものとなる。CDでは、核軍縮、核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)、宇宙空間における軍備競争の防止(PAROS)、消極的安全保証(NSAs)を始めとする事項が取り扱われてきているが、地域グループや国により各事項の優先度が異なることやコンセンサス原則があることから、僅かな例外を除いて、実質的交渉を行うために必要な年間の「作業計画(Programme of Work)」を採択できない状況が続いている。
2009年に採択された作業計画は、FMCTについては交渉を、PARO及びNSAsについては実質的議論を、核軍縮については意見及び情報交換を行うことを決定した。しかし、採択直後から、パキスタンが作業計画を実施するための日程や議長を定める「作業計画の実施決定」案の採択に反対したことから、一旦合意済みの作業計画は実施されなかった。
(2)近年の動向
このように作業計画を採択できず条約交渉を開始できない状況が続く中であっても、上記の4主要事項を含め少なくとも実質的議論は行うべきとの意見を踏まえ、補助機関を設置してCDの議題に関する議論を進める等の取組がなされてきている。
2018年には、作業計画の採択には至らなかったものの、採択された決定に基づき、CDの議題に沿って5つの補助機関が設置された。補助機関では専門家による発表を含め、各国により共通理解を探るための議論が行われ、その内容は補助機関ごとの報告書にまとめられた(CD/2138、CD/2139、CD/2140及びCD/2141)が、消極的安全保証について議論した補助機関4は、報告書に合意できなかった。
2019~21年は、作業計画の採択に至らず、補助機関も設置されることなく、CDの議題に沿って各議長の下で分野別討論が行われた。
2022年は、作業計画の採択には至らなかったものの、採択された「作業に関する決定(Decision on the Work)」に基づき、CDの議題に沿って5つの補助機関((1)核軍拡競争の防止と核軍縮、(2)核戦争の防止、(3)宇宙空間における軍備競争の防止、(4)消極的安全保証、(5)放射性兵器等新型大量破壊兵器、包括的軍縮計画、軍備の透明性)が設置され、それぞれに調整役が指名され、各国により議論が行われた。しかし議論の結果、各補助機関の報告書の採択に至ったのは補助機関(3)及び補助機関(5)のみであった。
2023年は、作業計画の採択に至らず、補助機関も設置されることなく、CDの議題に沿って各議長の下で分野別討論が行われた。取り上げられたテーマは、核軍備競争停止及び核軍縮、核ドクトリン・戦力に関する透明性、宇宙空間における軍備競争の防止、教育と研究等であり、フランス及びドイツは、両国が連続して議長を務めた間にCDの再活性化を重視した。
【参考】軍縮会議における日本のステートメント