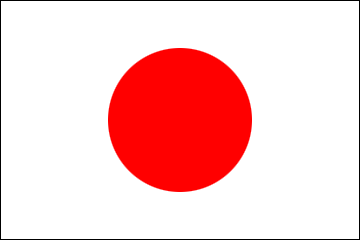特定通常兵器使用禁止制限条約 (自律型致死兵器システム政府専門家会合)
令和4年6月14日
1.特定通常兵器使用禁止条約の概要
特定通常兵器使用禁止制限条約(正式名称「過度に障害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止または制限に関する条約」(Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects) 、通称「Convention on Certain Conventional Weapons」又はCCW)は、手続事項や適用範囲を定めた枠組み条約及び個別の通常兵器等について規制する附属議定書から成る。現在、以下の5つの附属議定書が成立している。
日本は枠組み条約及び改正議定書IIを含む議定書I~IVを締結している。
○ 議定書I:検出不可能な破片を利用する兵器に関する議定書(1983年発効)
○ 改正議定書II:地雷、ブービートラップ(注:食物、玩具等外見上無害な物の中に爆発物等をしかけたものを言う)及び他の類似の装置の使用の禁止又は制限に関する議定書(1998年発効)(改正議定書IIについては、「対人地雷」の項で紹介)
○ 議定書III:焼夷兵器の使用の禁止又は制限に関する議定書(1983年発効)
○ 議定書IV:失明をもたらすレーザー兵器に関する議定書(1998年発効)
○ 議定書V:爆発性戦争残存物に関する議定書(2006年発効)
日本は枠組み条約及び改正議定書IIを含む議定書I~IVを締結している。
○ 議定書I:検出不可能な破片を利用する兵器に関する議定書(1983年発効)
○ 改正議定書II:地雷、ブービートラップ(注:食物、玩具等外見上無害な物の中に爆発物等をしかけたものを言う)及び他の類似の装置の使用の禁止又は制限に関する議定書(1998年発効)(改正議定書IIについては、「対人地雷」の項で紹介)
○ 議定書III:焼夷兵器の使用の禁止又は制限に関する議定書(1983年発効)
○ 議定書IV:失明をもたらすレーザー兵器に関する議定書(1998年発効)
○ 議定書V:爆発性戦争残存物に関する議定書(2006年発効)
2.自律型致死兵器システムに関する議論
(1)CCWにおける自律型致死兵器システムに関する議論の開始(2013年~2015年)
2013年、国際NGOが「殺人ロボット阻止キャンペーン」を開始し、また、国連人権理事会のヘインズ特別報告が「自律型致死性ロボット」に対する国際社会の対処の必要性を指摘したのを背景に、2013年11月のCCW締約国会合にて、2014年から自律型致死兵器システム(LAWS:Lethal Autonomous Weapons Systems)に関する非公式専門家会合を開催することが決定された。非公式専門家会合は2016年まで3年間にわたって開催され、ロボット技術の自律性、軍事有用性、国際人道法の適用等について議論された。
(2)LAWSに関する政府専門家会合の設置
2016年の第5回検討会議において、非公式専門家会合に代えて政府専門家会合を設置することが決定された。同会合は、コロナ感染症拡大で実施できなかった2020年を除き、2017年以降、毎年実施されており、規制すべきLAWSの定義・特徴、人間の関与の在り方、国際人道法との関係、関連技術の軍事的応用の在り方、今後の議論の進め方又は規制の方向性等について議論されている。
そして、2019年の会合では、LAWSに関して各国が考慮すべき指針(Guiding Principles)が承認された。この指針は、後述の通り、第6回運用検討会議で締約国によって承認された後、CCWにおけるLAWSに関する議論において極めて重要な位置づけを付与されている。その概要は以下のとおり。
(a) 国際人道法(IHL) は、 LAWS の潜在的な開発及び使用 を含む、 全ての兵器システムに完全に適用される。
(b) 兵器システムの使用の決定に当たっては、 説明責任が機械に転嫁できないため、人間の責任が確保されなければならない。人間の責任の確保は、兵器システムのライフ・サイクル全体で考慮されるべき。
(c) 人間と機械の相互関係は、様々な形態を取り得るもので、かつ、兵器のライフ・サイクルの様々な段階で起こり得るものである。人間と機械の相互関係は、LAWS関連の新興技術に基づく兵器システムの潜在的な使用が、適用可能な国際法、特に国際人道法に従うことを確保すべき。人間と機械の相互関係の特性と程度の決定に際しては、運用の状況、兵器システム全体としての特徴や性能を含む様々な要因が考慮されるべき。
(d) CCWの枠組みにおける新たな兵器システムの開発、配備及び使用における説明責任は、責任ある人間の指揮統制系統の範囲内における兵器システムの運用を通じたものを含め、適用可能な 国際法に従って確保されなければならない。
(e) 国際法の下での国家の義務に従い、新たな兵器、戦闘の手段又は方法の研究・開発・取得・採用に当たっては、その使用/利用が一部又は全ての状況において、国際法で禁じられているか否かを決めなければならない。
(f) LAWS関連の新興技術に基づく新たな兵器システムの開発・取得に当たっては、 物理的な防護、適切な非物理的な予防措置(ハッキングやフィッシング対策のサイバーセキュリティを含む)、テロリスト・グループによる取得のリスク、拡散のリスクが考慮されるべき。
(g) リスク評価と緩和措置は、兵器システムにおける新興技術の設計・開発・試験・配備サイクル一部とすべき。
(h) LAWS関連の新興技術を使用する際、IHL 及びその他の適用可能な国際的な法的義務の遵守が考慮されるべき。
(i) あり得べき政策的措置の形成に際しては、LAWS関連の新興技術を擬人化すべきではない。
(j) CCW場裏での議論及びあり得べき政策的措置が、高度な自律化技術の進展やその平和的利用 へのアクセスを妨げるべきではない。
(k) CCWは、軍事的必要性と人道的考慮のバランスを追求するという条約の趣旨及び目的の文脈において、LAWS関連の新興技術の問題 を扱う適切な枠組みを提供する。
(3)2021年第6回CCW運用検討会議以降
2021年12月に開催されたCCW第6回運用検討会議で、LAWSに関し以下の宣言を盛り込んだ最終文書が締約国によって採択された。
・政府専門家グループの結論と勧告の価値及びLAWS政府専門家会合が勧告し、2019年締約国会合で認められた指針(Guiding Principles)を承認すること。
・国際人道法が、潜在的なLAWSの開発及び使用を含むすべての兵器システムに引き続き完全に適用されることを確認すること。
・LAWSの分野における新興技術に基づく兵器システムは、それが過度な傷害又は不必要な苦痛を与える性質を有する場合、又は本質的に無差別である場合、又はその他の国際人道法に従った使用が不可能である場合には、使用してはならないことを認識すること。
・武力の行使に関する決定について、人間は、常に、適用される国際法に従って説明責任を負わなければならないとの信念を有すること。
・CCWが、軍事的必要性と人道的考慮の間のバランスを追求する条約の目的及び趣旨に照らして、LAWSの分野における新興技術の問題を取り扱うための適切な枠組みを提供していると認識すること。
・特に、倫理的観点に留意しつつ、法的、軍事的及び技術的側面を考慮し、LAWSの分野における新興技術に対処する努力を継続し、強化するとの決意を新たにしたこと。
・国際法、特に国際連合憲章及び国際人道法並びに関連する倫理的観点が、政府専門家グループの継続的作業を導くべきであることを確認すること。
CCW第6回運用検討会議は、LAWS政府専門家会合をジュネーブで継続することを決定し、2022年2月11日ダミーコ(Mr. Flàvio Soares Damico)ブラジル軍縮代大使が同会合の議長に就任した。同会合は、2022年3月及び7月の計10日間開催され、各国から様々な提案書が提出され、我が国は3月、米国、英国、カナダ、オーストラリア及び韓国とともに国際人道法のLAWSへの適用等について具体的な議論を進めるべく、実用的な運用に耐え得るガイドラインやグッドプラクティス集の作成を提案し、「LAWS分野における新興技術に係る原則とグッドプラクティス」を提出し、サブスタンス面へ貢献した。一方、3月の会合は同年2月24日、ロシアによるウクライナ侵略の影響により公式協議が開催できない状態が長く続き、非公式協議の時間が多くを占める等、十分な議論の時間が確保できなかった。7月の会合において、LAWSの規制推進派と慎重派の懸隔は埋まらず、同会合で採択された報告書は過去に作成された文書の文言の確認等、最小限の内容にとどまった。
2023年は、引き続き、ダミーコブラジル軍縮代大使議長の下、同年3月6日から10日及び5月15日から19日の計10日間の政府専門家会合が開催されることなった。昨年3月、我が国は、米国、英国、カナダ、オーストラリア及び韓国とともに「LAWS分野における新興技術に係る原則とグッドプラクティス」を提出したが、グッドプラクティス集に反対する国の立場を考慮し、2023年3月のセッションに合わせ、我が国は再び米国、英国、カナダ、オーストラリア及び韓国とともに国際人道法のルールを詳らかにし、国際人道法履行に際しての、そのルールを具体的にどのように適用しようとしているのかを規定した「国際人道法を基礎とした禁止と制限の方法にかかる自律型兵器システムに関する条項案」を提出した(ポーランドが5月15日共同提案国入り)。
第2回会合では実質的な議論の深化を文章に落とし込むための議論がなされ、手続き面のみならず、実質的内容を含む同報告書(CCW/GGE.1/2023/2)には、LAWSに関する新興技術を用いた兵器システムに関して、国際人道法を遵守できないものは使用禁止であり、また、兵器システムのライフ・サイクル全体を通じて、国際人道法を含む国際法の遵守を確保するため、必要に応じて標的の種類の制限等を行うべきこと等が明記され、全会一致で採択された。他方、翌2024年のGGEのマンデートについては、時間切れのため審議できず、2023年11月のCCW締約国会議で決定されることとなった。
現状、LAWSについては、定義や特徴、人間の関与の在り方等の重要論点について、各国の立場に引き続き隔たりがある。我が国は、完全自律型の致死性を有する兵器の開発を行う意図はないが、一方で有意な人間の関与が確保された自律性を有する兵器システムは、ヒューマンエラーの減少、省力化・省人化といった安全保障上の意義を有するとの立場からLAWSの議論に積極的に参加している。また、このような観点から、上述の通り、我が国は、米国、英国、カナダ、オーストラリア及び韓国と共に2022年の政府専門家会合には、「LAWS分野における新興技術に係る原則とグッドプラクティス」を、また、2023年の政府専門家会合には、「国際人道法を基礎とした禁止と制限の方法にかかる自律型兵器システムに関する条項案」、それぞれの会合のあり得べき成果物として共同提案し議論に貢献した。
(4)日本の立場と対応
日本は、LAWSの有する安全保障上の重要性に鑑み、LAWS関連技術を有する主要国の一つとして、CCWの下に設置されたGGEを重視し、人道と安全保障の利点を考慮したバランスのとれた議論が行われ、国際社会が目指すべき取組の方向性が示されるよう、積極的にGGEに参加してきた。2023年の政府専門家会合においても、(3)で述べた通り、米国、英国、ポーランド、カナダ、オーストラリア及び韓国と作業文書を共同提案してる。
我が国は、2019年のGGEに、我が国の立場を対外的に示す作業文書を提出した。この作業文書のポイントは以下のとおり。
ア 目的:国際社会が将来目指すべき取組の方向性を示すことに貢献。
イ 議論の整理:過去の議論を踏まえ、関係者間で認識共有すべき事項を指摘。
ウ 日本の考え方:日本は、完全自律型の致死性を有する兵器を開発しないという立場。有意な人間の関与が確保された自律型兵器システムについては、ヒューマンエラーの減少や、省力化・省人化といった安全保障上の意義がある。
エ あり得べき成果:主要国を含む、国際社会で広く共通認識を確保した上でルールについて合意するのが望ましいが、意見の相違があるため、法的拘束力のある文書を直ちに実効的なルール枠組みとすることは困難。現状においては、GGEにおける議論を踏まえた成果文書が適切なオプションの一つであり、今後、他の関係者と協力する。(2023年5月26日更新)
【参考】日本のステートメントと提案等
2023年3月6日 米英加豪韓とともに(ポーランドが5月15日共同提案国入り)「国際人道法を基礎とした禁止と制限の方法にかかる自律型兵器システムに関する条項案」(作業文書)
2019年3月21日 自律型致死兵器システム(LAWS)に関する政府専門家会合に対する日本政府の作業文書(英文)
2013年、国際NGOが「殺人ロボット阻止キャンペーン」を開始し、また、国連人権理事会のヘインズ特別報告が「自律型致死性ロボット」に対する国際社会の対処の必要性を指摘したのを背景に、2013年11月のCCW締約国会合にて、2014年から自律型致死兵器システム(LAWS:Lethal Autonomous Weapons Systems)に関する非公式専門家会合を開催することが決定された。非公式専門家会合は2016年まで3年間にわたって開催され、ロボット技術の自律性、軍事有用性、国際人道法の適用等について議論された。
(2)LAWSに関する政府専門家会合の設置
2016年の第5回検討会議において、非公式専門家会合に代えて政府専門家会合を設置することが決定された。同会合は、コロナ感染症拡大で実施できなかった2020年を除き、2017年以降、毎年実施されており、規制すべきLAWSの定義・特徴、人間の関与の在り方、国際人道法との関係、関連技術の軍事的応用の在り方、今後の議論の進め方又は規制の方向性等について議論されている。
そして、2019年の会合では、LAWSに関して各国が考慮すべき指針(Guiding Principles)が承認された。この指針は、後述の通り、第6回運用検討会議で締約国によって承認された後、CCWにおけるLAWSに関する議論において極めて重要な位置づけを付与されている。その概要は以下のとおり。
(a) 国際人道法(IHL) は、 LAWS の潜在的な開発及び使用 を含む、 全ての兵器システムに完全に適用される。
(b) 兵器システムの使用の決定に当たっては、 説明責任が機械に転嫁できないため、人間の責任が確保されなければならない。人間の責任の確保は、兵器システムのライフ・サイクル全体で考慮されるべき。
(c) 人間と機械の相互関係は、様々な形態を取り得るもので、かつ、兵器のライフ・サイクルの様々な段階で起こり得るものである。人間と機械の相互関係は、LAWS関連の新興技術に基づく兵器システムの潜在的な使用が、適用可能な国際法、特に国際人道法に従うことを確保すべき。人間と機械の相互関係の特性と程度の決定に際しては、運用の状況、兵器システム全体としての特徴や性能を含む様々な要因が考慮されるべき。
(d) CCWの枠組みにおける新たな兵器システムの開発、配備及び使用における説明責任は、責任ある人間の指揮統制系統の範囲内における兵器システムの運用を通じたものを含め、適用可能な 国際法に従って確保されなければならない。
(e) 国際法の下での国家の義務に従い、新たな兵器、戦闘の手段又は方法の研究・開発・取得・採用に当たっては、その使用/利用が一部又は全ての状況において、国際法で禁じられているか否かを決めなければならない。
(f) LAWS関連の新興技術に基づく新たな兵器システムの開発・取得に当たっては、 物理的な防護、適切な非物理的な予防措置(ハッキングやフィッシング対策のサイバーセキュリティを含む)、テロリスト・グループによる取得のリスク、拡散のリスクが考慮されるべき。
(g) リスク評価と緩和措置は、兵器システムにおける新興技術の設計・開発・試験・配備サイクル一部とすべき。
(h) LAWS関連の新興技術を使用する際、IHL 及びその他の適用可能な国際的な法的義務の遵守が考慮されるべき。
(i) あり得べき政策的措置の形成に際しては、LAWS関連の新興技術を擬人化すべきではない。
(j) CCW場裏での議論及びあり得べき政策的措置が、高度な自律化技術の進展やその平和的利用 へのアクセスを妨げるべきではない。
(k) CCWは、軍事的必要性と人道的考慮のバランスを追求するという条約の趣旨及び目的の文脈において、LAWS関連の新興技術の問題 を扱う適切な枠組みを提供する。
(3)2021年第6回CCW運用検討会議以降
2021年12月に開催されたCCW第6回運用検討会議で、LAWSに関し以下の宣言を盛り込んだ最終文書が締約国によって採択された。
・政府専門家グループの結論と勧告の価値及びLAWS政府専門家会合が勧告し、2019年締約国会合で認められた指針(Guiding Principles)を承認すること。
・国際人道法が、潜在的なLAWSの開発及び使用を含むすべての兵器システムに引き続き完全に適用されることを確認すること。
・LAWSの分野における新興技術に基づく兵器システムは、それが過度な傷害又は不必要な苦痛を与える性質を有する場合、又は本質的に無差別である場合、又はその他の国際人道法に従った使用が不可能である場合には、使用してはならないことを認識すること。
・武力の行使に関する決定について、人間は、常に、適用される国際法に従って説明責任を負わなければならないとの信念を有すること。
・CCWが、軍事的必要性と人道的考慮の間のバランスを追求する条約の目的及び趣旨に照らして、LAWSの分野における新興技術の問題を取り扱うための適切な枠組みを提供していると認識すること。
・特に、倫理的観点に留意しつつ、法的、軍事的及び技術的側面を考慮し、LAWSの分野における新興技術に対処する努力を継続し、強化するとの決意を新たにしたこと。
・国際法、特に国際連合憲章及び国際人道法並びに関連する倫理的観点が、政府専門家グループの継続的作業を導くべきであることを確認すること。
CCW第6回運用検討会議は、LAWS政府専門家会合をジュネーブで継続することを決定し、2022年2月11日ダミーコ(Mr. Flàvio Soares Damico)ブラジル軍縮代大使が同会合の議長に就任した。同会合は、2022年3月及び7月の計10日間開催され、各国から様々な提案書が提出され、我が国は3月、米国、英国、カナダ、オーストラリア及び韓国とともに国際人道法のLAWSへの適用等について具体的な議論を進めるべく、実用的な運用に耐え得るガイドラインやグッドプラクティス集の作成を提案し、「LAWS分野における新興技術に係る原則とグッドプラクティス」を提出し、サブスタンス面へ貢献した。一方、3月の会合は同年2月24日、ロシアによるウクライナ侵略の影響により公式協議が開催できない状態が長く続き、非公式協議の時間が多くを占める等、十分な議論の時間が確保できなかった。7月の会合において、LAWSの規制推進派と慎重派の懸隔は埋まらず、同会合で採択された報告書は過去に作成された文書の文言の確認等、最小限の内容にとどまった。
2023年は、引き続き、ダミーコブラジル軍縮代大使議長の下、同年3月6日から10日及び5月15日から19日の計10日間の政府専門家会合が開催されることなった。昨年3月、我が国は、米国、英国、カナダ、オーストラリア及び韓国とともに「LAWS分野における新興技術に係る原則とグッドプラクティス」を提出したが、グッドプラクティス集に反対する国の立場を考慮し、2023年3月のセッションに合わせ、我が国は再び米国、英国、カナダ、オーストラリア及び韓国とともに国際人道法のルールを詳らかにし、国際人道法履行に際しての、そのルールを具体的にどのように適用しようとしているのかを規定した「国際人道法を基礎とした禁止と制限の方法にかかる自律型兵器システムに関する条項案」を提出した(ポーランドが5月15日共同提案国入り)。
第2回会合では実質的な議論の深化を文章に落とし込むための議論がなされ、手続き面のみならず、実質的内容を含む同報告書(CCW/GGE.1/2023/2)には、LAWSに関する新興技術を用いた兵器システムに関して、国際人道法を遵守できないものは使用禁止であり、また、兵器システムのライフ・サイクル全体を通じて、国際人道法を含む国際法の遵守を確保するため、必要に応じて標的の種類の制限等を行うべきこと等が明記され、全会一致で採択された。他方、翌2024年のGGEのマンデートについては、時間切れのため審議できず、2023年11月のCCW締約国会議で決定されることとなった。
現状、LAWSについては、定義や特徴、人間の関与の在り方等の重要論点について、各国の立場に引き続き隔たりがある。我が国は、完全自律型の致死性を有する兵器の開発を行う意図はないが、一方で有意な人間の関与が確保された自律性を有する兵器システムは、ヒューマンエラーの減少、省力化・省人化といった安全保障上の意義を有するとの立場からLAWSの議論に積極的に参加している。また、このような観点から、上述の通り、我が国は、米国、英国、カナダ、オーストラリア及び韓国と共に2022年の政府専門家会合には、「LAWS分野における新興技術に係る原則とグッドプラクティス」を、また、2023年の政府専門家会合には、「国際人道法を基礎とした禁止と制限の方法にかかる自律型兵器システムに関する条項案」、それぞれの会合のあり得べき成果物として共同提案し議論に貢献した。
(4)日本の立場と対応
日本は、LAWSの有する安全保障上の重要性に鑑み、LAWS関連技術を有する主要国の一つとして、CCWの下に設置されたGGEを重視し、人道と安全保障の利点を考慮したバランスのとれた議論が行われ、国際社会が目指すべき取組の方向性が示されるよう、積極的にGGEに参加してきた。2023年の政府専門家会合においても、(3)で述べた通り、米国、英国、ポーランド、カナダ、オーストラリア及び韓国と作業文書を共同提案してる。
我が国は、2019年のGGEに、我が国の立場を対外的に示す作業文書を提出した。この作業文書のポイントは以下のとおり。
ア 目的:国際社会が将来目指すべき取組の方向性を示すことに貢献。
イ 議論の整理:過去の議論を踏まえ、関係者間で認識共有すべき事項を指摘。
ウ 日本の考え方:日本は、完全自律型の致死性を有する兵器を開発しないという立場。有意な人間の関与が確保された自律型兵器システムについては、ヒューマンエラーの減少や、省力化・省人化といった安全保障上の意義がある。
エ あり得べき成果:主要国を含む、国際社会で広く共通認識を確保した上でルールについて合意するのが望ましいが、意見の相違があるため、法的拘束力のある文書を直ちに実効的なルール枠組みとすることは困難。現状においては、GGEにおける議論を踏まえた成果文書が適切なオプションの一つであり、今後、他の関係者と協力する。(2023年5月26日更新)
【参考】日本のステートメントと提案等
2023年3月6日 米英加豪韓とともに(ポーランドが5月15日共同提案国入り)「国際人道法を基礎とした禁止と制限の方法にかかる自律型兵器システムに関する条項案」(作業文書)
2019年3月21日 自律型致死兵器システム(LAWS)に関する政府専門家会合に対する日本政府の作業文書(英文)