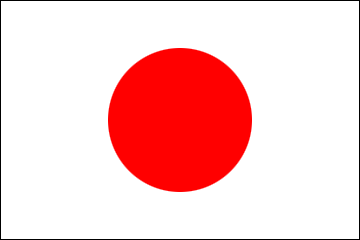核兵器の非人道的影響
令和7年1月31日
【概要】
2010年核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議の最終文書には、「会議は、核兵器のいかなる使用についても壊滅的で非人道的な結末に深い懸念を表明し、いかなる場合であっても、全ての国が国際人道法を含む適用可能な国際法を遵守する必要性を再確認する」との文言が盛り込まれた。その後、核兵器の非人道的影響に焦点を当てる動きが、オーストリア、スイス、メキシコ、ニュージーランド、南アフリカなどを中心とする「人道グループ」や市民社会を中心に活発化し、「核兵器禁止条約」作成への動きに発展していった。核軍縮は、抑止理論を中心とする国家安全保障の観点と人道的観点のバランスの上で議論されてきたが、この動きは、核軍縮が具体的な成果を生んでいないとの認識を背景に、軍事的必要性から非倫理性・非道徳性に、国家安全保障から人道主義に議論の中心を移すことにより、核軍縮を進めようとする取組とみられる。
「人道グループ」は、2015年NPT運用検討プロセスにおいて、核兵器の非人道的影響に関する共同ステートメントを計6回実施し、いかなる状況においても核兵器が二度と使用されないことの重要性を訴え、非人道的側面に焦点を当てた政治的意思を示し、全てのアプローチを支えるものとして核兵器の非人道的影響についての意義を位置づけた。これに対し、豪州が主導し、核抑止の下にある国を中心とする国々が実施した核兵器の非人道的影響に関する共同ステートメント(上記プロセスにおいて計3回実施)は、核兵器の非人道的側面に加えて国家安全保障上の側面を重視し、漸進的かつ実践的なアプローチを志向した。(日本が参加した共同ステートメントはこちらを参照)
また、2013年から2014年にかけて、核兵器の人道的影響に関する国際会議が計3回開催され、核兵器の使用がもたらす様々な影響について、科学的・技術的見地から専門家レベルで議論が行われた。(会議概要はこちらを参照)
これらの動きは、2015年の第70回国連総会第一委員会における3つの人道関連決議((1)人道グループの共同ステートメントの内容を反映した「核兵器の人道上の結末」決議(オーストリア主導)、(2)核兵器の人道的影響に関する国際会議の結果を踏まえた「核兵器の禁止及び廃絶のための人道の制約」決議(オーストリア主導)、(3)核兵器が集団安全保障を阻害すること等を宣言する「核兵器のない世界のための倫理上の責務」決議(南アフリカ主導))の提出・採択につながった。これらの決議はその後毎年国連総会第一委員会に提出・採択されてきている。
なお、(2)は、2017年以降は「核兵器禁止条約」決議に名称を変更。また、2022年には、核兵器禁止条約第1回締約国会議と同時期に、「核兵器の人道的影響に関する2022年ウィーン会議」がオーストリアにて開催された。
2024年にはアイルランド及びニュージーランドが核戦争の影響についての包括的な調査研究のための科学パネルの立ち上げを求める決議案を国連総会第一委員会に提出し、136 か国の賛成を得て国連総会で採択された。
【活動の状況】
日本は、国家安全保障の側面と核兵器の非人道的側面の二つの認識を基礎として、核軍縮・不拡散に向けた国際社会の取組を主導してきている。特に、核兵器の非人道性については、唯一の戦争被爆国として重視してきている。
上記の3つの人道関連決議については、日本の原則的立場やこれまでの政策との整合性を踏まえて投票態度を決定(注)し、採択後に概要次のとおり投票理由説明を行ってきている。
「唯一の戦争被爆国として、核兵器の非人道性についてはどの国よりも直接に理解している。こうした背景も踏まえ、日本は、核兵器の非人道性への認識を広め、深めるために、様々な努力を以前から行っている。日本としては、引き続き拡大抑止を含む安全保障政策をとり、また、安全保障と両立する形で核軍縮を進めつつも、核兵器の非人道性に関する認識が、日本の核軍縮政策の基本方針である現実的かつ実践的なアプローチの根幹をなすものであることには変わりない。他方で、核軍縮の進展には、核兵器国と非核兵器国の協力が必要である。その意味で、核兵器の非人道性への認識は国際社会を結束させる橋渡し役であるべきで、分断させてはならない。」
(注)核兵器の人道上の結末決議については、「核兵器の非人道性の認識が全てのアプローチ・取組を下支えする」という主文の文言には、日本が進める現実的かつ実践的なアプローチも含まれ、安全保障政策と両立する形で核軍縮を進めるという日本の政策と整合がとれると解されることから賛成。「核兵器禁止条約」決議には反対。「核兵器のない世界のための倫理上の責務」決議には棄権。
2010年核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議の最終文書には、「会議は、核兵器のいかなる使用についても壊滅的で非人道的な結末に深い懸念を表明し、いかなる場合であっても、全ての国が国際人道法を含む適用可能な国際法を遵守する必要性を再確認する」との文言が盛り込まれた。その後、核兵器の非人道的影響に焦点を当てる動きが、オーストリア、スイス、メキシコ、ニュージーランド、南アフリカなどを中心とする「人道グループ」や市民社会を中心に活発化し、「核兵器禁止条約」作成への動きに発展していった。核軍縮は、抑止理論を中心とする国家安全保障の観点と人道的観点のバランスの上で議論されてきたが、この動きは、核軍縮が具体的な成果を生んでいないとの認識を背景に、軍事的必要性から非倫理性・非道徳性に、国家安全保障から人道主義に議論の中心を移すことにより、核軍縮を進めようとする取組とみられる。
「人道グループ」は、2015年NPT運用検討プロセスにおいて、核兵器の非人道的影響に関する共同ステートメントを計6回実施し、いかなる状況においても核兵器が二度と使用されないことの重要性を訴え、非人道的側面に焦点を当てた政治的意思を示し、全てのアプローチを支えるものとして核兵器の非人道的影響についての意義を位置づけた。これに対し、豪州が主導し、核抑止の下にある国を中心とする国々が実施した核兵器の非人道的影響に関する共同ステートメント(上記プロセスにおいて計3回実施)は、核兵器の非人道的側面に加えて国家安全保障上の側面を重視し、漸進的かつ実践的なアプローチを志向した。(日本が参加した共同ステートメントはこちらを参照)
また、2013年から2014年にかけて、核兵器の人道的影響に関する国際会議が計3回開催され、核兵器の使用がもたらす様々な影響について、科学的・技術的見地から専門家レベルで議論が行われた。(会議概要はこちらを参照)
これらの動きは、2015年の第70回国連総会第一委員会における3つの人道関連決議((1)人道グループの共同ステートメントの内容を反映した「核兵器の人道上の結末」決議(オーストリア主導)、(2)核兵器の人道的影響に関する国際会議の結果を踏まえた「核兵器の禁止及び廃絶のための人道の制約」決議(オーストリア主導)、(3)核兵器が集団安全保障を阻害すること等を宣言する「核兵器のない世界のための倫理上の責務」決議(南アフリカ主導))の提出・採択につながった。これらの決議はその後毎年国連総会第一委員会に提出・採択されてきている。
なお、(2)は、2017年以降は「核兵器禁止条約」決議に名称を変更。また、2022年には、核兵器禁止条約第1回締約国会議と同時期に、「核兵器の人道的影響に関する2022年ウィーン会議」がオーストリアにて開催された。
2024年にはアイルランド及びニュージーランドが核戦争の影響についての包括的な調査研究のための科学パネルの立ち上げを求める決議案を国連総会第一委員会に提出し、136 か国の賛成を得て国連総会で採択された。
【活動の状況】
日本は、国家安全保障の側面と核兵器の非人道的側面の二つの認識を基礎として、核軍縮・不拡散に向けた国際社会の取組を主導してきている。特に、核兵器の非人道性については、唯一の戦争被爆国として重視してきている。
上記の3つの人道関連決議については、日本の原則的立場やこれまでの政策との整合性を踏まえて投票態度を決定(注)し、採択後に概要次のとおり投票理由説明を行ってきている。
「唯一の戦争被爆国として、核兵器の非人道性についてはどの国よりも直接に理解している。こうした背景も踏まえ、日本は、核兵器の非人道性への認識を広め、深めるために、様々な努力を以前から行っている。日本としては、引き続き拡大抑止を含む安全保障政策をとり、また、安全保障と両立する形で核軍縮を進めつつも、核兵器の非人道性に関する認識が、日本の核軍縮政策の基本方針である現実的かつ実践的なアプローチの根幹をなすものであることには変わりない。他方で、核軍縮の進展には、核兵器国と非核兵器国の協力が必要である。その意味で、核兵器の非人道性への認識は国際社会を結束させる橋渡し役であるべきで、分断させてはならない。」
(注)核兵器の人道上の結末決議については、「核兵器の非人道性の認識が全てのアプローチ・取組を下支えする」という主文の文言には、日本が進める現実的かつ実践的なアプローチも含まれ、安全保障政策と両立する形で核軍縮を進めるという日本の政策と整合がとれると解されることから賛成。「核兵器禁止条約」決議には反対。「核兵器のない世界のための倫理上の責務」決議には棄権。