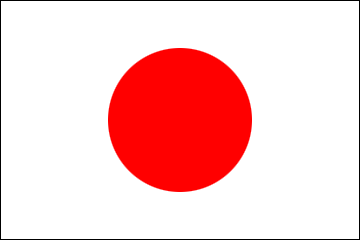対人地雷等
令和5年6月8日
1 問題の現状
武力紛争時のみならず、紛争後や平時においても、対人地雷や即席爆発装置等の爆発物は、一般人を含め深刻な被害をもたらしている。その現状と国際社会の取組及び我が国の取組についてまとめると以下のとおり(クラスター弾及び人口密集地における爆発性兵器(EWIPA)については、それぞれの項目を参照)。
(1)対人地雷問題
紛争地域を中心に埋設された地雷は、非戦闘員である一般市民に対し無差別に被害を与えるという、人道上極めて重大な問題を引き起こし、紛争終結後の地域復興と開発にとっても大きな障害となる。2021年記録された地雷及び爆発性戦争残存物(ERW)による死傷者数は、少なくとも5,544人に上る(「Landmine Monitor 2022」報告)。この対人地雷の問題に対処するため、特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)改正議定書IIが一定の規制を設けていたが、さらに1999年に発効した対人地雷禁止条約は、対人地雷の除去を締約国に義務づけた。この義務に基づき2021年には、少なくとも117,863個の埋設地雷が除去され、5,500万発以上の貯蔵対人地雷が廃棄されたとされる(同上)。
一方で、世界における記録された過去10年間(2013年以降)の地雷及び爆発性戦争残像物による年間死傷者数は、約3,500人から9,500人の間で推移しており、直近では2020年が7,073人、2021年が5,544人であった。(同上)。また、現在、ロシアの侵攻による戦争が行われているウクライナでも、対人地雷が使用された疑いが生じている。
(2)即席爆発装置(Improvised Explosive Device:IED)
国連地雷対策サービス部(UNMAS)によると、非対称戦に代表される紛争の増加や即席爆発装置即席爆発装置の使用増加が広がっており、爆発物や即席爆発装置は、少なくとも50か国と地域に影響を与え、過去10年間で17万人以上の死傷者を出した。即席爆発装置は主に非国家主体によって使用され、即席爆発装置関連の死傷者の80%を民間人が占めている。即席爆発装置の設計、サイズ、設置方法は多様で、即席爆発装置の位置を特定し、被害を軽減するために採用された対策を回避するために、即席爆発装置は進化し続けている。その製造に必要な技術や部品は、インターネットの普及により国境を越えて容易に入手することができる。また、安全が確認されていない軍用弾薬や、農業用化学薬品など合法的なデュアル・ユースに使用される前駆物質を用いて、安価で簡単に製造することができる特徴がある。(UNMAS ANNUAL REPORT 2021)
(1)対人地雷問題
紛争地域を中心に埋設された地雷は、非戦闘員である一般市民に対し無差別に被害を与えるという、人道上極めて重大な問題を引き起こし、紛争終結後の地域復興と開発にとっても大きな障害となる。2021年記録された地雷及び爆発性戦争残存物(ERW)による死傷者数は、少なくとも5,544人に上る(「Landmine Monitor 2022」報告)。この対人地雷の問題に対処するため、特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)改正議定書IIが一定の規制を設けていたが、さらに1999年に発効した対人地雷禁止条約は、対人地雷の除去を締約国に義務づけた。この義務に基づき2021年には、少なくとも117,863個の埋設地雷が除去され、5,500万発以上の貯蔵対人地雷が廃棄されたとされる(同上)。
一方で、世界における記録された過去10年間(2013年以降)の地雷及び爆発性戦争残像物による年間死傷者数は、約3,500人から9,500人の間で推移しており、直近では2020年が7,073人、2021年が5,544人であった。(同上)。また、現在、ロシアの侵攻による戦争が行われているウクライナでも、対人地雷が使用された疑いが生じている。
(2)即席爆発装置(Improvised Explosive Device:IED)
国連地雷対策サービス部(UNMAS)によると、非対称戦に代表される紛争の増加や即席爆発装置即席爆発装置の使用増加が広がっており、爆発物や即席爆発装置は、少なくとも50か国と地域に影響を与え、過去10年間で17万人以上の死傷者を出した。即席爆発装置は主に非国家主体によって使用され、即席爆発装置関連の死傷者の80%を民間人が占めている。即席爆発装置の設計、サイズ、設置方法は多様で、即席爆発装置の位置を特定し、被害を軽減するために採用された対策を回避するために、即席爆発装置は進化し続けている。その製造に必要な技術や部品は、インターネットの普及により国境を越えて容易に入手することができる。また、安全が確認されていない軍用弾薬や、農業用化学薬品など合法的なデュアル・ユースに使用される前駆物質を用いて、安価で簡単に製造することができる特徴がある。(UNMAS ANNUAL REPORT 2021)
2 改正議定書II(特定通常兵器使用禁止制限条約の議定書の一つ)
(1)概要
改正議定書IIは、地雷、ブービートラップ(食物、玩具等外見上無害な物の中に爆発物等を仕掛けたもの。)及び他の類似の装置の使用を禁止又は制限する条約(1998年発効)である。地雷やこれらの装置は、非戦闘員である一般市民に対し無差別に被害を与える恐れがあり、地域の紛争終結後の復興と開発にとって大きな障害となっている。
現在、11か国 (中国、キューバ、インド、イラン、ミャンマー、北朝鮮、パキスタン、ロシア、シンガポール、韓国、ベトナム)が対人地雷を生産(Landmine Monitor 2022報告)。又:米国は、2022年6月に対人地雷の生産中止を宣言した。これらの内、中国、インド、パキスタン、ロシア、韓国、米国は改正議定書IIに加盟しているが、イラン、ミャンマー、北朝鮮、シンガポール、ベトナムは加入していない。又、上記11か国及び米国のいずれも対人地雷禁止条約(後述)には加入していない。
(2)改正の経緯
特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)の下で、1980年に採択された地雷等の使用の禁止または制限に関する議定書(議定書II)は、内乱には適用されず、また探知不可能な地雷等を禁止していなかった。しかし、地雷問題に関する国際的な機運の盛り上がりを受けて、1996年5月、議定書IIは改正された。この改正議定書IIは内乱にも適用されることとなり、また探知不可能なもの及び自己破壊装置のないもの等、悪質な対人地雷を原則使用禁止とし、移譲を制限する等規制の内容が強化された。
(3)即席爆発装置
近年は、上述のとおり、即席爆発装置による被害が急激に増えており、火器を除く他の如何なる兵器よりも甚大な殺傷被害を年々出していると言われ、この問題が主要な議題となっている。
(4)最近の動き(日本議長の下での締約国会議開催)
2021年の改正議定書IIの年次締約国会議議長を小笠原一郎軍縮会議日本政府代表部大使が務めた同年次締約国会議では、2016年次締約国会議にて採択された即席爆発装置宣言を改訂した。改訂した同宣言は年末の第6回CCW運用検討会議に提出され、同会議の最終文書(CCW/CONF.VI/11)において締約国により歓迎された。改訂版即席爆発装置宣言全文(CCW/AP.II/CONF.23./6)のポイントは、以下のとおり。
ア 即席爆発装置による脅威に対抗するため、国家及び地域の対応の発展強化に努力する。
イ 即席爆発装置の製造に使用され得る爆発物及び部品の転用を防止するため、それらの備蓄管理を含む実行可能な全ての措置を講じ、かつ協力的に行動する。
ウ 即席爆発装置の脅威に対処することを目的とした対策、ベストプラクティス、方法並びに即席爆発装置攻撃に関する情報を自主的に交換する。
エ 他に関連する国際機関及びネットワークとの間で、即席爆発装置への対処の意識向上を継続する。
オ 必要に応じて即席爆発装置リスク教育キャンペーンを行う
カ 国家、国際連合及び関連する専門知識を有する国際、地域及びその他の機関に対し、即席爆発装置の脅威に対抗する当該国の能力を強化するための技術、財政的及び物的援助を提供することを奨励する。
また同締約国会議では、国際協力機構(JICA)が、地雷対策に係る南南協力についてのプレゼンテーションを行い、我が国が行ってきた組織・人材育成を含む包括的な地雷対策支援プログラムの実績を紹介した。さらに、JICAの地雷対策支援活動の長年のパートナーであるカンボジアの地雷対策センター(CMAC)、そしてカンボジアからキャパシティビルディング支援を受けて地雷対策を進めてきたコロンビアの地雷対策当局と共に、これまでの活動から得られた教訓やグットプラクティスを、締約国と共有した。
2022年の改正議定書II年次締約国会議では、同年2月24日に開始されたロシアによるウクライナ侵攻を受け、我が国を含む西側諸国が、ロシアによるウクライナ侵攻を非難するとともに、その他いくつかの国は、ロシア軍による即席爆発装置使用、死体へのブービートラップの仕掛け等、改正議定書II不遵守行為を非難した。右にロシア側が反論し、議論が膠着する場面が見られ、結果として、成果は即席爆発装置報告書の承認や予算等手続事項に合意するに留まった。
改正議定書IIは、地雷、ブービートラップ(食物、玩具等外見上無害な物の中に爆発物等を仕掛けたもの。)及び他の類似の装置の使用を禁止又は制限する条約(1998年発効)である。地雷やこれらの装置は、非戦闘員である一般市民に対し無差別に被害を与える恐れがあり、地域の紛争終結後の復興と開発にとって大きな障害となっている。
現在、11か国 (中国、キューバ、インド、イラン、ミャンマー、北朝鮮、パキスタン、ロシア、シンガポール、韓国、ベトナム)が対人地雷を生産(Landmine Monitor 2022報告)。又:米国は、2022年6月に対人地雷の生産中止を宣言した。これらの内、中国、インド、パキスタン、ロシア、韓国、米国は改正議定書IIに加盟しているが、イラン、ミャンマー、北朝鮮、シンガポール、ベトナムは加入していない。又、上記11か国及び米国のいずれも対人地雷禁止条約(後述)には加入していない。
(2)改正の経緯
特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)の下で、1980年に採択された地雷等の使用の禁止または制限に関する議定書(議定書II)は、内乱には適用されず、また探知不可能な地雷等を禁止していなかった。しかし、地雷問題に関する国際的な機運の盛り上がりを受けて、1996年5月、議定書IIは改正された。この改正議定書IIは内乱にも適用されることとなり、また探知不可能なもの及び自己破壊装置のないもの等、悪質な対人地雷を原則使用禁止とし、移譲を制限する等規制の内容が強化された。
(3)即席爆発装置
近年は、上述のとおり、即席爆発装置による被害が急激に増えており、火器を除く他の如何なる兵器よりも甚大な殺傷被害を年々出していると言われ、この問題が主要な議題となっている。
(4)最近の動き(日本議長の下での締約国会議開催)
2021年の改正議定書IIの年次締約国会議議長を小笠原一郎軍縮会議日本政府代表部大使が務めた同年次締約国会議では、2016年次締約国会議にて採択された即席爆発装置宣言を改訂した。改訂した同宣言は年末の第6回CCW運用検討会議に提出され、同会議の最終文書(CCW/CONF.VI/11)において締約国により歓迎された。改訂版即席爆発装置宣言全文(CCW/AP.II/CONF.23./6)のポイントは、以下のとおり。
ア 即席爆発装置による脅威に対抗するため、国家及び地域の対応の発展強化に努力する。
イ 即席爆発装置の製造に使用され得る爆発物及び部品の転用を防止するため、それらの備蓄管理を含む実行可能な全ての措置を講じ、かつ協力的に行動する。
ウ 即席爆発装置の脅威に対処することを目的とした対策、ベストプラクティス、方法並びに即席爆発装置攻撃に関する情報を自主的に交換する。
エ 他に関連する国際機関及びネットワークとの間で、即席爆発装置への対処の意識向上を継続する。
オ 必要に応じて即席爆発装置リスク教育キャンペーンを行う
カ 国家、国際連合及び関連する専門知識を有する国際、地域及びその他の機関に対し、即席爆発装置の脅威に対抗する当該国の能力を強化するための技術、財政的及び物的援助を提供することを奨励する。
また同締約国会議では、国際協力機構(JICA)が、地雷対策に係る南南協力についてのプレゼンテーションを行い、我が国が行ってきた組織・人材育成を含む包括的な地雷対策支援プログラムの実績を紹介した。さらに、JICAの地雷対策支援活動の長年のパートナーであるカンボジアの地雷対策センター(CMAC)、そしてカンボジアからキャパシティビルディング支援を受けて地雷対策を進めてきたコロンビアの地雷対策当局と共に、これまでの活動から得られた教訓やグットプラクティスを、締約国と共有した。
2022年の改正議定書II年次締約国会議では、同年2月24日に開始されたロシアによるウクライナ侵攻を受け、我が国を含む西側諸国が、ロシアによるウクライナ侵攻を非難するとともに、その他いくつかの国は、ロシア軍による即席爆発装置使用、死体へのブービートラップの仕掛け等、改正議定書II不遵守行為を非難した。右にロシア側が反論し、議論が膠着する場面が見られ、結果として、成果は即席爆発装置報告書の承認や予算等手続事項に合意するに留まった。
3 対人地雷禁止条約(正式名称「対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約」、通称「オタワ条約」)(Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction)
(1)改正議定書II 上記2(1)は、対人地雷の「生産」や「貯蔵」を禁止はするには至っておらず、また、「使用」や「移譲」の禁止に関しても一定の条件の下の規制となっており、全面禁止とはなっていない。改正議定書IIに基づく部分的な禁止では対人地雷問題の抜本的な解決には至らず、使用、貯蔵、生産、移譲の全面禁止が必要であるとする国際世論を背景に、カナダ政府が1996年にオタワで開催した国際会議に端を発する、いわゆるオタワ・プロセスを通じて、対人地雷禁止条約が作成された。同上約は、1997年12月のオタワでの署名式において署名のため各国に開放され、1999年3月1日に発効した(日本は、1997年12月3日に署名し、1998年9月30日に締結した。)。2020年5 月現在、対人地雷禁止条約の締約国数は164か国・地域に上る。他方、対人地雷生産国である、中国、ロシア、インド、韓国、北朝鮮等11か国や、2022年に対人地雷の生産中止を宣言した米国は加入していない。
(2)同条約は、対人地雷の使用、貯蔵、生産、移譲等を全面的に禁止し、貯蔵地雷の4年以内の廃棄、埋設地雷の10年以内の除去等を義務付けるとともに、地雷除去、犠牲者支援についての国際協力・援助等を規定している。2003年2月、対人地雷禁止条約の義務を履行するために、我が国は保有する全ての対人地雷(ただし同条約第3条で認められている、地雷の探知、除去又は廃棄の技術の開発及び訓練のための若干数の対人地雷を除く。)の廃棄を終了した。
(3)運用検討会議(第1回~第3回)2004年には条約発効後初の検討会議がナイロビ(ケニア)で開催され、「行動計画」、「ハイレベル宣言」等の文書が採択された。その後検討会議は5年毎に開催されている。
(4)2019年11月、オスロ(ノルウェー)で第4回検討会議が開催され、我が国から尾身朝子外務大臣政務官(当時)が参加した。同検討会議では、今後5年間の行動指針となる「オスロ行動計画」や締約国のコミットメントを謳う「オスロ政治宣言」が採択された。また、2025年までに対人地雷のない世界を達成するという従来の政治目標に向け、更に取組を加速させていくことが確認された。
(2)同条約は、対人地雷の使用、貯蔵、生産、移譲等を全面的に禁止し、貯蔵地雷の4年以内の廃棄、埋設地雷の10年以内の除去等を義務付けるとともに、地雷除去、犠牲者支援についての国際協力・援助等を規定している。2003年2月、対人地雷禁止条約の義務を履行するために、我が国は保有する全ての対人地雷(ただし同条約第3条で認められている、地雷の探知、除去又は廃棄の技術の開発及び訓練のための若干数の対人地雷を除く。)の廃棄を終了した。
(3)運用検討会議(第1回~第3回)2004年には条約発効後初の検討会議がナイロビ(ケニア)で開催され、「行動計画」、「ハイレベル宣言」等の文書が採択された。その後検討会議は5年毎に開催されている。
(4)2019年11月、オスロ(ノルウェー)で第4回検討会議が開催され、我が国から尾身朝子外務大臣政務官(当時)が参加した。同検討会議では、今後5年間の行動指針となる「オスロ行動計画」や締約国のコミットメントを謳う「オスロ政治宣言」が採択された。また、2025年までに対人地雷のない世界を達成するという従来の政治目標に向け、更に取組を加速させていくことが確認された。
4 ODAを通じた日本の取組
(1)地雷被害国の多くは発展途上国であり、対人地雷禁止条約に規定される10年の地雷除去期限 内に除去を完了するためには、先進国からの支援を必要とするケースが多い。日本は2022年に22か国において地雷・不発弾対策に約5,200万ドルの支援を実施した。地雷対策分野で日本は世界の主要ドナーである(2021年のドナー国としては、第1位米国、第2位ドイツ、第3位日本(「Landmine Monitor 2022」報告)。
(2)日本の地雷対策支援では、特に、被害国や被害コミュニティとの協議を通じ、現地の人々が設定した目標について具体的成果が得られるような支援を続けてきた。例えば、カンボジアの地雷対策センター(CMAC)に専門家を派遣し、連携しながらカンボジア政府の「国家地雷活動戦略プラン」に沿って迅速な除去活動や被害地域のインフラ整備を行ってきた。最近では、JICAの取組は、カンボジアのCMACを起点として、ラオス、アンゴラ、コロンビア等を巻き込んだ三角協力に発展している。
(3)また、日本は、国際機関を通じた支援も行っている。例えば、2023年4月には、国連の地雷対策機関UNMAS経由で553万ドル、国際赤十字委員会(ICRC)経由で、約2,100万ドルの地雷対策支援を決定し、数多くの地雷が残存するアフガニスタン、イエメン、イラク、エチオピア、シリア、スーダン、ソマリア、ミャンマーや、新たな懸念が生じているウクライナにおいて地雷・不発弾の脅威を削減するための事業を現在実施している。
(4)2020年11月以降、日本は2年間の任期で4カ国から構成される「協力・支援強化」委員となり、2021年11月の第19回対人地雷禁止条約締約国会議の期間中、日本は、国際協力機構(JICA)と共催し、カンボジア、コロンビアとともに「平和構築のための地雷対策-南南協力の主要なパートナーとしてのカンボジア地雷対策センター(CMAC)の成長とJICAの役割」と題したサイドイベントを開催し、日本の地雷対策支援を紹介した。また、第19回対人地雷禁止条約締約国会議で、日本は「協力と支援の強化」委員長に選ばれ、永井奈菜軍縮会議日本政府代表部書記官が委員長に就任した。永井書記官は、同委員会委員長として2022年6月の会期間会合のパネルディスカッション(「地雷除去と協力支援」及び「被害者支援と協力支援」)の共同議長を務めた他、第21回締約国会議 (2022年11月)では、各国の協力・支援分野の実施状況の報告や、同委員会の活動報告等を行うとともに、これらの会合のマージンで、協力・支援強化委員会が主催した4つの各国別支援会合(チャド、カンボジア、ギニア・ビサウ及び南スーダン )のファシリテーターを務める等貢献した。
(5)さらに2022年6月の会期間会合においては、地雷除去に関するパネルディスカッションにおいて、JICA及びCMACがそれぞれ南南協力をテーマに共同プレゼンテーションを実施し、日本の地雷対策支援におけるこれまでの取組や貢献を国際社会にアピールした。(2023年5月26日更新)
【参考】日本のステートメント
(2)日本の地雷対策支援では、特に、被害国や被害コミュニティとの協議を通じ、現地の人々が設定した目標について具体的成果が得られるような支援を続けてきた。例えば、カンボジアの地雷対策センター(CMAC)に専門家を派遣し、連携しながらカンボジア政府の「国家地雷活動戦略プラン」に沿って迅速な除去活動や被害地域のインフラ整備を行ってきた。最近では、JICAの取組は、カンボジアのCMACを起点として、ラオス、アンゴラ、コロンビア等を巻き込んだ三角協力に発展している。
(3)また、日本は、国際機関を通じた支援も行っている。例えば、2023年4月には、国連の地雷対策機関UNMAS経由で553万ドル、国際赤十字委員会(ICRC)経由で、約2,100万ドルの地雷対策支援を決定し、数多くの地雷が残存するアフガニスタン、イエメン、イラク、エチオピア、シリア、スーダン、ソマリア、ミャンマーや、新たな懸念が生じているウクライナにおいて地雷・不発弾の脅威を削減するための事業を現在実施している。
(4)2020年11月以降、日本は2年間の任期で4カ国から構成される「協力・支援強化」委員となり、2021年11月の第19回対人地雷禁止条約締約国会議の期間中、日本は、国際協力機構(JICA)と共催し、カンボジア、コロンビアとともに「平和構築のための地雷対策-南南協力の主要なパートナーとしてのカンボジア地雷対策センター(CMAC)の成長とJICAの役割」と題したサイドイベントを開催し、日本の地雷対策支援を紹介した。また、第19回対人地雷禁止条約締約国会議で、日本は「協力と支援の強化」委員長に選ばれ、永井奈菜軍縮会議日本政府代表部書記官が委員長に就任した。永井書記官は、同委員会委員長として2022年6月の会期間会合のパネルディスカッション(「地雷除去と協力支援」及び「被害者支援と協力支援」)の共同議長を務めた他、第21回締約国会議 (2022年11月)では、各国の協力・支援分野の実施状況の報告や、同委員会の活動報告等を行うとともに、これらの会合のマージンで、協力・支援強化委員会が主催した4つの各国別支援会合(チャド、カンボジア、ギニア・ビサウ及び南スーダン )のファシリテーターを務める等貢献した。
(5)さらに2022年6月の会期間会合においては、地雷除去に関するパネルディスカッションにおいて、JICA及びCMACがそれぞれ南南協力をテーマに共同プレゼンテーションを実施し、日本の地雷対策支援におけるこれまでの取組や貢献を国際社会にアピールした。(2023年5月26日更新)
【参考】日本のステートメント