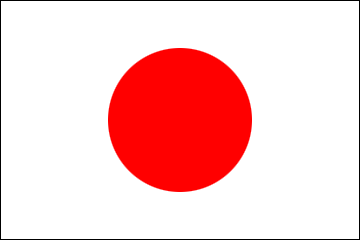核軍縮の検証
令和3年10月6日
1 概要
核軍縮を進めるに当たっては、条約やコミットメントの下での義務が関係当事国において確実に遵守されていることが不可欠である。条約等の一方の当事国が義務を遵守していない場合に、他方の当事国が義務を履行すれば、義務を履行した当事国が安全保障上甚大な不利益を被ることになりかねないからである。したがって、義務の遵守状況を検証することは、核軍縮のプロセスを確実なものとするために極めて重要な意義を有している。
このような検証は、例えば、新戦略兵器削減条約(新START)における米国及びロシア両国政府による相互査察等、核兵器国間で既に行われているが、将来における更なる核軍縮の進展のために、核兵器国のみならず非核兵器国も交えた形で多数国間の検証体制の在り方について検討を始めることは大きな意義がある。このため、有志国によるイニシアティブや国連の場において、核兵器国及び非核兵器国の双方を交える形で核軍縮検証について議論されている。
2000年のNPT運用検討会議の最終文書では、核軍縮の「透明性、不可逆性、検証可能性」の原則が合意され、核軍縮のための国際約束に規定されている義務を締約国が履行し遵守していることを確認できる検証可能性は、不可逆性の担保(いったんとられた核軍縮措置が後戻りしないように確保すること)及び透明性の向上とともに、核軍縮プロセスを進める上での3原則として位置付けられている。
このような検証は、例えば、新戦略兵器削減条約(新START)における米国及びロシア両国政府による相互査察等、核兵器国間で既に行われているが、将来における更なる核軍縮の進展のために、核兵器国のみならず非核兵器国も交えた形で多数国間の検証体制の在り方について検討を始めることは大きな意義がある。このため、有志国によるイニシアティブや国連の場において、核兵器国及び非核兵器国の双方を交える形で核軍縮検証について議論されている。
2000年のNPT運用検討会議の最終文書では、核軍縮の「透明性、不可逆性、検証可能性」の原則が合意され、核軍縮のための国際約束に規定されている義務を締約国が履行し遵守していることを確認できる検証可能性は、不可逆性の担保(いったんとられた核軍縮措置が後戻りしないように確保すること)及び透明性の向上とともに、核軍縮プロセスを進める上での3原則として位置付けられている。
2 核軍縮検証の課題(非核兵器国の関与)
核兵器は一般的に国家安全保障における最高機密に属することから、そうした極めて機微な情報に配慮しながら核軍縮措置を検証することは核兵器国間であっても本来技術的に非常に難しい。そのような核軍縮の検証を非核兵器国の関与を得ながら進めていく場合、核兵器国は非核兵器国に対して核兵器の製造や取得につき何ら援助や奨励を行ってはならないとのNPT第1条の義務、また、非核兵器国は核兵器の製造・取得について何ら援助を受け取ってはならないとの同第2条の義務に違反しない形で進めなければならないとのより困難な問題に直面する。
同時に、核兵器国による核軍縮措置の検証に対しては、機微性や機密性の高い情報を保護しながらも、非核兵器国が信頼できるレベルのものでなければならない。現時点では非核兵器国が核兵器国による核軍縮の検証に実際に参加することは具体的に想定されていないものの、将来的には、核軍縮が進み、核弾頭数が低いレベルとなる段階、あるいは、実際に核兵器のない世界が達成される段階においては、核軍縮措置の検証は現在のような当事国となる核兵器国によるもののみではなく、非核兵器国も交えたより国際的な検証体制が必要となろう。また、将来的に核軍縮が進展すればするほど、1個当たりの核兵器の戦略的価値がますます高まることとなり、より精緻な検証と高い信頼性が求められ、核軍縮関連条約に要求される検証のレベルも高まることとなろう。したがって、核軍縮における検証や透明性の重要性は今後高まっていくものと考えられる。
同時に、核兵器国による核軍縮措置の検証に対しては、機微性や機密性の高い情報を保護しながらも、非核兵器国が信頼できるレベルのものでなければならない。現時点では非核兵器国が核兵器国による核軍縮の検証に実際に参加することは具体的に想定されていないものの、将来的には、核軍縮が進み、核弾頭数が低いレベルとなる段階、あるいは、実際に核兵器のない世界が達成される段階においては、核軍縮措置の検証は現在のような当事国となる核兵器国によるもののみではなく、非核兵器国も交えたより国際的な検証体制が必要となろう。また、将来的に核軍縮が進展すればするほど、1個当たりの核兵器の戦略的価値がますます高まることとなり、より精緻な検証と高い信頼性が求められ、核軍縮関連条約に要求される検証のレベルも高まることとなろう。したがって、核軍縮における検証や透明性の重要性は今後高まっていくものと考えられる。
3 具体的な取組
3-1 IPNDV
このような中、米国は、2014年、核兵器のライフサイクルにおけるモニタリング及び検証に関する複雑な課題の理解を促進し、核軍縮のモニタリング及び検証に関する国際的な能力・専門性を構築・多様化すべく「核軍縮検証のための国際パートナーシップ(IPNDV: International Partnership for Nuclear Disarmament Verification)」を立ち上げた。核軍縮の検証に関する議論に非核兵器国が参加する新たな国際的な枠組みとして注目される。IPNDVは、これまでに、核兵器の解体、保管、輸送等、核兵器を廃棄する一連の段階について、モニタリング及び検証活動上の課題、技術、手続等について議論を深めたほか、机上・実働演習などが行われてきた。
3-2 核軍縮検証に関する政府専門家会合
第71回国連総会(2016年)では、ノルウェーが主導して核軍縮検証に関する決議(A/RES/71/67)が採択され、これに基づいて核軍縮検証に関する政府専門家会合(GGE)が設置された。GGEは、2018年から翌年にかけてジュネーブで3回にわたり会合し、核軍縮検証の原則及び在り方についての概念整理に加え、過去の検証制度から得られる教訓、能力構築支援等について検討を行った。GGEは、3度に亘る会議を経て、国連加盟国及び関連する国際的な軍縮機関(Disarmament Machinery)がGGEのとりまとめる報告書を検討すること、報告書を踏まえて核軍縮を進める上での検証の役割に関する作業を更に検討すること等の勧告を含む報告書を採択し、2019年5月に公表した(A/74/90)。第74回総会(2019年)では、2021年から22年にかけて新たなGGEを設置する決議が採択され(A/RES/74/50、ロシアのみが反対)た。同GGEは、流行する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受け、当初予定されていたジュネーブでの会合は延期され、2021年9月末以降、本格的な活動を開始する見込みである。
3-3 その他の取組
このほか、1990年代後半の米国、ロシア、国際原子力機関(IAEA)のトライラテラル・イニシアティブは、戦略核兵器削減条約(START)の履行などの核兵器削減の結果、余剰となった核分裂性物質(高濃縮ウランとプルトニウム)がその後核兵器用に再び用いられないことを確認するための検証技術を探求することを目的として実施された。
英国も、2000年以来、核弾頭解体の検証について英国防省を中心に独自研究及び米国と共同研究を行い、2005年NPT運用検討プロセスで研究成果を随時発表してきた。また、英国は、2007年には、核兵器国と非核兵器国が協力して、核軍縮においてより効果的かつ相互に信頼できる検証措置の実現を目指すという趣旨の下、ノルウェーとの共同研究プロジェクトを開始した。英国及びノルウェーは、同プロジェクトについて、2010年NPT運用検討会議において紹介した。
2015年、英国、米国、ノルウェー及びスウェーデンは、英国及びノルウェーのイニシアティブ等を基に「Quad」イニシアティブを設立し、2017年10月の核軍縮検証の実働演習をはじめとする取組を進めている。これら一連の取組は、上述の核軍縮検証に関する国連総会決議のきっかけになった。
このような中、米国は、2014年、核兵器のライフサイクルにおけるモニタリング及び検証に関する複雑な課題の理解を促進し、核軍縮のモニタリング及び検証に関する国際的な能力・専門性を構築・多様化すべく「核軍縮検証のための国際パートナーシップ(IPNDV: International Partnership for Nuclear Disarmament Verification)」を立ち上げた。核軍縮の検証に関する議論に非核兵器国が参加する新たな国際的な枠組みとして注目される。IPNDVは、これまでに、核兵器の解体、保管、輸送等、核兵器を廃棄する一連の段階について、モニタリング及び検証活動上の課題、技術、手続等について議論を深めたほか、机上・実働演習などが行われてきた。
3-2 核軍縮検証に関する政府専門家会合
第71回国連総会(2016年)では、ノルウェーが主導して核軍縮検証に関する決議(A/RES/71/67)が採択され、これに基づいて核軍縮検証に関する政府専門家会合(GGE)が設置された。GGEは、2018年から翌年にかけてジュネーブで3回にわたり会合し、核軍縮検証の原則及び在り方についての概念整理に加え、過去の検証制度から得られる教訓、能力構築支援等について検討を行った。GGEは、3度に亘る会議を経て、国連加盟国及び関連する国際的な軍縮機関(Disarmament Machinery)がGGEのとりまとめる報告書を検討すること、報告書を踏まえて核軍縮を進める上での検証の役割に関する作業を更に検討すること等の勧告を含む報告書を採択し、2019年5月に公表した(A/74/90)。第74回総会(2019年)では、2021年から22年にかけて新たなGGEを設置する決議が採択され(A/RES/74/50、ロシアのみが反対)た。同GGEは、流行する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受け、当初予定されていたジュネーブでの会合は延期され、2021年9月末以降、本格的な活動を開始する見込みである。
3-3 その他の取組
このほか、1990年代後半の米国、ロシア、国際原子力機関(IAEA)のトライラテラル・イニシアティブは、戦略核兵器削減条約(START)の履行などの核兵器削減の結果、余剰となった核分裂性物質(高濃縮ウランとプルトニウム)がその後核兵器用に再び用いられないことを確認するための検証技術を探求することを目的として実施された。
英国も、2000年以来、核弾頭解体の検証について英国防省を中心に独自研究及び米国と共同研究を行い、2005年NPT運用検討プロセスで研究成果を随時発表してきた。また、英国は、2007年には、核兵器国と非核兵器国が協力して、核軍縮においてより効果的かつ相互に信頼できる検証措置の実現を目指すという趣旨の下、ノルウェーとの共同研究プロジェクトを開始した。英国及びノルウェーは、同プロジェクトについて、2010年NPT運用検討会議において紹介した。
2015年、英国、米国、ノルウェー及びスウェーデンは、英国及びノルウェーのイニシアティブ等を基に「Quad」イニシアティブを設立し、2017年10月の核軍縮検証の実働演習をはじめとする取組を進めている。これら一連の取組は、上述の核軍縮検証に関する国連総会決議のきっかけになった。
4 日本の立場
核軍縮検証は、核兵器国と非核兵器国が共に取り組むことのできる数少ない措置であり、核兵器のない世界に向けた不可欠な取組である。核兵器国と非核兵器国の双方が関与し、透明性を保ちながら具体的手法を確立する過程で双方の信頼醸成を図ることにより、また、信頼に足る核軍縮検証メカニズムによって核軍縮義務の遵守が確保されることを通じて、核軍縮の進展と安全保障環境改善の双方に資する。現実的かつ実践的なアプローチをとる日本は、核兵器のない世界の実現に向けた中長期的な取組の一環として、核軍縮プロセスにおける検証の検討や検証技術の開発に取り組むことは重要と考えている。また、非核兵器国である日本は、核軍縮そのものの主体的なアクターではないものの、その大規模な原子力活動に対して高度なIAEA保障措置を受けているため検証や査察に関する多くの経験を有しており、高い技術力を持っていることから、核軍縮の検証においても十分に貢献し得る。
こうした考えに基づき、日本は、核軍縮検証のメカニズムを構築する上で一定の役割を果たすため、上述のIPNDV及び核軍縮検証に関するGGEにも積極的に関与している。2018年から翌年にかけて開催されたGGEには中根猛外務省参与が専門家として参加し、核軍縮検証の全体像を把握し、将来的な作業につなげていく観点から、核軍縮のフェーズ(段階目標)に応じた検証の具体的な技術、開発すべき研究、能力構築等について整理したチャート(「Main elements to be considered for effective Verification of Nuclear Disarmament」)を提出し、議論に貢献した。同チャートは報告書の附属文書として公表されている。2021年から22年にかけて開催される新たなGGE(上述)には、我が国からは樋川和子大阪女学院大学教授が専門家として参加している。
また、核軍縮の実質的な進展のための賢人会議が2019年10月にとりまとめた議長レポートは、上記3-3のような各種の取組が核兵器国と非核兵器国の間の協力として有用であり、これらの活動目標は、非核兵器国に機微情報を開示することなく、高いレベルの信頼を提供し、費用対効果の高い技術の発展であるべき旨指摘した上で、侵入やスパイ行為、監視・検証技術が悪用される可能性についての懸念を緩和するための人的交流、現地査察、合同検証チーム等の補完的メカニズムの必要性についても言及している。
我が国が2020年(第75回)国連総会第一委員会に提出した核兵器廃絶決議においても、国連加盟国が、核軍縮検証のための国際パートナーシップ(IPNDV)を含め、国連及び軍縮会議の場で核軍縮検証について具体的な貢献を継続するよう奨励している。
こうした考えに基づき、日本は、核軍縮検証のメカニズムを構築する上で一定の役割を果たすため、上述のIPNDV及び核軍縮検証に関するGGEにも積極的に関与している。2018年から翌年にかけて開催されたGGEには中根猛外務省参与が専門家として参加し、核軍縮検証の全体像を把握し、将来的な作業につなげていく観点から、核軍縮のフェーズ(段階目標)に応じた検証の具体的な技術、開発すべき研究、能力構築等について整理したチャート(「Main elements to be considered for effective Verification of Nuclear Disarmament」)を提出し、議論に貢献した。同チャートは報告書の附属文書として公表されている。2021年から22年にかけて開催される新たなGGE(上述)には、我が国からは樋川和子大阪女学院大学教授が専門家として参加している。
また、核軍縮の実質的な進展のための賢人会議が2019年10月にとりまとめた議長レポートは、上記3-3のような各種の取組が核兵器国と非核兵器国の間の協力として有用であり、これらの活動目標は、非核兵器国に機微情報を開示することなく、高いレベルの信頼を提供し、費用対効果の高い技術の発展であるべき旨指摘した上で、侵入やスパイ行為、監視・検証技術が悪用される可能性についての懸念を緩和するための人的交流、現地査察、合同検証チーム等の補完的メカニズムの必要性についても言及している。
我が国が2020年(第75回)国連総会第一委員会に提出した核兵器廃絶決議においても、国連加盟国が、核軍縮検証のための国際パートナーシップ(IPNDV)を含め、国連及び軍縮会議の場で核軍縮検証について具体的な貢献を継続するよう奨励している。