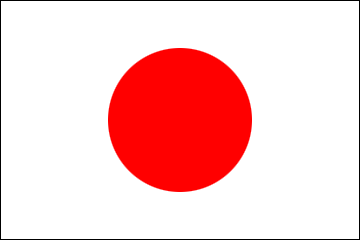核兵器の禁止
令和4年6月7日
1 核兵器の禁止の概念(2017年の核兵器禁止条約の採択に向けた動きが高まるまで)
「核兵器条約」(NWC:Nuclear Weapons Convention)の構想は,民間団体「核兵器に反対する法律家協会(IALANA)」,「核戦争防止国際医師の会(IPPNW)」,「拡散に反対する科学者国際ネットワーク(INESAP)」により発表され,1997年にコスタリカがモデル核兵器禁止条約として国連に提出した。2007年にはコスタリカ及びマレーシアが,2010年NPT運用検討会議第1回準備委員会に対し作業文書として同条約案の改訂版を提出し,また,国連にも提出した。同条約案は,核兵器の完全な禁止及び検証を伴う廃絶を規定したものであり,締約国の一般的義務として,(1)核兵器の開発,実験,生産,貯蔵,移譲,使用及び使用の威嚇の禁止,(2)核兵器国の核軍備(核兵器,核施設)廃棄,(3)核兵器に利用可能な核分裂性物質の生産禁止,(4)運搬手段の廃棄,(5)検証措置の実施を規定している。「核兵器条約」については,2008年に潘基文国連事務総長(当時)が,講演の中で発表した5項目の提案の1つとして,「強力な検証システムに裏付けられた核兵器条約の交渉が検討できる」と述べ,2010年NPT運用検討会議の最終文書で,「核兵器条約の交渉に関する検討を含む事務総長の5項目提案に留意する」 と言及している。
以下2の「核兵器禁止条約」と区別するために,核兵器国に対して核兵器を物理的に廃棄することを義務付け,それを検証する措置を備えることを定める「核兵器条約」は「包括的核兵器条約」とも呼ばれる。
なお,「核兵器条約」とは別に,その前段階として,核兵器の使用及び威嚇を禁止する「核兵器使用禁止条約」を交渉すべきとの考え方もあり,1996年第51回国連総会以降,インドが国連総会に対し,核兵器の使用又は使用の威嚇を禁止する国際協定締結のための交渉を開始することを要請する決議案を提出し,2021年にも採択されているが,核兵器使用禁止の要素は2021年1月に発効した核兵器禁止条約にも含まれている。
以下2の「核兵器禁止条約」と区別するために,核兵器国に対して核兵器を物理的に廃棄することを義務付け,それを検証する措置を備えることを定める「核兵器条約」は「包括的核兵器条約」とも呼ばれる。
なお,「核兵器条約」とは別に,その前段階として,核兵器の使用及び威嚇を禁止する「核兵器使用禁止条約」を交渉すべきとの考え方もあり,1996年第51回国連総会以降,インドが国連総会に対し,核兵器の使用又は使用の威嚇を禁止する国際協定締結のための交渉を開始することを要請する決議案を提出し,2021年にも採択されているが,核兵器使用禁止の要素は2021年1月に発効した核兵器禁止条約にも含まれている。
2 「核兵器禁止条約」をめぐる近年の動き
核兵器の非人道性に関する議論やこれに関する国際会議の結果,また,核軍縮の進展の遅さへの不満もあり,核兵器国が参加しない形であっても,核兵器の使用,開発,保有など核兵器に関するあらゆる側面を法的に先行して禁止する「核兵器禁止条約」を策定すべきとの主張が強まった。2015年NPT運用検討会議においては,法的条文を含めNPT第6条の「効果的措置」について議論するオープン・エンド作業部会(OEWG) の設置が議長の最終文書案に盛り込まれたものの,最終的には,中東問題が直接の原因となって同文書案は採択されなかった。このOEWGは,その後,同年10月からの第70回会期国連総会第一委員会において,メキシコが,核兵器のない世界を達成・維持するために締結される必要のある具体的かつ効果的な法的措置,法的条文及び規範を実質的に検討するためのOEWGを設置する「多国間核軍縮交渉前進」決議を提出,採択された。
同決議に基づいて,2016年2月~8月にジュネーブにおいて,OEWGが三回開催された。OEWGでは,核兵器のない世界に向けた具体的かつ効果的な法的措置,法的条文及び規範についての実質的議論が行われ,核兵器禁止条約の交渉開始を勧告する報告書が賛成多数で採択された(日本は,OEWGの議論に積極的に参加し,現実的かつ具体的な核軍縮措置としてFMCT,CTBT,透明性措置などを示し,これらは報告書に反映されたが,核兵器国の参加がなかった中で,核兵器禁止条約の交渉開始を勧告することは効果的な核軍縮措置とはいえないとして,報告書採択の際には棄権を投じた。なお,他の核兵器の抑止を認める国の多くも反対または棄権の立場を取った)。この報告書の採択を受けて,2016年10月からの第71回会期国連総会において,オーストリア,メキシコ,南アなどが,OEWG の報告書を歓迎しつつ,核兵器の廃絶につながる核兵器を禁止する法的拘束力のある文書の交渉会議を2017年にニューヨークで招集する「多国間核軍縮交渉前進」決議を提出,採択された。
同決議に基づいて,2017年3月,6月~7月に,核兵器禁止条約交渉会議が,コスタリカ議長の下で2回開催され,100以上の政府,市民社会が参加し,7月7日に核兵器禁止条約が採択された(122か国が賛成,オランダが反対,シンガポールが棄権。)。同条約は,第1条で,(a)核兵器その他の核爆発装置(以下「核兵器」という。)の開発,実験,生産,製造,取得,保有又は貯蔵,(b)核兵器又はその管理の直接的・間接的な移転,(c)核兵器又はその管理の直接的・間接的な受領,(d)核兵器の使用又は使用の威嚇,(e)この条約が禁止する活動に対する援助,奨励又は勧誘,(f)この条約が禁止する活動に対する援助の求め又は受入れ,(g)自国の領域又は管轄・管理下にある場所への核兵器の配備,設置又は展開の容認等を禁止することについて規定している。NPTとは異なり,同条約では一部の国に核兵器国としての地位を認めておらず,条約の義務は全締約国に適用される。同条の規定にかかわらず,核兵器を保有する国が核兵器を可及的速やかに破棄することが義務付けられている。同条約は,2017年9月20日に署名のため開放され,50か国の批准後90日で発効するとされており,2020年10月24日,50番目の締約国としてホンジュラスが同条約を締結したことを受け,2021年1月22日に発効した。同条約には2022年4月現在,86か国が署名,60か国が批准している。なお,日本は2017年3月の第1回核兵器禁止条約交渉会議ハイレベル・セグメントにおいて,核軍縮を進めるには核兵器使用の非人道性と安全保障の両方の認識に加えて,国際社会の対話と協力が不可欠だが,今回の交渉は核兵器国の協力を通じ,核廃絶に結びつく措置を追求する交渉のあり方が担保されていない旨表明し,それ以降の交渉には参加しなかった(核兵器国は参加せず,核抑止の下にある国の中ではオランダのみが参加した。)。
同決議に基づいて,2016年2月~8月にジュネーブにおいて,OEWGが三回開催された。OEWGでは,核兵器のない世界に向けた具体的かつ効果的な法的措置,法的条文及び規範についての実質的議論が行われ,核兵器禁止条約の交渉開始を勧告する報告書が賛成多数で採択された(日本は,OEWGの議論に積極的に参加し,現実的かつ具体的な核軍縮措置としてFMCT,CTBT,透明性措置などを示し,これらは報告書に反映されたが,核兵器国の参加がなかった中で,核兵器禁止条約の交渉開始を勧告することは効果的な核軍縮措置とはいえないとして,報告書採択の際には棄権を投じた。なお,他の核兵器の抑止を認める国の多くも反対または棄権の立場を取った)。この報告書の採択を受けて,2016年10月からの第71回会期国連総会において,オーストリア,メキシコ,南アなどが,OEWG の報告書を歓迎しつつ,核兵器の廃絶につながる核兵器を禁止する法的拘束力のある文書の交渉会議を2017年にニューヨークで招集する「多国間核軍縮交渉前進」決議を提出,採択された。
同決議に基づいて,2017年3月,6月~7月に,核兵器禁止条約交渉会議が,コスタリカ議長の下で2回開催され,100以上の政府,市民社会が参加し,7月7日に核兵器禁止条約が採択された(122か国が賛成,オランダが反対,シンガポールが棄権。)。同条約は,第1条で,(a)核兵器その他の核爆発装置(以下「核兵器」という。)の開発,実験,生産,製造,取得,保有又は貯蔵,(b)核兵器又はその管理の直接的・間接的な移転,(c)核兵器又はその管理の直接的・間接的な受領,(d)核兵器の使用又は使用の威嚇,(e)この条約が禁止する活動に対する援助,奨励又は勧誘,(f)この条約が禁止する活動に対する援助の求め又は受入れ,(g)自国の領域又は管轄・管理下にある場所への核兵器の配備,設置又は展開の容認等を禁止することについて規定している。NPTとは異なり,同条約では一部の国に核兵器国としての地位を認めておらず,条約の義務は全締約国に適用される。同条の規定にかかわらず,核兵器を保有する国が核兵器を可及的速やかに破棄することが義務付けられている。同条約は,2017年9月20日に署名のため開放され,50か国の批准後90日で発効するとされており,2020年10月24日,50番目の締約国としてホンジュラスが同条約を締結したことを受け,2021年1月22日に発効した。同条約には2022年4月現在,86か国が署名,60か国が批准している。なお,日本は2017年3月の第1回核兵器禁止条約交渉会議ハイレベル・セグメントにおいて,核軍縮を進めるには核兵器使用の非人道性と安全保障の両方の認識に加えて,国際社会の対話と協力が不可欠だが,今回の交渉は核兵器国の協力を通じ,核廃絶に結びつく措置を追求する交渉のあり方が担保されていない旨表明し,それ以降の交渉には参加しなかった(核兵器国は参加せず,核抑止の下にある国の中ではオランダのみが参加した。)。
3 「核兵器の威嚇又は使用の合法性」に関する国際司法裁判所(ICJ)勧告的意見
1993年,IALANA,IPPNW等が形成した「世界法廷プロジェクト」運動の結果,世界保健機関 (WHO)総会において,健康及び環境の見地から,核兵器の使用の合法性につきICJ勧告的意見を要請する決議が採択された。また,翌1994年,インドネシアが国連総会に,核兵器の使用の合法性につきICJ勧告的意見を要請する決議を提出し,採択された(多くの西側諸国が反対する中,日本は,唯一の戦争被爆国として,核兵器は二度と使われてはならないものの,本件が各国間の対立を助長することになりがちであるとして棄権した。)。
ICJはWHOの請求は却下したものの,1996年7月,国連総会からの要請に対して次のとおり勧告的意見を出した。「(中略)核兵器の威嚇又は使用は,武力紛争に適用される国際法の要件及び特に人道法の原則及び規則に一般的に違反することとなる。しかしながら,国際法の現状及び入手可能な事実関係に鑑み,裁判所は,国の生存そのものが問題となるような極限状況における核兵器の威嚇又は使用が合法か違法かを確定的に結論することはできない(賛成7-反対7,裁判長の決定票)」 としつつ,「厳格かつ効果的な国際管理の下におけるあらゆる側面での核軍縮を目指す交渉を誠実に行い,かつ妥結させる義務が存在する(全会一致)」とした。
このICJによる勧告的意見を受け,マレーシアは,1996年の第51 回総会以来現在に至るまで毎年,国連総会に対し,ICJ判事の全会一致の意見である核軍縮交渉を妥結する義務についてフォローアップを要請する「核兵器の威嚇又は使用の合法性に関するICJ勧告的意見フォローアップ」決議を提出し,2017年以降は,同決議の中で核兵器禁止条約の採択を歓迎し,同条約に基づくものも含めて核軍縮に向けた多国間交渉への関与を要請している。
なお,2014年4月には,マーシャル政府が核兵器を保有すると考えられる9か国・ 地域(米国,ロシア,英国,フランス,中国,インド,パキスタン,イスラエル及び北朝鮮)について, 核軍縮に向けた交渉を誠実に追求せず核戦力を増強しているのは,核兵器不拡散条約(NPT)第6条に明記されている核軍縮の(誠実交渉)義務及びそれに基づく国際慣習法に違反しているとして,国別にICJに提訴する動きも見られた。
核兵器禁止条約は、「核兵器のない世界」への出口とも言える重要な条約である。しかし、現実を変えるためには、核兵器国の協力が必要だが、同条約には核兵器国は1か国も参加していない。そのため、同条約の署名・批准といった対応よりも、日本は、唯一の戦争被爆国として、核兵器国を関与させるよう努力していかなければならず、そのためにも、まずは、「核兵器のない世界」の実現に向けて、唯一の同盟国である米国との信頼関係を基礎としつつ、現実的な取り組みを進めていく考えである。
ICJはWHOの請求は却下したものの,1996年7月,国連総会からの要請に対して次のとおり勧告的意見を出した。「(中略)核兵器の威嚇又は使用は,武力紛争に適用される国際法の要件及び特に人道法の原則及び規則に一般的に違反することとなる。しかしながら,国際法の現状及び入手可能な事実関係に鑑み,裁判所は,国の生存そのものが問題となるような極限状況における核兵器の威嚇又は使用が合法か違法かを確定的に結論することはできない(賛成7-反対7,裁判長の決定票)」 としつつ,「厳格かつ効果的な国際管理の下におけるあらゆる側面での核軍縮を目指す交渉を誠実に行い,かつ妥結させる義務が存在する(全会一致)」とした。
このICJによる勧告的意見を受け,マレーシアは,1996年の第51 回総会以来現在に至るまで毎年,国連総会に対し,ICJ判事の全会一致の意見である核軍縮交渉を妥結する義務についてフォローアップを要請する「核兵器の威嚇又は使用の合法性に関するICJ勧告的意見フォローアップ」決議を提出し,2017年以降は,同決議の中で核兵器禁止条約の採択を歓迎し,同条約に基づくものも含めて核軍縮に向けた多国間交渉への関与を要請している。
なお,2014年4月には,マーシャル政府が核兵器を保有すると考えられる9か国・ 地域(米国,ロシア,英国,フランス,中国,インド,パキスタン,イスラエル及び北朝鮮)について, 核軍縮に向けた交渉を誠実に追求せず核戦力を増強しているのは,核兵器不拡散条約(NPT)第6条に明記されている核軍縮の(誠実交渉)義務及びそれに基づく国際慣習法に違反しているとして,国別にICJに提訴する動きも見られた。
核兵器禁止条約は、「核兵器のない世界」への出口とも言える重要な条約である。しかし、現実を変えるためには、核兵器国の協力が必要だが、同条約には核兵器国は1か国も参加していない。そのため、同条約の署名・批准といった対応よりも、日本は、唯一の戦争被爆国として、核兵器国を関与させるよう努力していかなければならず、そのためにも、まずは、「核兵器のない世界」の実現に向けて、唯一の同盟国である米国との信頼関係を基礎としつつ、現実的な取り組みを進めていく考えである。