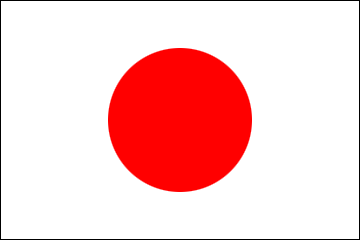軍縮会議日本政府代表部の取組(概観と2024年の展望)
令和6年1月23日
<当代表部の業務の概要>
ジュネーブには、「唯一の多数国間軍縮交渉機関」としての軍縮会議(1960年設立の「10か国軍縮委員会」を起源とし、1984年に「軍縮会議」と名称を変更)が設置されていることに加え、各種の軍備管理・軍縮関係の条約体の事務局が置かれ、関連の会議が開催されています。当代表部は、ジュネーブをベースとしたこれらの軍備管理・軍縮関係の条約体において、日本政府の立場を代表しています。また、ニューヨークで開催される国連総会第一委員会(軍縮問題及び関連の国際安全保障問題を担当)や核不拡散条約(NPT)運用検討会議プロセス(年によりウィーン、ジュネーブ又はニューヨークで開催)にも日本政府を代表して出席しています。
ロシアによるウクライナ侵略や我が国周辺における核・ミサイル戦力を含む軍備増強の急速な進展など、我が国は、第二次大戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しています。軍備管理・軍縮関係の多国間の枠組みを通じて、個々の兵器に着目しつつ、軍備面での国際的なルールを作りその履行を確保していくことは、我が国を取り巻く安全保障環境を改善し、国際社会の平和と安定を実現する上で重要な意義を有します。我が国は、唯一の戦争被爆国であるという歴史的使命感を持って、「核兵器のない世界」の実現に向けて、現実的な取組を進めています。
<「核兵器のない世界」に向けて>
2023年には、5月に広島で開催されたG7サミットにおいて、G7首脳は、核軍縮に焦点を当てたG7初の首脳独立文書である「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン 」を発出し、「核兵器のない世界」へのコミットメントを再確認しました。7~8月には次回NPT運用検討会議(2026年)に向けた第1回準備委員会がウィーンで開催され、NPTの新しい運用検討サイクルが開始しました。
10月には、日本は、核兵器廃絶決議案「核兵器のない世界に向けた共通のロードマップ構築のための取り組み 」を国連総会第一委員会に提出し、同決議は12月に国連総会で148票の賛成票を得て採択されました。この決議は、岸田総理が2022年8月のNPT運用検討会議で発表した「ヒロシマ・アクション・プラン」((1)核兵器不使用の継続性の重要性の共有、(2)透明性の向上、(3)核兵器数の減少傾向の維持、(4)核兵器の不拡散及び原子力の平和的利用、(5)各国指導者等による被爆地訪問の推進)を基礎にして、同運用検討会議及びG7広島サミットでの議論も踏まえて作成されたものです。同決議は、国際社会の核軍縮へ向けての機運を維持、強化する上で重要な役割を果たしてきていると考えます。
本年は7~8月に当地ジュネーブで、NPT第2回準備委員会が開催されます。当代表部では、広島・長崎の関係者の皆様と連携しつつ被爆の実相について国際社会の理解を深める活動を含め、核軍縮の進展のため積極的な取り組みを続けます。
<生物兵器の脅威>
新型コロナウイルスのパンデミックにより、バイオウイルスが国際社会および経済に及ぼす深刻な影響が再認識されました。生物兵器によっても同様の事態が引き起こされ得るところ、テロリスト等非国家主体によるその使用の懸念が強まっています。
2022年の生物兵器禁止条約第9回運用検討会議では、条約の強化を目指し、国際協力・支援、科学技術の進展、信頼醸成・透明性、遵守及び検証等の措置について検討するため、また、履行支援ユニットの組織的強化を図るための作業部会が設けられました。2023年から開始されたこれらの作業部会において、日本は特に組織・制度・財政事項の検討に議長フレンズとして貢献しています。本年は、昨年の作業部会での議論の成果を基に、条約の強化策を更に具体化、実体化していくための取組みを行っていきます。
<新たな技術が及ぼす安全保障上の影響への対応>
科学技術の高度な利用により、軍事・安全保障分野でも著しい進展が見られ、国際的な禁止・規制のための枠組みが、そのような進展に後れを取っている面も出てきています。人工知能(AI)技術の進歩が安全保障に及ぼす影響や、宇宙における様々な活動が及ぼし得る安全保障上の影響について、ルール作りのための議論が行われています。
ジュネーブにおいては、AI搭載兵器について、特定通常兵器使用禁止制限条約の下に、自律型致死兵器システム(LAWS)に関する政府専門家グループ(GGE)会合が設けられています。これまでのLAWS・GGEにおける議論の成果として、国際人道法がLAWSにも適用されること、国際人道法を遵守できないものは使用が禁止されること、また、兵器システムのライフサイクル全体を通じて、国際人道法を含む国際法の遵守を確保するため、必要に応じて標的の種類の制限を行うべきこと等につき合意が形成されています。 本年も引き続き、技術的、法的に掘り下げられた議論が続けられる予定です。
宇宙については、2022~23年にかけて、国連総会決議に基づき立ち上げられた、すべての国連加盟国に開かれた作業部会が4回開催され、宇宙における脅威を低減するための責任ある行動について具体的な議論が深められました。また、2023年11~12月には、同じく国連総会決議で立ち上げられた、宇宙空間における軍備競争の防止に関する政府専門家会合の第1回会合がジュネーブで開催されました。日本の専門家も同会合に参加しています。本年8月に第2回(最終)会合が開催される予定で、宇宙空間における軍備競争を防止するための法的拘束力のある文書の実質的な要素について議論が進められる予定です。
日本は、これらの高度な技術を有し、また、これらの高度な技術が不適切に使用されれば、その脅威にも最も曝され得る国の一つです。このような観点を踏まえ、日本は、これらのルール作りに具体的な提案を行い、積極的な参加を続けていきます。
<通常兵器への取り組み>
地雷や小型武器といった通常兵器は、戦争や内戦、更に犯罪等を通じて多数の被害者を出し続けています。更に、紛争終了後も、一般人を含めて無差別な被害をもたらすことにより、社会経済開発の大きな妨げとなっています。日本は、これらの通常兵器に関する国際的取組みにも積極的に貢献してきています。対人地雷禁止条約の下では、2021年から協力支援強化委員会委員を務めており、2025年には市川軍縮代大使が第22回締約国会議の議長を務めることが決まっています。本年は、カンボジアのシェムリアップで第5回運用検討会議が開催される予定であり、今後5年間の指針となる政治宣言や行動計画の採択が見込まれており、日本としても積極的に議論に参加していきます。
小型武器分野に関しては、日本はコロンビア及び南アフリカと共に、2001年以降、国連総会第一委員会に「小型武器非合法取引」決議案を提出しています。本年6月には、国連小型武器行動計画第4回運用検討会議が開催される予定であり、日本は上記決議の主提案国として、意義ある貢献をしていきます。
<展望>
現在の国際安全保障環境の下で、国際社会ではコンセンサス形成が一層困難となっており、ジュネーブでの議論も例外ではありません。特に、軍縮・軍備管理の分野では、各国の安全保障上の利害が直接にぶつかり合うこともあり、合意形成の困難さは深刻です。そのような状況であればこそ、対話や交渉、信頼醸成措置を通じた国際的なルール作りの重要性は益々高まっています。このような認識を共有する米国を初めとする同志国と連帯しつつ、多国間の交渉枠組みにおけるコンセンサスの形成と軍縮・軍備管理分野での具体的な成果を目指して、当代表部は今年も積極的に活動していきます。
ジュネーブには、「唯一の多数国間軍縮交渉機関」としての軍縮会議(1960年設立の「10か国軍縮委員会」を起源とし、1984年に「軍縮会議」と名称を変更)が設置されていることに加え、各種の軍備管理・軍縮関係の条約体の事務局が置かれ、関連の会議が開催されています。当代表部は、ジュネーブをベースとしたこれらの軍備管理・軍縮関係の条約体において、日本政府の立場を代表しています。また、ニューヨークで開催される国連総会第一委員会(軍縮問題及び関連の国際安全保障問題を担当)や核不拡散条約(NPT)運用検討会議プロセス(年によりウィーン、ジュネーブ又はニューヨークで開催)にも日本政府を代表して出席しています。
ロシアによるウクライナ侵略や我が国周辺における核・ミサイル戦力を含む軍備増強の急速な進展など、我が国は、第二次大戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しています。軍備管理・軍縮関係の多国間の枠組みを通じて、個々の兵器に着目しつつ、軍備面での国際的なルールを作りその履行を確保していくことは、我が国を取り巻く安全保障環境を改善し、国際社会の平和と安定を実現する上で重要な意義を有します。我が国は、唯一の戦争被爆国であるという歴史的使命感を持って、「核兵器のない世界」の実現に向けて、現実的な取組を進めています。
<「核兵器のない世界」に向けて>
2023年には、5月に広島で開催されたG7サミットにおいて、G7首脳は、核軍縮に焦点を当てたG7初の首脳独立文書である「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン 」を発出し、「核兵器のない世界」へのコミットメントを再確認しました。7~8月には次回NPT運用検討会議(2026年)に向けた第1回準備委員会がウィーンで開催され、NPTの新しい運用検討サイクルが開始しました。
10月には、日本は、核兵器廃絶決議案「核兵器のない世界に向けた共通のロードマップ構築のための取り組み 」を国連総会第一委員会に提出し、同決議は12月に国連総会で148票の賛成票を得て採択されました。この決議は、岸田総理が2022年8月のNPT運用検討会議で発表した「ヒロシマ・アクション・プラン」((1)核兵器不使用の継続性の重要性の共有、(2)透明性の向上、(3)核兵器数の減少傾向の維持、(4)核兵器の不拡散及び原子力の平和的利用、(5)各国指導者等による被爆地訪問の推進)を基礎にして、同運用検討会議及びG7広島サミットでの議論も踏まえて作成されたものです。同決議は、国際社会の核軍縮へ向けての機運を維持、強化する上で重要な役割を果たしてきていると考えます。
本年は7~8月に当地ジュネーブで、NPT第2回準備委員会が開催されます。当代表部では、広島・長崎の関係者の皆様と連携しつつ被爆の実相について国際社会の理解を深める活動を含め、核軍縮の進展のため積極的な取り組みを続けます。
<生物兵器の脅威>
新型コロナウイルスのパンデミックにより、バイオウイルスが国際社会および経済に及ぼす深刻な影響が再認識されました。生物兵器によっても同様の事態が引き起こされ得るところ、テロリスト等非国家主体によるその使用の懸念が強まっています。
2022年の生物兵器禁止条約第9回運用検討会議では、条約の強化を目指し、国際協力・支援、科学技術の進展、信頼醸成・透明性、遵守及び検証等の措置について検討するため、また、履行支援ユニットの組織的強化を図るための作業部会が設けられました。2023年から開始されたこれらの作業部会において、日本は特に組織・制度・財政事項の検討に議長フレンズとして貢献しています。本年は、昨年の作業部会での議論の成果を基に、条約の強化策を更に具体化、実体化していくための取組みを行っていきます。
<新たな技術が及ぼす安全保障上の影響への対応>
科学技術の高度な利用により、軍事・安全保障分野でも著しい進展が見られ、国際的な禁止・規制のための枠組みが、そのような進展に後れを取っている面も出てきています。人工知能(AI)技術の進歩が安全保障に及ぼす影響や、宇宙における様々な活動が及ぼし得る安全保障上の影響について、ルール作りのための議論が行われています。
ジュネーブにおいては、AI搭載兵器について、特定通常兵器使用禁止制限条約の下に、自律型致死兵器システム(LAWS)に関する政府専門家グループ(GGE)会合が設けられています。これまでのLAWS・GGEにおける議論の成果として、国際人道法がLAWSにも適用されること、国際人道法を遵守できないものは使用が禁止されること、また、兵器システムのライフサイクル全体を通じて、国際人道法を含む国際法の遵守を確保するため、必要に応じて標的の種類の制限を行うべきこと等につき合意が形成されています。 本年も引き続き、技術的、法的に掘り下げられた議論が続けられる予定です。
宇宙については、2022~23年にかけて、国連総会決議に基づき立ち上げられた、すべての国連加盟国に開かれた作業部会が4回開催され、宇宙における脅威を低減するための責任ある行動について具体的な議論が深められました。また、2023年11~12月には、同じく国連総会決議で立ち上げられた、宇宙空間における軍備競争の防止に関する政府専門家会合の第1回会合がジュネーブで開催されました。日本の専門家も同会合に参加しています。本年8月に第2回(最終)会合が開催される予定で、宇宙空間における軍備競争を防止するための法的拘束力のある文書の実質的な要素について議論が進められる予定です。
日本は、これらの高度な技術を有し、また、これらの高度な技術が不適切に使用されれば、その脅威にも最も曝され得る国の一つです。このような観点を踏まえ、日本は、これらのルール作りに具体的な提案を行い、積極的な参加を続けていきます。
<通常兵器への取り組み>
地雷や小型武器といった通常兵器は、戦争や内戦、更に犯罪等を通じて多数の被害者を出し続けています。更に、紛争終了後も、一般人を含めて無差別な被害をもたらすことにより、社会経済開発の大きな妨げとなっています。日本は、これらの通常兵器に関する国際的取組みにも積極的に貢献してきています。対人地雷禁止条約の下では、2021年から協力支援強化委員会委員を務めており、2025年には市川軍縮代大使が第22回締約国会議の議長を務めることが決まっています。本年は、カンボジアのシェムリアップで第5回運用検討会議が開催される予定であり、今後5年間の指針となる政治宣言や行動計画の採択が見込まれており、日本としても積極的に議論に参加していきます。
小型武器分野に関しては、日本はコロンビア及び南アフリカと共に、2001年以降、国連総会第一委員会に「小型武器非合法取引」決議案を提出しています。本年6月には、国連小型武器行動計画第4回運用検討会議が開催される予定であり、日本は上記決議の主提案国として、意義ある貢献をしていきます。
<展望>
現在の国際安全保障環境の下で、国際社会ではコンセンサス形成が一層困難となっており、ジュネーブでの議論も例外ではありません。特に、軍縮・軍備管理の分野では、各国の安全保障上の利害が直接にぶつかり合うこともあり、合意形成の困難さは深刻です。そのような状況であればこそ、対話や交渉、信頼醸成措置を通じた国際的なルール作りの重要性は益々高まっています。このような認識を共有する米国を初めとする同志国と連帯しつつ、多国間の交渉枠組みにおけるコンセンサスの形成と軍縮・軍備管理分野での具体的な成果を目指して、当代表部は今年も積極的に活動していきます。