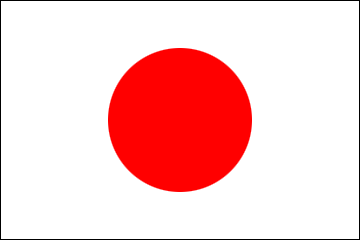核兵器不拡散条約(NPT)
令和5年5月19日
1 概要
核兵器不拡散条約(NPT:Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons)は、米国、ロシア、英国、フランス及び中国の5か国を「核兵器国」とし、それ以外の「非核兵器国」への核兵器の拡散を防止するとともに、誠実な核軍縮交渉を義務づけ、さらに、原子力の平和的利用のための協力を促進することを主たる目的とする条約である。NPTは、核軍縮、核不拡散、原子力の平和的利用という3つの柱(3本柱)で構成されていると一般的に言われている。NPTは、1968年7月に署名のために開放され、1970年3月に発効した(日本は1970年2月署名、1976年6月批准。)。締約国数は191か国・地域(北朝鮮を含む。2023年5月現在。インド、パキスタン、イスラエル及び南スーダンは未加入。)。
NPT第8条3項は、条約の前文の目的の実現及び条約の規定の遵守を確保するため、5年ごとに条約の運用を検討する会議(運用検討会議)を開催することを規定しており、1970年に発効して以来、その時々の国際情勢も反映した議論が展開されてきた。また、 NPT第10条2項には、発効の25年後にNPTを無期限又は一定期間存続させるかを決定することが明記されており、この規定に基づき、1995年に開催されたNPT運用検討・延長会議において、NPTの無期限延長の決定と共に、運用検討プロセス強化に関する決定、核不拡散及び核軍縮のための原則及び目標に関する決定及び中東決議が採択された。
1995年の運用検討プロセス強化に関する決定において、5年毎に開催される運用検討会議に先立つ3年間、毎年準備委員会を開催することが合意された。また、2000年の運用検討会議での運用検討プロセス強化に関する合意では、 各準備委員会の目的を明確化することが盛り込まれた。すなわち、第1回及び第2回の準備委員会は、1995年NPT運用検討・延長会議の決定及び中東決議に加え、1995年以降の運用検討会議の結果における具体的な実質事項を検討する。準備委員会の議長は、検討の内容を事実に即して要約し、さらなる議論に付すために次の準備委員会に送付する。第3回準備委員会は、それ以前の2回の準備委員会での議論を踏まえ、運用検討会議へのコンセンサスの勧告を含む報告書を作成する努力とともに、運用検討会議に関する手続事項について最終的にまとめることが求められる。
NPT第8条3項は、条約の前文の目的の実現及び条約の規定の遵守を確保するため、5年ごとに条約の運用を検討する会議(運用検討会議)を開催することを規定しており、1970年に発効して以来、その時々の国際情勢も反映した議論が展開されてきた。また、 NPT第10条2項には、発効の25年後にNPTを無期限又は一定期間存続させるかを決定することが明記されており、この規定に基づき、1995年に開催されたNPT運用検討・延長会議において、NPTの無期限延長の決定と共に、運用検討プロセス強化に関する決定、核不拡散及び核軍縮のための原則及び目標に関する決定及び中東決議が採択された。
1995年の運用検討プロセス強化に関する決定において、5年毎に開催される運用検討会議に先立つ3年間、毎年準備委員会を開催することが合意された。また、2000年の運用検討会議での運用検討プロセス強化に関する合意では、 各準備委員会の目的を明確化することが盛り込まれた。すなわち、第1回及び第2回の準備委員会は、1995年NPT運用検討・延長会議の決定及び中東決議に加え、1995年以降の運用検討会議の結果における具体的な実質事項を検討する。準備委員会の議長は、検討の内容を事実に即して要約し、さらなる議論に付すために次の準備委員会に送付する。第3回準備委員会は、それ以前の2回の準備委員会での議論を踏まえ、運用検討会議へのコンセンサスの勧告を含む報告書を作成する努力とともに、運用検討会議に関する手続事項について最終的にまとめることが求められる。
2 核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議
2-1 2000年・2005年・2010年・2015年NPT運用検討会議の概要
(1)第6回NPT運用検討会議(2000年)
2000年NPT運用検討会議では、核軍縮の停滞や1998年のインド、パキスタンの核実験といった厳しい状況下で、何度かの交渉決裂の危機を乗り越え、核兵器の全面的廃絶への核兵器国による「明確な約束」をはじめとする核軍縮に関する13の措置を含む最終文書が採択された。
(2)第7回NPT運用検討会議(2005年)
2005年NPT運用検討会議は、本来ならば準備委員会で決定されているべきである議題等の手続事項すら決定されていない中で行われ、その決定に会議日程の3分の2を要した結果、実質的議論や最終文書案の作成に十分な時間が割けず最終文書を採択できなかった。
(3)第8回NPT運用検討会議(2010年)
2010年NPT運用検討会議では、前回と同じ結果を繰り返さないため最終文書に合意すべきとの各国の強い意思や2009年4月のオバマ大統領のプラハ演説を契機とする核軍縮に向けた機運の高まりが見られる中で、米国・ロシアによる新戦略兵器削減条約(新START)署名や、米国、英国による核兵器保有数や削減規模に関する情報公開措置、インドネシアの包括的核実験禁止条約(CTBT)批准手続の開始表明等の具体的な動きが、会議の成功に向けて追い風となり、最終的に3本柱(核軍縮、核不拡散、原子力の平和的利用)全体を網羅する64項目の行動計画を含む最終文書が採択された。最終文書は、すべてのNPT締約国が協力して核軍縮・不拡散・原子力の平和的利用を推進していくための共通の基盤を提供するとともに、1995年の中東決議の実施に関する合意も含まれた。なお、中根猛ウィーン国際機関代表部大使(当時)は、主要委員会IIIの議長を務め、各国と意見調整を行いつつ、原子力の平和的利用に関する同議長の報告書案を作成し、最終文書の作成に貢献した。
(4)第9回NPT運用検討会議(2015年)
被爆70年の節目の年に当たる2015年のNPT運用検討会議は、核兵器国と非核兵器国の核軍縮をめぐる対立が深まり、加えて、2012年に開催されることで合意されていた中東非大量破壊兵器地帯に関する国際会議が開催されず、核兵器の非人道的影響等締約国の意見を収斂することが難しい課題が顕在化する中で開催された。議長には、フェルーキ・アルジェリア外務省顧問が選出され、議題等の手続事項は直ちに合意され、早い段階から実質的議論に入ることができた。しかし、同会議では、2010年運用検討会議で合意した行動計画の実施状況がレビューされ、非核兵器国の中からは、核軍縮分野のアクションの遅滞が見られるとの批判が表明された。
注目すべき動きとしては、以下が挙げられる。
ア 核軍縮分野では、核兵器の非人道的影響に関する議論が大きな盛り上がりを見せた。そのような中、NPT第6条に関する「効果的措置」の議論が核軍縮に関する議論の中心を占め、核兵器禁止条約の重要性を主張する国もあった。また、日本や軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)が提案した核兵器の透明性の向上や報告も論点となり、議長の最終文書案に反映された。なお、グループの活動が目立ち、新アジェンダ連合(NAC)やNPDIといったグループに加えて、人道グループが出現し、一定の発言力を持った。
イ 核不拡散については、保障措置、輸出管理、核セキュリティ、北朝鮮や中東を含む地域問題といった幅広い議題について議論が行われた。特に、核セキュリティについては、過去5年間の議論の進展が最終文書案に反映された。
ウ 原子力の平和的利用に関しては、途上国における原子力科学・技術へのアクセスの拡充及び平和的利用の促進に向けたIAEAの役割、東電福島第一原発事故の教訓の共有を含む原子力安全強化に向けた取組等について議論された。
また、締約国がNPTを脱退する場合の新たな規定についても議論が行われた。同運用検討会議の最終日前日に、各分野における合意案をベースに、フェルーキ議長が自らの責任の下で作成した最終文書案を配布し各国に対して最大限の柔軟性を発揮するよう求めたが、中東非大量破壊兵器地帯の書きぶりについて合意できず、会議最終日に、米国、英国及びカナダが議長最終案の当該部分に賛同できないとして、コンセンサスをブロックし、最終文書案が採択されないまま同運用検討会議は終了した。
2-2 第10回NPT運用検討会議プロセス(2022年)
前回の2015年の第9回NPT運用検討会議が最終文書に合意できなかったことを踏まえ、第10回NPT運用検討会議に向けてのプロセスは、その成功の必要性が共有される一方、国際的な安全保障環境が複雑化し、また、核軍縮の進め方についてのアプローチの違いが締約国間で顕在化する、という楽観を許さない状況の中で始まった。各準備委員会の概要は以下のとおり。
(1)第1回準備委員会
2020年に予定されていた第10回NPT運用検討会議に向けたプロセスの出発点として、2017年にウィーンで第1回準備委員会が開催された。同委員会では、3本柱(核軍縮・不拡散・原子力の平和的利用)それぞれの実質事項に関する議論が行われ、議長が、議長責任の下で議論の内容を総括した議長要約(サマリー)を公表した。日本からは、岸田文雄外務大臣(当時)が出席して一般討論演説を行った。また、日本も参加する軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)は、核戦力の透明性を含む6本の共同作業文書を提出するとともに、共同ステートメントを行った。
(2)第2回準備委員会
2018年にジュネーブで開催された第2回準備委員会でも、3本柱それぞれについて議論が行われた。
日本は、河野太郎外務大臣(当時)が出席して一般討論演説を行うとともに、2017年11月と2018年3月に実施した「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」(以下4参照)の提言を同委員会に提出した。また、NPDIとしては、透明性を始めとする4本の作業文書を提出し、透明性強化によるNPT検証プロセスの強化についてのサイドイベントを実施した。
なお、第2回準備委員会でも第1回準備委員会と同様、議長要約(サマリー)が公表された。
(3)第3回準備委員会
第3回準備委員会は、2020年に予定されていた第10回NPT運用検討会議に向けた最後の準備委員会として、2019年にニューヨークで開催された。同準備委員会では、グロッシー・アルゼンチン・ウィーン代表部大使(現国際原子力機関(IAEA)事務局長)の2020年NPT運用検討会議議長への指名の確定や議題等が合意され、3本柱についての実質的議論が行われた。核軍縮分野については、第1回及び第2回準備委員会と同様の議論が行われた一方で、5核兵器国(米、英、仏、中、露)からは、共同ステートメントの発出、英国及び中国による国別履行報告の提出、米国による「核軍縮のための環境創出(CEND)」イニシアティブの説明等の動きがあった。また、ヴァルストロム・スウェーデン外相(当時)が、核軍縮のための新しい取組としてステッピング・ストーン・アプローチを提唱した。また、フランスが北朝鮮の核問題についての共同ステートメント(日本を含む70か国が参加)を主導し、米国等がシリア問題についてIAEA保障措置協定不遵守に関する共同ステートメントを行った。
これらの実質的議論に基づいて、第3回準備委員会の議長(サイエド・ハスリン・マレーシア国連代表部大使)は、第10回NPT運用検討会議への勧告案を作成し、同案についての議論が行われたが、とりわけ核軍縮分野での記述について意見の対立が見られ、最終的に勧告案は合意に至らなかった。
日本は、辻清人外務大臣政務官(当時)が出席して一般討論演説を行うとともに、2020年NPT運用検討会議の意義ある成果に向けて具体的な提案を行うための「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」の成果である「京都アピール」を披露するとともに、55か国の賛同国を代表して軍縮・不拡散教育に関する共同ステートメントを実施した。日本を含むNPDIとしては、透明性や軍縮・不拡散教育を含む5本の作業文書を提出した。
2-3 第10回NPT運用検討会議
2020年NPT運用検討会議議長として指名されることが確実となっていたグロッシー・アルゼンチン・ウィーン代表部大使は、天野之弥IAEA事務局長の逝去に伴って行われたIAEA事務局長選挙に立候補し、2019年12月にIAEA事務局長に就任した。これにより、NPT運用検討会議予定議長のポストを維持することが困難となり、同じアルゼンチンのスラウビネン筆頭外務副大臣(当時)が、 2020年1月にNPT運用検討会議予定議長として全締約国に承認された。
当初2020年4月から5月にかけて予定されていた第10回NPT運用検討会議は、新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延を受け、延期を繰り返した後、2022年8月に開催されることとなった。
8月1日から26日まで、米国ニューヨークの国連本部において行われた会議は、従来からの核軍縮のアプローチをめぐる分断に加え、ロシアによるウクライナ侵略など厳しい状況を受けて、最終的にコンセンサスで単一の包括的文書を採択することは非常に厳しいとの見通しの中での開催となった。会議冒頭でスラウビネン議長が正式に選出され、議題等の手続事項も直ちに合意され、早い段階から実質的議論に入ることができた。日本からは、小笠原一郎軍縮会議日本政府代表部大使が副議長に選出された。
第1週は、各国の一般討論演説により、会議全体のトーンセッティングが行われ、日本からは、岸田文雄総理大臣が日本の総理として初めてNPT運用検討会議に出席して演説を行い、(1)核兵器不使用の継続の重要性の共有、(2)透明性の向上、(3)核兵器数の減少傾向の維持、(4)核兵器の不拡散及び原子力の平和的利用、(5)各国指導者等による被爆地訪問の促進、の5つの行動を基礎とする「ヒロシマ・アクション・プラン」を発表した。
第2週は、NPTの3つの「柱」(核軍縮、核不拡散、原子力の平和的利用)ごとの協議体(主要委員会、補助機関)に分かれて議論が行われた。主要委員会Iでは、小笠原一郎軍縮会議日本政府代表部大使が、88か国・地域を代表して、軍縮・不拡散教育共同ステートメントを行った。
第3週は、第1の柱(核軍縮)については核軍縮交渉義務、軍縮と安全保障環境の関係、同盟国の責務、消極的安全保証(NSA)、先行不使用(NFU: No First Use)、兵器級核分裂性物質の生産モラトリアム、透明性の向上・報告事項の精緻化、核兵器禁止条約及び軍縮・不拡散教育等に関し、第2の柱(不拡散)についてはイラン、北朝鮮、中東非大量破壊兵器地帯、AUKUS及びザポリッジャ原発への保障措置活動等に関し、また、第3の柱(原子力の平和的利用)については、ザポリッジャ原発の安全性を含む原子力安全等に関して文言交渉が行われたが、多くの争点を残したまま第3週の議論を終了した。そのため、状況を打開すべく、週末から、非公式の少数国会合が開催された。日本は、国際的な核軍縮・不拡散体制の礎石であるNPTを重視し、NPT体制を維持・強化する観点から各国の建設的な対応を繰り返し呼びかけつつ、協議・交渉にあたった。
第4週(最終週)は、非公式会合や関係国間の協議が断続的に行われ、対立点についての重点的な議論を実施し、残る対立点を巡る関係国の立場を踏まえ、スラウビネン議長より、最終成果文書案が提示された。そして迎えた26日午後3時の最後の公式本会議の直前に、ロシア代表団が最終成果文書案には合意できないと表明したため、同文書案については最終的にコンセンサスは成立しなかったが、次回の運用検討会議の時期(2026年)やそれに向けた会議プロセス、さらに、運用検討プロセス強化に向けた作業部会の設置や手続事項は合意され、会議を終了した。
2-4 第10回NPT運用検討会議の具体的成果に向けた日本の取組
ア「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」及び「核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会合」
日本は、2017年の第1回準備委員会において、岸田文雄外務大臣(当時)が、様々なアプローチを有する国々の信頼関係を再構築し、核軍縮の実質的な進展に資する提言を得ることを目的とし、日本人有識者7名に加えて、核兵器国、中道国、核兵器禁止条約推進国の外国人有識者10名の合計17名で構成される「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」の立ち上げを表明した。同会議は、第2回及び第3回準備委員会に成果物を提出し、2019年10月には5回の会合の内容をまとめた議長レポートを発出した。その後、我が国は、核兵器国と非核兵器国を含む各国の政府関係者及び民間有識者の参加を得て、「核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会合」を立ち上げた。同会合は、2020年3月に第1回会合を開催し、国際社会として直ちに取り組むべき核軍縮措置として、透明性、核リスク低減及び軍縮・不拡散教育についての議論を行った。その後、 2021年3月には第2回会合を開催し、次回NPT運用検討会議において意義ある成果を達成するための方策について議論を行った。更に2021年12月に開催した第3回会合には、岸田文雄総理大臣が参加し、NPTの3本柱(軍縮・不拡散・平和的利用)のバランスの取れた成果、NPT第6条に基づく核軍縮分野における前進などについて、議論が行われた。この他、2021年12月には、第10回NPT運用検討会議に向けて、核軍縮の実質的な進展のための賢人会議に焦点を当てた作業文書を提出した。
イ 日本提出の核兵器廃絶国連総会決議
我が国は、1994年以降、毎年、核兵器廃絶に向けた決議案を国連総会第一委員会に提出してきている。2019年、2020年及び2021年に提出した決議案「核兵器のない世界に向けた共同行動の指針と未来志向の対話」においては、国際社会が核軍縮において直ちに取り組むべき共同行動の指針として、(1)透明性、(2)核リスク低減、(3)核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)、(4)包括的核実験禁止条約(CTBT)、(5)核軍縮検証、(6)軍縮不拡散教育に焦点を当て、第10回NPT運用検討会議の成果文書の材料となり得るコモン・グラウンド文言の提示に努めた他、今後の長期的課題として未来志向の対話の重要性が強調されている。2021年12月6日、同決議案は、57か国の共同提案国を得て、国連総会において採択された(158票の賛成、4票の反対、27票の棄権)。
ウ 軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)の活動
また、日本は、地域横断的なNPDIのメンバーとして、2010年の設立以降、準備委員会やNPT運用検討会議で具体的な提案を行ってきている。NPDIは2019年11月、名古屋において、茂木敏充外務大臣が議長を務め、外相会合を開催し、共同声明を発出した。また、NPDIは、 3回の準備委員会で提出したこれまでの作業文書を踏まえつつ、第10回NPT運用検討会議における最終文書案の要素、つまり、NPTの3本柱を維持・強化するための具体的な指針を提示するための作業文書を提出した。また、NPDIは、第10回NPT運用検討会議初日に第11回NPDIハイレベル会合を開催し、共同声明を発出した。同会合には岸田文雄総理大臣が出席し、核兵器の透明性の向上を始めとするNPDIの現実的・実践的な取組の更なる推進・強化を呼びかけた。
エ ストックホルム・イニシアティブの活動
2019年NPT第3回準備委員会においてスウェーデンが提唱したステッピング・ストーン・アプローチに基づき、 2019年6月、ストックホルムで核軍縮及びNPTに関する閣僚会合が開催された。同会合には、異なる地域から非核兵器国16か国(アルゼンチン、カナダ、フィンランド、エチオピア、ドイツ、インドネシア、ヨルダン、日本、カザフスタン、オランダ、ノルウェー、NZ、韓国、スペイン及びスウェーデン)が参加し、我が国からは河野太郎外務大臣(当時)が出席した。同会合は、第10回NPT運用検討会議で見出し得る共通の基盤を示唆する閣僚宣言を発出した。2020年2月、ベルリンで第2回閣僚会合を開催し、核軍縮の進展及びNPT体制の強化に向けた議論を行って閣僚宣言及び附属文書を採択した。日本からは小笠原一郎軍縮会議日本政府代表部大使が出席した。2021年1月及び7月には、第3回及び第4回閣僚会合が開催され、日本から鷲尾英一郎外務副大臣(当時)が参加した。更に2021年12月には、日本から小田原潔外務副大臣参加の下、第5回閣僚会合が開催され、NPT運用検討会議に向けた見通しや各国の取組等について議論が行われた。(2023年5月更新)
【参考】第10回NPT運用検討会議における日本のステートメント
2022年8月1日の岸田総理大臣による一般討論演説(日本語(PDF) /英語(PDF))
2022年8月22日の核兵器不拡散条約(NPT)本会議での武井外務副大臣によるステートメント
2022年8月12日の核兵器不拡散条約(NPT)主要委員会Iにおける小笠原大使ステートメント
2022年8月10日の核兵器不拡散条約(NPT)主要委員会Iにおける小笠原大使ステートメント
2022年8月5日の核兵器不拡散条約(NPT)主要委員会Iにおける軍縮不拡散教育に関する小笠原大使ステートメント
2022年8月5日の核兵器不拡散条約(NPT)主要委員会Iにおける小笠原大使ステートメント
(1)第6回NPT運用検討会議(2000年)
2000年NPT運用検討会議では、核軍縮の停滞や1998年のインド、パキスタンの核実験といった厳しい状況下で、何度かの交渉決裂の危機を乗り越え、核兵器の全面的廃絶への核兵器国による「明確な約束」をはじめとする核軍縮に関する13の措置を含む最終文書が採択された。
(2)第7回NPT運用検討会議(2005年)
2005年NPT運用検討会議は、本来ならば準備委員会で決定されているべきである議題等の手続事項すら決定されていない中で行われ、その決定に会議日程の3分の2を要した結果、実質的議論や最終文書案の作成に十分な時間が割けず最終文書を採択できなかった。
(3)第8回NPT運用検討会議(2010年)
2010年NPT運用検討会議では、前回と同じ結果を繰り返さないため最終文書に合意すべきとの各国の強い意思や2009年4月のオバマ大統領のプラハ演説を契機とする核軍縮に向けた機運の高まりが見られる中で、米国・ロシアによる新戦略兵器削減条約(新START)署名や、米国、英国による核兵器保有数や削減規模に関する情報公開措置、インドネシアの包括的核実験禁止条約(CTBT)批准手続の開始表明等の具体的な動きが、会議の成功に向けて追い風となり、最終的に3本柱(核軍縮、核不拡散、原子力の平和的利用)全体を網羅する64項目の行動計画を含む最終文書が採択された。最終文書は、すべてのNPT締約国が協力して核軍縮・不拡散・原子力の平和的利用を推進していくための共通の基盤を提供するとともに、1995年の中東決議の実施に関する合意も含まれた。なお、中根猛ウィーン国際機関代表部大使(当時)は、主要委員会IIIの議長を務め、各国と意見調整を行いつつ、原子力の平和的利用に関する同議長の報告書案を作成し、最終文書の作成に貢献した。
(4)第9回NPT運用検討会議(2015年)
被爆70年の節目の年に当たる2015年のNPT運用検討会議は、核兵器国と非核兵器国の核軍縮をめぐる対立が深まり、加えて、2012年に開催されることで合意されていた中東非大量破壊兵器地帯に関する国際会議が開催されず、核兵器の非人道的影響等締約国の意見を収斂することが難しい課題が顕在化する中で開催された。議長には、フェルーキ・アルジェリア外務省顧問が選出され、議題等の手続事項は直ちに合意され、早い段階から実質的議論に入ることができた。しかし、同会議では、2010年運用検討会議で合意した行動計画の実施状況がレビューされ、非核兵器国の中からは、核軍縮分野のアクションの遅滞が見られるとの批判が表明された。
注目すべき動きとしては、以下が挙げられる。
ア 核軍縮分野では、核兵器の非人道的影響に関する議論が大きな盛り上がりを見せた。そのような中、NPT第6条に関する「効果的措置」の議論が核軍縮に関する議論の中心を占め、核兵器禁止条約の重要性を主張する国もあった。また、日本や軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)が提案した核兵器の透明性の向上や報告も論点となり、議長の最終文書案に反映された。なお、グループの活動が目立ち、新アジェンダ連合(NAC)やNPDIといったグループに加えて、人道グループが出現し、一定の発言力を持った。
イ 核不拡散については、保障措置、輸出管理、核セキュリティ、北朝鮮や中東を含む地域問題といった幅広い議題について議論が行われた。特に、核セキュリティについては、過去5年間の議論の進展が最終文書案に反映された。
ウ 原子力の平和的利用に関しては、途上国における原子力科学・技術へのアクセスの拡充及び平和的利用の促進に向けたIAEAの役割、東電福島第一原発事故の教訓の共有を含む原子力安全強化に向けた取組等について議論された。
また、締約国がNPTを脱退する場合の新たな規定についても議論が行われた。同運用検討会議の最終日前日に、各分野における合意案をベースに、フェルーキ議長が自らの責任の下で作成した最終文書案を配布し各国に対して最大限の柔軟性を発揮するよう求めたが、中東非大量破壊兵器地帯の書きぶりについて合意できず、会議最終日に、米国、英国及びカナダが議長最終案の当該部分に賛同できないとして、コンセンサスをブロックし、最終文書案が採択されないまま同運用検討会議は終了した。
2-2 第10回NPT運用検討会議プロセス(2022年)
前回の2015年の第9回NPT運用検討会議が最終文書に合意できなかったことを踏まえ、第10回NPT運用検討会議に向けてのプロセスは、その成功の必要性が共有される一方、国際的な安全保障環境が複雑化し、また、核軍縮の進め方についてのアプローチの違いが締約国間で顕在化する、という楽観を許さない状況の中で始まった。各準備委員会の概要は以下のとおり。
(1)第1回準備委員会
2020年に予定されていた第10回NPT運用検討会議に向けたプロセスの出発点として、2017年にウィーンで第1回準備委員会が開催された。同委員会では、3本柱(核軍縮・不拡散・原子力の平和的利用)それぞれの実質事項に関する議論が行われ、議長が、議長責任の下で議論の内容を総括した議長要約(サマリー)を公表した。日本からは、岸田文雄外務大臣(当時)が出席して一般討論演説を行った。また、日本も参加する軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)は、核戦力の透明性を含む6本の共同作業文書を提出するとともに、共同ステートメントを行った。
(2)第2回準備委員会
2018年にジュネーブで開催された第2回準備委員会でも、3本柱それぞれについて議論が行われた。
日本は、河野太郎外務大臣(当時)が出席して一般討論演説を行うとともに、2017年11月と2018年3月に実施した「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」(以下4参照)の提言を同委員会に提出した。また、NPDIとしては、透明性を始めとする4本の作業文書を提出し、透明性強化によるNPT検証プロセスの強化についてのサイドイベントを実施した。
なお、第2回準備委員会でも第1回準備委員会と同様、議長要約(サマリー)が公表された。
(3)第3回準備委員会
第3回準備委員会は、2020年に予定されていた第10回NPT運用検討会議に向けた最後の準備委員会として、2019年にニューヨークで開催された。同準備委員会では、グロッシー・アルゼンチン・ウィーン代表部大使(現国際原子力機関(IAEA)事務局長)の2020年NPT運用検討会議議長への指名の確定や議題等が合意され、3本柱についての実質的議論が行われた。核軍縮分野については、第1回及び第2回準備委員会と同様の議論が行われた一方で、5核兵器国(米、英、仏、中、露)からは、共同ステートメントの発出、英国及び中国による国別履行報告の提出、米国による「核軍縮のための環境創出(CEND)」イニシアティブの説明等の動きがあった。また、ヴァルストロム・スウェーデン外相(当時)が、核軍縮のための新しい取組としてステッピング・ストーン・アプローチを提唱した。また、フランスが北朝鮮の核問題についての共同ステートメント(日本を含む70か国が参加)を主導し、米国等がシリア問題についてIAEA保障措置協定不遵守に関する共同ステートメントを行った。
これらの実質的議論に基づいて、第3回準備委員会の議長(サイエド・ハスリン・マレーシア国連代表部大使)は、第10回NPT運用検討会議への勧告案を作成し、同案についての議論が行われたが、とりわけ核軍縮分野での記述について意見の対立が見られ、最終的に勧告案は合意に至らなかった。
日本は、辻清人外務大臣政務官(当時)が出席して一般討論演説を行うとともに、2020年NPT運用検討会議の意義ある成果に向けて具体的な提案を行うための「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」の成果である「京都アピール」を披露するとともに、55か国の賛同国を代表して軍縮・不拡散教育に関する共同ステートメントを実施した。日本を含むNPDIとしては、透明性や軍縮・不拡散教育を含む5本の作業文書を提出した。
2-3 第10回NPT運用検討会議
2020年NPT運用検討会議議長として指名されることが確実となっていたグロッシー・アルゼンチン・ウィーン代表部大使は、天野之弥IAEA事務局長の逝去に伴って行われたIAEA事務局長選挙に立候補し、2019年12月にIAEA事務局長に就任した。これにより、NPT運用検討会議予定議長のポストを維持することが困難となり、同じアルゼンチンのスラウビネン筆頭外務副大臣(当時)が、 2020年1月にNPT運用検討会議予定議長として全締約国に承認された。
当初2020年4月から5月にかけて予定されていた第10回NPT運用検討会議は、新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延を受け、延期を繰り返した後、2022年8月に開催されることとなった。
8月1日から26日まで、米国ニューヨークの国連本部において行われた会議は、従来からの核軍縮のアプローチをめぐる分断に加え、ロシアによるウクライナ侵略など厳しい状況を受けて、最終的にコンセンサスで単一の包括的文書を採択することは非常に厳しいとの見通しの中での開催となった。会議冒頭でスラウビネン議長が正式に選出され、議題等の手続事項も直ちに合意され、早い段階から実質的議論に入ることができた。日本からは、小笠原一郎軍縮会議日本政府代表部大使が副議長に選出された。
第1週は、各国の一般討論演説により、会議全体のトーンセッティングが行われ、日本からは、岸田文雄総理大臣が日本の総理として初めてNPT運用検討会議に出席して演説を行い、(1)核兵器不使用の継続の重要性の共有、(2)透明性の向上、(3)核兵器数の減少傾向の維持、(4)核兵器の不拡散及び原子力の平和的利用、(5)各国指導者等による被爆地訪問の促進、の5つの行動を基礎とする「ヒロシマ・アクション・プラン」を発表した。
第2週は、NPTの3つの「柱」(核軍縮、核不拡散、原子力の平和的利用)ごとの協議体(主要委員会、補助機関)に分かれて議論が行われた。主要委員会Iでは、小笠原一郎軍縮会議日本政府代表部大使が、88か国・地域を代表して、軍縮・不拡散教育共同ステートメントを行った。
第3週は、第1の柱(核軍縮)については核軍縮交渉義務、軍縮と安全保障環境の関係、同盟国の責務、消極的安全保証(NSA)、先行不使用(NFU: No First Use)、兵器級核分裂性物質の生産モラトリアム、透明性の向上・報告事項の精緻化、核兵器禁止条約及び軍縮・不拡散教育等に関し、第2の柱(不拡散)についてはイラン、北朝鮮、中東非大量破壊兵器地帯、AUKUS及びザポリッジャ原発への保障措置活動等に関し、また、第3の柱(原子力の平和的利用)については、ザポリッジャ原発の安全性を含む原子力安全等に関して文言交渉が行われたが、多くの争点を残したまま第3週の議論を終了した。そのため、状況を打開すべく、週末から、非公式の少数国会合が開催された。日本は、国際的な核軍縮・不拡散体制の礎石であるNPTを重視し、NPT体制を維持・強化する観点から各国の建設的な対応を繰り返し呼びかけつつ、協議・交渉にあたった。
第4週(最終週)は、非公式会合や関係国間の協議が断続的に行われ、対立点についての重点的な議論を実施し、残る対立点を巡る関係国の立場を踏まえ、スラウビネン議長より、最終成果文書案が提示された。そして迎えた26日午後3時の最後の公式本会議の直前に、ロシア代表団が最終成果文書案には合意できないと表明したため、同文書案については最終的にコンセンサスは成立しなかったが、次回の運用検討会議の時期(2026年)やそれに向けた会議プロセス、さらに、運用検討プロセス強化に向けた作業部会の設置や手続事項は合意され、会議を終了した。
2-4 第10回NPT運用検討会議の具体的成果に向けた日本の取組
ア「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」及び「核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会合」
日本は、2017年の第1回準備委員会において、岸田文雄外務大臣(当時)が、様々なアプローチを有する国々の信頼関係を再構築し、核軍縮の実質的な進展に資する提言を得ることを目的とし、日本人有識者7名に加えて、核兵器国、中道国、核兵器禁止条約推進国の外国人有識者10名の合計17名で構成される「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」の立ち上げを表明した。同会議は、第2回及び第3回準備委員会に成果物を提出し、2019年10月には5回の会合の内容をまとめた議長レポートを発出した。その後、我が国は、核兵器国と非核兵器国を含む各国の政府関係者及び民間有識者の参加を得て、「核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会合」を立ち上げた。同会合は、2020年3月に第1回会合を開催し、国際社会として直ちに取り組むべき核軍縮措置として、透明性、核リスク低減及び軍縮・不拡散教育についての議論を行った。その後、 2021年3月には第2回会合を開催し、次回NPT運用検討会議において意義ある成果を達成するための方策について議論を行った。更に2021年12月に開催した第3回会合には、岸田文雄総理大臣が参加し、NPTの3本柱(軍縮・不拡散・平和的利用)のバランスの取れた成果、NPT第6条に基づく核軍縮分野における前進などについて、議論が行われた。この他、2021年12月には、第10回NPT運用検討会議に向けて、核軍縮の実質的な進展のための賢人会議に焦点を当てた作業文書を提出した。
イ 日本提出の核兵器廃絶国連総会決議
我が国は、1994年以降、毎年、核兵器廃絶に向けた決議案を国連総会第一委員会に提出してきている。2019年、2020年及び2021年に提出した決議案「核兵器のない世界に向けた共同行動の指針と未来志向の対話」においては、国際社会が核軍縮において直ちに取り組むべき共同行動の指針として、(1)透明性、(2)核リスク低減、(3)核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)、(4)包括的核実験禁止条約(CTBT)、(5)核軍縮検証、(6)軍縮不拡散教育に焦点を当て、第10回NPT運用検討会議の成果文書の材料となり得るコモン・グラウンド文言の提示に努めた他、今後の長期的課題として未来志向の対話の重要性が強調されている。2021年12月6日、同決議案は、57か国の共同提案国を得て、国連総会において採択された(158票の賛成、4票の反対、27票の棄権)。
ウ 軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)の活動
また、日本は、地域横断的なNPDIのメンバーとして、2010年の設立以降、準備委員会やNPT運用検討会議で具体的な提案を行ってきている。NPDIは2019年11月、名古屋において、茂木敏充外務大臣が議長を務め、外相会合を開催し、共同声明を発出した。また、NPDIは、 3回の準備委員会で提出したこれまでの作業文書を踏まえつつ、第10回NPT運用検討会議における最終文書案の要素、つまり、NPTの3本柱を維持・強化するための具体的な指針を提示するための作業文書を提出した。また、NPDIは、第10回NPT運用検討会議初日に第11回NPDIハイレベル会合を開催し、共同声明を発出した。同会合には岸田文雄総理大臣が出席し、核兵器の透明性の向上を始めとするNPDIの現実的・実践的な取組の更なる推進・強化を呼びかけた。
エ ストックホルム・イニシアティブの活動
2019年NPT第3回準備委員会においてスウェーデンが提唱したステッピング・ストーン・アプローチに基づき、 2019年6月、ストックホルムで核軍縮及びNPTに関する閣僚会合が開催された。同会合には、異なる地域から非核兵器国16か国(アルゼンチン、カナダ、フィンランド、エチオピア、ドイツ、インドネシア、ヨルダン、日本、カザフスタン、オランダ、ノルウェー、NZ、韓国、スペイン及びスウェーデン)が参加し、我が国からは河野太郎外務大臣(当時)が出席した。同会合は、第10回NPT運用検討会議で見出し得る共通の基盤を示唆する閣僚宣言を発出した。2020年2月、ベルリンで第2回閣僚会合を開催し、核軍縮の進展及びNPT体制の強化に向けた議論を行って閣僚宣言及び附属文書を採択した。日本からは小笠原一郎軍縮会議日本政府代表部大使が出席した。2021年1月及び7月には、第3回及び第4回閣僚会合が開催され、日本から鷲尾英一郎外務副大臣(当時)が参加した。更に2021年12月には、日本から小田原潔外務副大臣参加の下、第5回閣僚会合が開催され、NPT運用検討会議に向けた見通しや各国の取組等について議論が行われた。(2023年5月更新)
【参考】第10回NPT運用検討会議における日本のステートメント
2022年8月1日の岸田総理大臣による一般討論演説(日本語(PDF) /英語(PDF))
2022年8月22日の核兵器不拡散条約(NPT)本会議での武井外務副大臣によるステートメント
2022年8月12日の核兵器不拡散条約(NPT)主要委員会Iにおける小笠原大使ステートメント
2022年8月10日の核兵器不拡散条約(NPT)主要委員会Iにおける小笠原大使ステートメント
2022年8月5日の核兵器不拡散条約(NPT)主要委員会Iにおける軍縮不拡散教育に関する小笠原大使ステートメント
2022年8月5日の核兵器不拡散条約(NPT)主要委員会Iにおける小笠原大使ステートメント