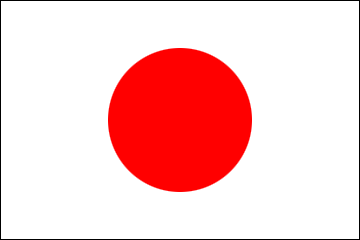軍縮・不拡散とジェンダー
令和7年6月19日
【概要】
ジェンダー全般についてはこちら。女性・平和・安全保障(Women, Peace and Security : WPS)に関する安保理決議と行動計画の概要についてはこちら。
ジェンダー主流化についての議論は軍縮・不拡散の文脈でも活発化してきた。2018年5月にグテーレス国連事務総長が発表した軍縮アジェンダでは「軍縮と国際安全保障に関する意思決定プロセスにおける女性の完全かつ平等な参加」が呼びかけられた。その行動計画において、40あるアクションのうち2つが「平等、完全かつ効果的な女性の参画の確保」に充てられ、その実施のために、(1)国連が開催する会議や国連関連組織への男女平等な参画に向けた取組、(2)一方の性別のみが出席する委員会や行事への国連軍縮部の不参加又は問題提起、(3)軍縮関連会議への出席者の男女別データの集計・公表、(4)国連軍縮部及び地域センターによる女性の有意義な参加を促す能力構築支援事業の履行、(5)国連軍縮研究所によるジェンダーと軍縮に関する情報発信が掲げられた。
なお、2014年に発効した武器貿易条約は、第7条4項において、締約国は通常兵器の輸出許可に際し、輸出する兵器が「ジェンダーに基づく重大な暴力行為又は女性及び児童に対する重大な暴力行為を行い、又は助長するために使用される危険性を考慮する」ことを定めている。これは、武器の輸出を検討する際に、ジェンダーに基づく重大な暴力に繋がるリスクがないかを検討することを明記した最初の国際条約である。
【活動の状況】
日本は、軍縮・不拡散を含む平和・安全保障分野において、ジェンダー主流化に努めている。全ての関係当事者に対し、女性の参画を拡大し、国連の平和・安全保障活動のあらゆる面においてジェンダーの視点を採用するよう要請するWPSに関する国連安保理決議第1325号(2000年)の履行を支持し、WPSに関する行動計画を2015年に策定し、2019年に第2次行動計画、2023年に第3次行動計画を策定した。
さらに日本は、国連総会第一委員会や対人地雷禁止条約等の各種条約体の関連会合においてジェンダー共同ステートメントに参画し、国連における各種政府専門家会合に女性専門家を積極的に派遣するなど、ジェンダー主流化に取り組んでいる。我が国が毎年国連総会に提出している核兵器廃絶決議においても、2018年以降、軍縮不拡散分野におけるジェンダーの視点の重要性に言及している。
また、市川軍縮代大使は、2024年3月に、ジェンダー平等の促進に取り組むインターナショナル・ジェンダー・チャンピオンに就任した(市川大使が表明したコミットメント(S.M.A.R.T. Commitments)はこちら。
2025年、日本は、対人地雷禁止条約(APMBC)の第22回締約国会議議長国の優先テーマの1つに「地雷対策とWPSアジェンダの連携」を掲げており、1年を通じて、APMBCジェンダーフォーカルポイント(GSP)とも協力して同テーマの推進に取り組んでいる。
【活動・ステートメント】
2025年
2025年6月19日 対人地雷禁止条約第22回締約国会議会期間会合:ジェンダー、多様性及びWPSアジェンダに関する共同ステートメント
2025年6月19日 対人地雷禁止条約第22回締約国会議会期間会合:地雷対策とWPSの連携に関する我が国ステートメント
2024年
2024年11月29日 対人地雷禁止条約第5回検討会議におけるジェンダーの平等・WPS推進と地雷対策にかかる共同ステートメント(市川大使)
2024年2月21日 武器貿易条約(ATT)第10回締約国会議作業部会:条約履行作業部会(WGTEI) における我が国ステートメント (性に基づく暴力(GBV)及び女性・平和・安全保障(WPS)アジェンダ)(英文)
ジェンダー全般についてはこちら。女性・平和・安全保障(Women, Peace and Security : WPS)に関する安保理決議と行動計画の概要についてはこちら。
ジェンダー主流化についての議論は軍縮・不拡散の文脈でも活発化してきた。2018年5月にグテーレス国連事務総長が発表した軍縮アジェンダでは「軍縮と国際安全保障に関する意思決定プロセスにおける女性の完全かつ平等な参加」が呼びかけられた。その行動計画において、40あるアクションのうち2つが「平等、完全かつ効果的な女性の参画の確保」に充てられ、その実施のために、(1)国連が開催する会議や国連関連組織への男女平等な参画に向けた取組、(2)一方の性別のみが出席する委員会や行事への国連軍縮部の不参加又は問題提起、(3)軍縮関連会議への出席者の男女別データの集計・公表、(4)国連軍縮部及び地域センターによる女性の有意義な参加を促す能力構築支援事業の履行、(5)国連軍縮研究所によるジェンダーと軍縮に関する情報発信が掲げられた。
なお、2014年に発効した武器貿易条約は、第7条4項において、締約国は通常兵器の輸出許可に際し、輸出する兵器が「ジェンダーに基づく重大な暴力行為又は女性及び児童に対する重大な暴力行為を行い、又は助長するために使用される危険性を考慮する」ことを定めている。これは、武器の輸出を検討する際に、ジェンダーに基づく重大な暴力に繋がるリスクがないかを検討することを明記した最初の国際条約である。
【活動の状況】
日本は、軍縮・不拡散を含む平和・安全保障分野において、ジェンダー主流化に努めている。全ての関係当事者に対し、女性の参画を拡大し、国連の平和・安全保障活動のあらゆる面においてジェンダーの視点を採用するよう要請するWPSに関する国連安保理決議第1325号(2000年)の履行を支持し、WPSに関する行動計画を2015年に策定し、2019年に第2次行動計画、2023年に第3次行動計画を策定した。
さらに日本は、国連総会第一委員会や対人地雷禁止条約等の各種条約体の関連会合においてジェンダー共同ステートメントに参画し、国連における各種政府専門家会合に女性専門家を積極的に派遣するなど、ジェンダー主流化に取り組んでいる。我が国が毎年国連総会に提出している核兵器廃絶決議においても、2018年以降、軍縮不拡散分野におけるジェンダーの視点の重要性に言及している。
また、市川軍縮代大使は、2024年3月に、ジェンダー平等の促進に取り組むインターナショナル・ジェンダー・チャンピオンに就任した(市川大使が表明したコミットメント(S.M.A.R.T. Commitments)はこちら。
2025年、日本は、対人地雷禁止条約(APMBC)の第22回締約国会議議長国の優先テーマの1つに「地雷対策とWPSアジェンダの連携」を掲げており、1年を通じて、APMBCジェンダーフォーカルポイント(GSP)とも協力して同テーマの推進に取り組んでいる。
【活動・ステートメント】
2025年
2025年6月19日 対人地雷禁止条約第22回締約国会議会期間会合:ジェンダー、多様性及びWPSアジェンダに関する共同ステートメント
2025年6月19日 対人地雷禁止条約第22回締約国会議会期間会合:地雷対策とWPSの連携に関する我が国ステートメント
2024年
2024年11月29日 対人地雷禁止条約第5回検討会議におけるジェンダーの平等・WPS推進と地雷対策にかかる共同ステートメント(市川大使)
2024年2月21日 武器貿易条約(ATT)第10回締約国会議作業部会:条約履行作業部会(WGTEI) における我が国ステートメント (性に基づく暴力(GBV)及び女性・平和・安全保障(WPS)アジェンダ)(英文)