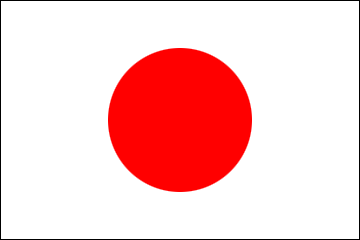宇宙空間における軍事・安全保障面での制度的枠組み
令和7年7月22日
【概要】
宇宙における軍備管理・軍縮の概要はこちら、宇宙全般に関する日本の取組みの概要はこちら、宇宙条約の概要はこちら。
近年、宇宙利用の多様化、宇宙活動国の増加、民間企業の参入に伴って宇宙空間の混雑化が進み、衛星破壊(ASAT)実験や人工衛星同士の衝突等によるスペースデブリが増加するなど、持続的・安定的な宇宙利用に対するリスクが増大していることを受け、宇宙活動に関する国際的なルール作りが活発化しており、安全保障面でも新たな国際的取組みに向けた動きが現れている。
ジュネーブ軍縮会議(CD)では、1985年から1994年まで「宇宙空間における軍備競争の防止(PAROS: Prevention of Arms Race in Outer Space)」に関する特別委員会が設置され、新たな条約の作成の必要性等につき議論が行われたが、実質的な成果は得られなかった。その後も、既存の合意の範囲内で信頼醸成措置を指向する西側諸国と、法的拘束力を伴った新たな国際約束を指向する中露その他の国々との対立構造が続き、2008年には、中露が「宇宙空間における兵器の配置及び武力による威嚇または武力の行使の防止に関する条約(PPWT)」案を提出した(2014年に改定版を提出)。西側諸国は、同条約案には兵器の定義の解釈や検証等の問題があり、まずは透明性及び信頼醸成措置から始めるべきとの立場をとっている。
国連総会第一委員会では、毎年、PAROSに関連した複数の決議案が提出・採択されている。
2014年以降、露が「宇宙空間に最初に兵器を配置しない(NFP)」決議案を提出。また、中露主導で、PAROSのための実際的な措置に係る政府専門家会合(GGE)が、2018-2019年(コンセンサスに至らず)及び2023-2024年(報告書発出)の2度にわたり開催された。これに対し、2020年以降、英国が主導し、我が国を含む22か国が共同で「責任ある行動の規範、規則及び原則を通じた宇宙空間における脅威の低減」決議案を提出。2022-2023年に国連オープンエンド作業部会(OEWG)が開催された(コンセンサスに至らず)。2023年には、露主導のPAROS・OEWG(2024-2028)と、西側主導の「責任ある行動」OEWG(2025-2026)の設立を決定する決議案がそれぞれ提出・採択されたが、2024年の国連総会にて、これら2つのOEWGを統合する決定案がエジプト・ブラジル等の主導により採択され、「宇宙空間における軍備競争のあらゆる側面における防止に関するOEWG」が2025-2028年に開催されることとなった。
2022年、米国が「破壊的な直接上昇地上発射型ミサイルによる衛星破壊実験(DA-ASAT)」決議案を提出、我が国を含む155か国の支持を得て採択された。
2024年3月に日米が提出した宇宙空間における核兵器等に関する安保理決議がロシアの拒否権行使により否決された。これを受けて、2024年の国連総会第一委員会において、我が国は、米国、アルゼンチンと共に、宇宙空間への核兵器の配備を禁止する宇宙条約(特に第4条)の遵守の再確認、宇宙への配備を目的とする大量破壊兵器の開発防止、宇宙条約の普遍化を主目的とする「宇宙における大量破壊兵器」決議案を提出し、167か国の賛成を得て採択された。ロシアは安保理決議と同様、配備禁止の対象をあらゆる兵器に拡大し、中露が推進するPPWTのナラティブに置き換える内容の修正提案を提出したが、いずれも否決された。
【活動の状況】
我が国は、宇宙空間における軍備競争は防止されるべきであるとの観点から、宇宙における軍備競争の問題に関する様々な論点につき総合的に検討し、以下の方針の下、CD等における議論に積極的に参加している。
【活動・ステートメント】
2025年
2025年7月22日 宇宙空間における軍備競争の防止(PAROS)のあらゆる側面に関するオープンエンド作業部会第2回会合における浪岡公使ステートメント
2024年
2024年10月30日 第79回国連総会第一委員会・クラスター3(「宇宙」)における市川大使ステートメント
2024年3月28日 軍縮会議(CD)本会議における「宇宙空間における軍備競争の防止(PAROS)」に関する市川大使によるステートメント
2023年
2023年9月1日 宇宙空間における責任ある行動に関するオープンエンド作業部会第4回会合(閉会セッション)における小笠原大使ステートメント(英文)
2023年8月28日 宇宙空間における責任ある行動に関するオープンエンド作業部会第4回会合における小笠原大使ステートメント(英文)
2023年7月6日 UNIDIR・日本共催ウェビナー「宇宙の持続可能性を目指して:宇宙安全保障のガバナンスとその取組の調査」
2023年4月11日 国連総会決議「宇宙活動に関する透明性・信頼醸成措置」(77/251)に基づく日本政府の意見書(英文)
2023年1月30日 宇宙空間における責任ある行動に関するオープンエンド作業部会に提出した我が国の作業文書(英文)
2023年1月30日 宇宙空間における責任ある行動に関するオープンエンド作業部会第3回会合における小笠原大使ステートメント(英文)
2022-2021年
2022年9月12日 宇宙空間における責任ある行動に関するオープンエンド作業部会第2回会合における小笠原大使ステートメント(英文)
2022年5月9日 宇宙における責任ある行動決議に基づく国連オープンエンド作業部会(OEWG)第1回会合におけるステートメント(英文)
2021年5月21日 「宇宙における責任ある行動の規範、規則及び原則に関するウェビナー」における小笠原大使の発言(英文)
宇宙における軍備管理・軍縮の概要はこちら、宇宙全般に関する日本の取組みの概要はこちら、宇宙条約の概要はこちら。
近年、宇宙利用の多様化、宇宙活動国の増加、民間企業の参入に伴って宇宙空間の混雑化が進み、衛星破壊(ASAT)実験や人工衛星同士の衝突等によるスペースデブリが増加するなど、持続的・安定的な宇宙利用に対するリスクが増大していることを受け、宇宙活動に関する国際的なルール作りが活発化しており、安全保障面でも新たな国際的取組みに向けた動きが現れている。
ジュネーブ軍縮会議(CD)では、1985年から1994年まで「宇宙空間における軍備競争の防止(PAROS: Prevention of Arms Race in Outer Space)」に関する特別委員会が設置され、新たな条約の作成の必要性等につき議論が行われたが、実質的な成果は得られなかった。その後も、既存の合意の範囲内で信頼醸成措置を指向する西側諸国と、法的拘束力を伴った新たな国際約束を指向する中露その他の国々との対立構造が続き、2008年には、中露が「宇宙空間における兵器の配置及び武力による威嚇または武力の行使の防止に関する条約(PPWT)」案を提出した(2014年に改定版を提出)。西側諸国は、同条約案には兵器の定義の解釈や検証等の問題があり、まずは透明性及び信頼醸成措置から始めるべきとの立場をとっている。
国連総会第一委員会では、毎年、PAROSに関連した複数の決議案が提出・採択されている。
2014年以降、露が「宇宙空間に最初に兵器を配置しない(NFP)」決議案を提出。また、中露主導で、PAROSのための実際的な措置に係る政府専門家会合(GGE)が、2018-2019年(コンセンサスに至らず)及び2023-2024年(報告書発出)の2度にわたり開催された。これに対し、2020年以降、英国が主導し、我が国を含む22か国が共同で「責任ある行動の規範、規則及び原則を通じた宇宙空間における脅威の低減」決議案を提出。2022-2023年に国連オープンエンド作業部会(OEWG)が開催された(コンセンサスに至らず)。2023年には、露主導のPAROS・OEWG(2024-2028)と、西側主導の「責任ある行動」OEWG(2025-2026)の設立を決定する決議案がそれぞれ提出・採択されたが、2024年の国連総会にて、これら2つのOEWGを統合する決定案がエジプト・ブラジル等の主導により採択され、「宇宙空間における軍備競争のあらゆる側面における防止に関するOEWG」が2025-2028年に開催されることとなった。
2022年、米国が「破壊的な直接上昇地上発射型ミサイルによる衛星破壊実験(DA-ASAT)」決議案を提出、我が国を含む155か国の支持を得て採択された。
2024年3月に日米が提出した宇宙空間における核兵器等に関する安保理決議がロシアの拒否権行使により否決された。これを受けて、2024年の国連総会第一委員会において、我が国は、米国、アルゼンチンと共に、宇宙空間への核兵器の配備を禁止する宇宙条約(特に第4条)の遵守の再確認、宇宙への配備を目的とする大量破壊兵器の開発防止、宇宙条約の普遍化を主目的とする「宇宙における大量破壊兵器」決議案を提出し、167か国の賛成を得て採択された。ロシアは安保理決議と同様、配備禁止の対象をあらゆる兵器に拡大し、中露が推進するPPWTのナラティブに置き換える内容の修正提案を提出したが、いずれも否決された。
【活動の状況】
我が国は、宇宙空間における軍備競争は防止されるべきであるとの観点から、宇宙における軍備競争の問題に関する様々な論点につき総合的に検討し、以下の方針の下、CD等における議論に積極的に参加している。
- 日本の安全保障及び宇宙空間の持続的かつ安定的な利用を確保すべく、同盟国及び友好国等と戦略的に連携する。
- 誤解や誤算によるリスクを回避すべく、関係国間の意思疎通の強化及び宇宙空間における透明性・信頼醸成措置の実施の重要性を発信する。
- 宇宙活動に関する国際的なルール作りをめぐる論点については、宇宙空間における軍備競争を防止すべく、実効的なルール作りを進めるという観点から、引き続き国際的な議論に積極的に参加する。
- 宇宙における「兵器」の定義は軍民両用(デュアルユース)性等に鑑みて困難。客観的に評価可能な「行動」に焦点を当てたルール作りを推進し、各国に宇宙空間における責任ある行動を求めていく。
【活動・ステートメント】
2025年
2025年7月22日 宇宙空間における軍備競争の防止(PAROS)のあらゆる側面に関するオープンエンド作業部会第2回会合における浪岡公使ステートメント
2024年
2024年10月30日 第79回国連総会第一委員会・クラスター3(「宇宙」)における市川大使ステートメント
2024年3月28日 軍縮会議(CD)本会議における「宇宙空間における軍備競争の防止(PAROS)」に関する市川大使によるステートメント
2023年
2023年9月1日 宇宙空間における責任ある行動に関するオープンエンド作業部会第4回会合(閉会セッション)における小笠原大使ステートメント(英文)
2023年8月28日 宇宙空間における責任ある行動に関するオープンエンド作業部会第4回会合における小笠原大使ステートメント(英文)
2023年7月6日 UNIDIR・日本共催ウェビナー「宇宙の持続可能性を目指して:宇宙安全保障のガバナンスとその取組の調査」
2023年4月11日 国連総会決議「宇宙活動に関する透明性・信頼醸成措置」(77/251)に基づく日本政府の意見書(英文)
2023年1月30日 宇宙空間における責任ある行動に関するオープンエンド作業部会に提出した我が国の作業文書(英文)
2023年1月30日 宇宙空間における責任ある行動に関するオープンエンド作業部会第3回会合における小笠原大使ステートメント(英文)
2022-2021年
2022年9月12日 宇宙空間における責任ある行動に関するオープンエンド作業部会第2回会合における小笠原大使ステートメント(英文)
2022年5月9日 宇宙における責任ある行動決議に基づく国連オープンエンド作業部会(OEWG)第1回会合におけるステートメント(英文)
2021年5月21日 「宇宙における責任ある行動の規範、規則及び原則に関するウェビナー」における小笠原大使の発言(英文)