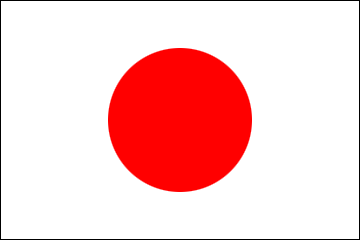国連軍備登録制度及び国連軍事支出報告制度
令和5年6月6日
国連軍備登録制度及び国連軍事支出報告制度各国の軍備の公開性と透明性を向上させることで信頼醸成を図り、過度の軍備の蓄積を防止する取組として、国連の枠組みにおける国連軍備登録制度と国連軍事支出報告制度がある。
1 国連軍備登録制度
(1)この制度は、1990年の湾岸危機においてイラクの過大な武器の蓄積が地域の不安定につながったという反省も踏まえ、1991年、日本が「湾岸危機後の中東の諸問題に対する当面の対策」を発表し、(1)主要武器輸出国に対する自粛と(2)通常兵器の国際取引の国連登録制度設立を呼びかけたことに端を発し、日本と当時の欧州共同体(EC)諸国が共同で国連総会決議案を作成し、同年成立させた「軍備の透明性」決議(A/RES/46/36L)に基づき設置されたものである。通常兵器の国際的な移転を中心とする軍備の透明性を向上させ、それにより各国の信頼醸成、過度の軍備の蓄積の防止を図ることを目的とした取組であり、当時、他に例を見ない画期的なものとして注目された。
(2)この制度の下では、国連加盟国に対し、過剰な蓄積によって地域及び国際社会の状況を不安定化させる恐れがあると位置付けられた7カテゴリーの通常兵器(I戦車、II装甲戦闘車両、III大口径火砲システム、IV戦闘用航空機及び戦闘用無人航空機、V攻撃用ヘリコプター及び回転翼無人機VI軍用艦艇、VIIミサイル及びミサイル発射基)につき、報告年前年の輸出入に関する情報、具体的には1年間の輸出入量、その輸出入相手国などを予め定められた書式に記入し国連事務局に提出することとなっている。また各国は軍備保有、国内生産を通じた調達に関する情報、関連政策などのデータの提出を奨励されている。
(3)1994年以降3年毎に開催される政府専門家会合では、7カテゴリーの定義、スコープ、運営などの見直しが行われ、政府専門家会合の勧告が含まれた報告書は、国連事務総長に提出され国連総会で承認されることになるが、これまで開催されたすべての政府専門家会合の報告書は、国連総会で承認されている。
(4)最近の取組として、2016年の政府専門家会合では、7つのカテゴリーに小型武器を加えた「7プラス1方式」での報告の試行的な実施、カテゴリー4への「無人戦闘機(UCAV)」の追加、オンライン登録サイトを全ての国連公用語に改訂することなどが勧告された。さらに2019年の政府専門家会合では、登録制度の目的や意義についての啓発活動やオンライン登録ツールの活用などを通じて、登録制度への参加を促進すること、報告対象とする小型武器の定義案、「7プラス1」方式を「試験的」ではなく任意の運用として継続すること、また、信頼醸成措置の履行に向けて報告を活用していくことが勧告された。そして、2022年会合では、カテゴリー5に「回転翼無人機」を報告対象とすることを明記したほか、トレーシング国際文書(ITI:InternationalTracingInstrument)に基づいた小型武器の定義を明確化し、軍備及び国内生産調達の報告様式の使用が勧告された。
(5)本制度には主要な武器輸出国が参加していることから、9割程度の国際武器移譲を網羅している。但し、毎年の登録数は減少傾向にあり、近年は50か国程度(2021年55か国)にとどまっており、今後本制度の一層の周知、参加促進を図ることが重要である。また、本制度に基づいて登録された各種情報は、「国連e-軍備登録制度」https://www.unroca.org/で閲覧可能である。日本は、本制度発足(1991年)以降、翌1992年から毎年登録を行うとともに、2019年会合では、ドイツと共に小型武器の定義を提案してコンセンサスを形成した。なお、武器貿易条約の締約国は、同条約の規定を実施するための国内的な管理制度の確立及び維持において、同条約の規定の対象となる兵器の定義を、国連軍備登録制度の定義よりも狭い範囲にすることはできないことが、同条約に定められている。
(2)この制度の下では、国連加盟国に対し、過剰な蓄積によって地域及び国際社会の状況を不安定化させる恐れがあると位置付けられた7カテゴリーの通常兵器(I戦車、II装甲戦闘車両、III大口径火砲システム、IV戦闘用航空機及び戦闘用無人航空機、V攻撃用ヘリコプター及び回転翼無人機VI軍用艦艇、VIIミサイル及びミサイル発射基)につき、報告年前年の輸出入に関する情報、具体的には1年間の輸出入量、その輸出入相手国などを予め定められた書式に記入し国連事務局に提出することとなっている。また各国は軍備保有、国内生産を通じた調達に関する情報、関連政策などのデータの提出を奨励されている。
(3)1994年以降3年毎に開催される政府専門家会合では、7カテゴリーの定義、スコープ、運営などの見直しが行われ、政府専門家会合の勧告が含まれた報告書は、国連事務総長に提出され国連総会で承認されることになるが、これまで開催されたすべての政府専門家会合の報告書は、国連総会で承認されている。
(4)最近の取組として、2016年の政府専門家会合では、7つのカテゴリーに小型武器を加えた「7プラス1方式」での報告の試行的な実施、カテゴリー4への「無人戦闘機(UCAV)」の追加、オンライン登録サイトを全ての国連公用語に改訂することなどが勧告された。さらに2019年の政府専門家会合では、登録制度の目的や意義についての啓発活動やオンライン登録ツールの活用などを通じて、登録制度への参加を促進すること、報告対象とする小型武器の定義案、「7プラス1」方式を「試験的」ではなく任意の運用として継続すること、また、信頼醸成措置の履行に向けて報告を活用していくことが勧告された。そして、2022年会合では、カテゴリー5に「回転翼無人機」を報告対象とすることを明記したほか、トレーシング国際文書(ITI:InternationalTracingInstrument)に基づいた小型武器の定義を明確化し、軍備及び国内生産調達の報告様式の使用が勧告された。
(5)本制度には主要な武器輸出国が参加していることから、9割程度の国際武器移譲を網羅している。但し、毎年の登録数は減少傾向にあり、近年は50か国程度(2021年55か国)にとどまっており、今後本制度の一層の周知、参加促進を図ることが重要である。また、本制度に基づいて登録された各種情報は、「国連e-軍備登録制度」https://www.unroca.org/で閲覧可能である。日本は、本制度発足(1991年)以降、翌1992年から毎年登録を行うとともに、2019年会合では、ドイツと共に小型武器の定義を提案してコンセンサスを形成した。なお、武器貿易条約の締約国は、同条約の規定を実施するための国内的な管理制度の確立及び維持において、同条約の規定の対象となる兵器の定義を、国連軍備登録制度の定義よりも狭い範囲にすることはできないことが、同条約に定められている。
2 国連軍事支出報告制度
(1)国連軍事支出報告制度は、1980年の国連総会決議35/142Bにより設立され、1981年から実際の運用が開始された。同制度は、各国が国連に自国の軍事支出に関する情報を一定の様式に従って報告する制度であり、透明性向上、信頼醸成に貢献するものとなっている。
(2)国連軍事支出制度の報告対象は、(1)人件費やメンテナンス費用などの運営費用、(2)調達及び建設費用、(3)研究開発費用であり、各項目の内訳も報告される。
(3)日本は1982年に最初の報告を行い、1997年以降毎年報告している。本制度への参加国数は2011年以降、2012年は51か国が提出したが、それ以降50か国を下回っており、2021年は38か国となっている。発足から30年を経た本制度の運用状況を見直すための政府専門家会合が、2010年から2011年にかけて開催され、本制度の信頼醸成措置としての有効性が確認されるとともに、報告様式の改訂などの改善策がとりまとめられた。最近では、2017年にも、同じ目的で専門家会合が開催され、軍事支出の総合計額のみを示した提出フォームの提出、軍隊を保持していない国への毎年軍隊未保有報告の実施、軍事支出のGDPに占める割合、前年度からの変更点、防衛政策、軍事戦略及びドクトリンなどの補足説明の提供等が勧告されると共に、改めて制度の有効性が確認された。これら専門家会合には我が国も参加し、議論に貢献してきている。なお、本件は、国連総会第一委員会に隔年で決議(A/RES/77/33)として提出されており、我が国は、軍事支出の透明性の問題を重視していることから、原共同提案国となっている。
(2)国連軍事支出制度の報告対象は、(1)人件費やメンテナンス費用などの運営費用、(2)調達及び建設費用、(3)研究開発費用であり、各項目の内訳も報告される。
(3)日本は1982年に最初の報告を行い、1997年以降毎年報告している。本制度への参加国数は2011年以降、2012年は51か国が提出したが、それ以降50か国を下回っており、2021年は38か国となっている。発足から30年を経た本制度の運用状況を見直すための政府専門家会合が、2010年から2011年にかけて開催され、本制度の信頼醸成措置としての有効性が確認されるとともに、報告様式の改訂などの改善策がとりまとめられた。最近では、2017年にも、同じ目的で専門家会合が開催され、軍事支出の総合計額のみを示した提出フォームの提出、軍隊を保持していない国への毎年軍隊未保有報告の実施、軍事支出のGDPに占める割合、前年度からの変更点、防衛政策、軍事戦略及びドクトリンなどの補足説明の提供等が勧告されると共に、改めて制度の有効性が確認された。これら専門家会合には我が国も参加し、議論に貢献してきている。なお、本件は、国連総会第一委員会に隔年で決議(A/RES/77/33)として提出されており、我が国は、軍事支出の透明性の問題を重視していることから、原共同提案国となっている。