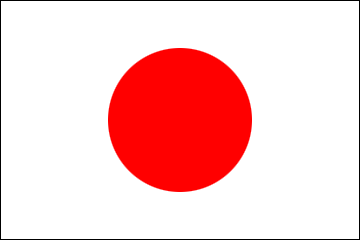日本提出の核兵器廃絶決議
令和5年5月23日
1 経緯
日本は、1994年以降毎年、核軍縮に関して日本が掲げる現実的かつ実践的アプローチに基づいた核廃絶のための決議案を国連総会に対して提出してきている。その内容は国際情勢の変化や核軍縮・不拡散の議論の変遷などを踏まえて更新され、賛成国の数や内訳も変化してきているが、この決議は国連加盟国の圧倒的な支持を得て毎年採択されてきている。また、我が国の核兵器廃絶決議には、非核兵器国のみならず、核兵器国も賛成票を投じて来ており、核兵器国を取り込みながら核軍縮を現実に進めようとする我が国の核軍縮アプローチを反映した結果となっている。
決議案の内容は、NPT運用検討会議のサイクルに合わせて5年ごとに大きく改定されており、1994年から1999年までは「究極的核廃絶」決議案を、2000年から2004年までは全面的核廃絶に至るまでの具体的道筋を示した「核兵器の全面的廃絶への道程」決議案を、2005年から2009年までは「核兵器の全面的廃絶への新たな決意」決議案を、2010年から2014年までは、2010年NPT運用検討会議において10年ぶりに全会一致で最終文書が採択されたことを受け、従来に比べてより包括的で核兵器のない世界に向けた国際社会の具体的行動を求める「核兵器の全面的廃絶に向けた共同行動」決議案を、2015年から2018年までは「核兵器の全面的廃絶に向けた新たな決意の下での共同行動」決議案を、それぞれ提出した。いずれの決議案も国連総会において圧倒的支持を得て採択されてきている。
決議案の内容は、NPT運用検討会議のサイクルに合わせて5年ごとに大きく改定されており、1994年から1999年までは「究極的核廃絶」決議案を、2000年から2004年までは全面的核廃絶に至るまでの具体的道筋を示した「核兵器の全面的廃絶への道程」決議案を、2005年から2009年までは「核兵器の全面的廃絶への新たな決意」決議案を、2010年から2014年までは、2010年NPT運用検討会議において10年ぶりに全会一致で最終文書が採択されたことを受け、従来に比べてより包括的で核兵器のない世界に向けた国際社会の具体的行動を求める「核兵器の全面的廃絶に向けた共同行動」決議案を、2015年から2018年までは「核兵器の全面的廃絶に向けた新たな決意の下での共同行動」決議案を、それぞれ提出した。いずれの決議案も国連総会において圧倒的支持を得て採択されてきている。
2 2019年及び2020年の核兵器廃絶決議
2019年は、国際的に厳しい安全保障環境が続く一方で、2017年に核兵器禁止条約が採択されるなど、核兵器国と非核兵器国のみならず、非核兵器国の間でも、それぞれの置かれた安全保障環境に応じて、核軍縮の進め方について立場の違いが一層顕在化していた。このような中、我が国は、2020年に予定されていた第10回NPT運用検討会議を見据え、各国の橋渡しに努め、 NPT体制の維持・強化に向けて国際社会が一致して直ちに取り組むべき行動の指針と未来志向の対話の重要性を強調する「核兵器のない世界に向けた共同行動の指針と未来志向の対話」決議案を提出した。同決議案は、160か国の賛成を得て国連総会本会議で採択された(同決議の文書番号:A/RES/74/63)。
2020年は、予定されていた第10回NPT運用検討会議が、コロナ禍の影響を受けて延期されたことを受け、2019年の決議をベースに修正を加え、前回と同じタイトルの決議案を提出し、150か国の賛成を得て国連総会本会議で採択された(同決議の文書番号:A/RES/75/71)。
2020年は、予定されていた第10回NPT運用検討会議が、コロナ禍の影響を受けて延期されたことを受け、2019年の決議をベースに修正を加え、前回と同じタイトルの決議案を提出し、150か国の賛成を得て国連総会本会議で採択された(同決議の文書番号:A/RES/75/71)。
3 2021年核兵器廃絶決議
第10回NPT運用検討会議が、コロナ禍のため2022年に再度延期されたことを受け、2021年も2020年の決議をベースに修正を加え、改めて同じタイトル(「核兵器のない世界に向けた共同行動の指針と未来志向の対話」)の下、決議案を提出し、158か国の賛成を得て、国連総会本会議で採択された(同決議の文書番号:A/RES/76/54)。同決議の前文では、過去のNPT運用検討会議の最終文書に含まれるコミットメントの履行の重要性の再確認、中東非大量破壊兵器地帯設置への支持の再確認、新戦略兵器削減条約(新START)の延長の歓迎、核兵器国間の更なる透明性のための具体的な行動の重要性の強調、軍備管理対話を開始する核兵器国の特別な責任の再確認、北朝鮮の核・ミサイル問題に関し、関連する安保理決議の想起、外交的努力の歓迎等がなされた。
同決議の主文では、国際的な緊張緩和、国家間の信頼強化及び国際的な核不拡散体制の強化等を通じ、第6条を含むNPTの完全で着実な履行にコミットすることが再確認されるとともに、共同行動の指針として、(1)透明性及び相互信頼の向上、(2)核リスク低減、(3)核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)の即時交渉開始に向けた取組、(4)包括的核実験禁止条約(CTBT)の署名及び批准、(5)核軍縮検証及び(6)核軍縮・不拡散教育、被爆者等との交流、被爆の実相の理解向上が奨励された。また、未来志向の対話として、(1)自国の核政策・ドクトリンの説明及び双方向の議論、(2)科学技術の進展が軍備管理・軍縮・不拡散に及ぼし得る影響に関する対話、(3)核軍縮と安全保障の関係に関する対話が奨励された。更に、関連安保理決議に基づく北朝鮮の全ての核兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイル等の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な放棄の実現へのコミットメント及び全ての国による関連安保理決議の完全な履行の義務が再確認され、北朝鮮に対し、NPT及びIAEA保障措置への速やかな復帰及びその完全な遵守が要請された。
同決議の主文では、国際的な緊張緩和、国家間の信頼強化及び国際的な核不拡散体制の強化等を通じ、第6条を含むNPTの完全で着実な履行にコミットすることが再確認されるとともに、共同行動の指針として、(1)透明性及び相互信頼の向上、(2)核リスク低減、(3)核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)の即時交渉開始に向けた取組、(4)包括的核実験禁止条約(CTBT)の署名及び批准、(5)核軍縮検証及び(6)核軍縮・不拡散教育、被爆者等との交流、被爆の実相の理解向上が奨励された。また、未来志向の対話として、(1)自国の核政策・ドクトリンの説明及び双方向の議論、(2)科学技術の進展が軍備管理・軍縮・不拡散に及ぼし得る影響に関する対話、(3)核軍縮と安全保障の関係に関する対話が奨励された。更に、関連安保理決議に基づく北朝鮮の全ての核兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイル等の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な放棄の実現へのコミットメント及び全ての国による関連安保理決議の完全な履行の義務が再確認され、北朝鮮に対し、NPT及びIAEA保障措置への速やかな復帰及びその完全な遵守が要請された。
4 2022年核兵器廃絶決議
コロナ禍による4回の延期を経て、ようやく2022年8月に開催された第10回NPT運用検討会議では、ロシア一カ国の反対によって最終文書のコンセンサス採択に至らなかったが、締約国間での真剣な議論を通じて、国際的な核軍縮・不拡散体制の礎石であるNPTの維持・強化の重要性を締約国が強く認識していることが示された。2022年10月に日本が提出した決議案(「核兵器のない世界に向けた共通のロードマップ構築のための取組」)は、NPT運用検討会議で岸田文雄内閣総理大臣が、「核兵器のない世界」という「理想」と「厳しい安全保障環境」という現実を結びつけるための第一歩として提唱した「ヒロシマ・アクション・プラン」(注)の内容、更に、同NPT運用検討会議における議論や、採択されなかった最終文書案の積極的要素をも踏まえて作成されている。この決議案は、第10回NPT運用検討会議が最終文書を採択できなかったことで核軍縮への機運が損なわれることを回避し、我が国として、「核兵器のない世界」を実現する上での現実的かつ実践的な取組の方向性を示す必要があるとの認識の下提出された。同決議案は、147か国の支持を得て国連総会本会議で採択された(同決議の文書番号:A/RES/77/76)。
決議の前文では、「核兵器のない世界」の実現という共通目標を再確認しつつ、 広島・長崎への原爆投下から77年を想起し、過去のNPT運用検討会議の最終文書におけるコミットメントの履行の重要性の再確認、ウクライナの状況含め国際安全保障環境の悪化や、いくつかの核兵器国が核戦力の急速な量的拡大や質的改良を行っていること等への懸念の表明、5核兵器国首脳共同宣言のコミットメントの履行に向けた具体的措置の必要性の確認、ウクライナのNPT加入に当たっての安全保証に関する覚書(ブダペスト覚書)を含む安全保証の遵守の重要性の再確認、中東非大量破壊兵器地帯設立への支持の再確認、核兵器使用の非人道的な結末に深い懸念の表明、指導者や若者等の広島・長崎訪問の歓迎、核兵器禁止条約の採択の認識、同条約の発効・第一回締約国会合開催への留意等が掲げられた。
決議案の主文では、核兵器が二度と使用されないこと及び核兵器使用に関する扇動的な表現を自制することの要請、核戦力・能力に関する具体的データの情報提供(含:核兵器用核分裂性物質(FM)の生産状況)等の透明性向上措置の要請、世界全体の核兵器数の減少傾向の維持の重要性の強調、核兵器国に対する核兵器の更なる削減の要請、包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期署名・批准の要請、核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)即時交渉開始及びFM生産モラトリアムの宣言を維持する又は新たに行うことの要請、核リスク低減に係る有効な措置の実施の核兵器国への要請、北朝鮮の関連安保理決議に従った全ての核兵器、既存の核計画、その他すべての既存の大量破壊兵器及び弾道ミサイル計画の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な放棄の実現へのコミットメント及び全ての加盟国による関連安保理決議の完全な履行の責務の再確認、北朝鮮に対するNPT及びIAEA保障措置の完全な遵守への早期復帰の要請、NPTの目標達成に有効な手段として、核軍縮・不拡散教育に向けた取組の要請(含:「被爆者」への言及)等がなされた。
決議の前文では、「核兵器のない世界」の実現という共通目標を再確認しつつ、 広島・長崎への原爆投下から77年を想起し、過去のNPT運用検討会議の最終文書におけるコミットメントの履行の重要性の再確認、ウクライナの状況含め国際安全保障環境の悪化や、いくつかの核兵器国が核戦力の急速な量的拡大や質的改良を行っていること等への懸念の表明、5核兵器国首脳共同宣言のコミットメントの履行に向けた具体的措置の必要性の確認、ウクライナのNPT加入に当たっての安全保証に関する覚書(ブダペスト覚書)を含む安全保証の遵守の重要性の再確認、中東非大量破壊兵器地帯設立への支持の再確認、核兵器使用の非人道的な結末に深い懸念の表明、指導者や若者等の広島・長崎訪問の歓迎、核兵器禁止条約の採択の認識、同条約の発効・第一回締約国会合開催への留意等が掲げられた。
決議案の主文では、核兵器が二度と使用されないこと及び核兵器使用に関する扇動的な表現を自制することの要請、核戦力・能力に関する具体的データの情報提供(含:核兵器用核分裂性物質(FM)の生産状況)等の透明性向上措置の要請、世界全体の核兵器数の減少傾向の維持の重要性の強調、核兵器国に対する核兵器の更なる削減の要請、包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期署名・批准の要請、核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)即時交渉開始及びFM生産モラトリアムの宣言を維持する又は新たに行うことの要請、核リスク低減に係る有効な措置の実施の核兵器国への要請、北朝鮮の関連安保理決議に従った全ての核兵器、既存の核計画、その他すべての既存の大量破壊兵器及び弾道ミサイル計画の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な放棄の実現へのコミットメント及び全ての加盟国による関連安保理決議の完全な履行の責務の再確認、北朝鮮に対するNPT及びIAEA保障措置の完全な遵守への早期復帰の要請、NPTの目標達成に有効な手段として、核軍縮・不拡散教育に向けた取組の要請(含:「被爆者」への言及)等がなされた。
5 結び
2022年12月、国連総会において「核兵器のない世界に向けた共通のロードマップ構築のための取組」」決議案が、核兵器国である米国(共同提案国)、英国及びフランス、並びに多くの非核兵器国を含む様々な立場の国々から支持を得て採択されたことは、8月の第10回NPT運用検討会議で最終文書が採択されなかったことで停滞しかねなかった核軍縮に向けての機運を維持し、回復させる上で意義があったと考える。
(注)ヒロシマ・アクション・プラン
2022年8月に開催された第10回NPT運用検討会議において、岸田総理大臣が発表した(1)核兵器不使用の継続の重要性の共有、(2)透明性の向上、(3)核兵器数の減少傾向の維持、(4)核兵器の不拡散及び原子力の平和的利用、(5)各国指導者等による被爆地訪問の促進、の5つの行動を基礎とするアクション・プラン。
(注)ヒロシマ・アクション・プラン
2022年8月に開催された第10回NPT運用検討会議において、岸田総理大臣が発表した(1)核兵器不使用の継続の重要性の共有、(2)透明性の向上、(3)核兵器数の減少傾向の維持、(4)核兵器の不拡散及び原子力の平和的利用、(5)各国指導者等による被爆地訪問の促進、の5つの行動を基礎とするアクション・プラン。